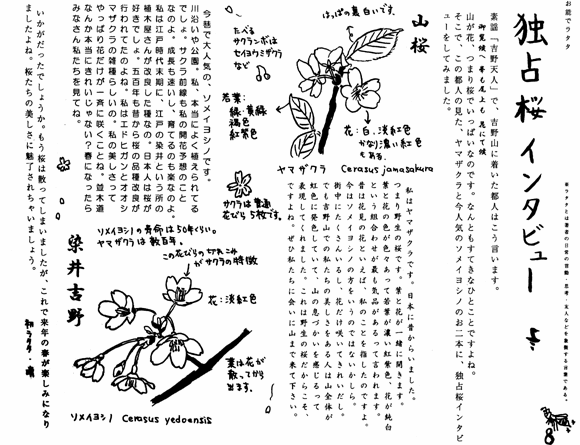
<五期生 H.Y>
■第五回 あやめ会■
|
平成十三年五月二十七日(土)午後二時始
第五回 あやめ会 連吟 鶴亀 仕舞 高砂 菊慈童 籠太鼓 素謡 吉野天人 招待校出演 佛教大学能楽部 素謡 橋弁慶 仕舞 小鍛冶キリ 雲雀山 天鼓 大江山 附祝言 終了予定 午後四時すぎ
|
|
連吟・鶴亀 鶴亀は、現行曲のうち本文が一番短くて、謡を習う人が、まず第一に稽古する入門曲となっています。実際に、私たちも、この曲を一番初めに教わりました。これは、古代の宮廷行事を能楽化したものです。年の始めの祝宴で、鶴と亀とが舞を奏し、皇帝自身も、立って舞うというものです。 昔、中国ではそれぞれの季節の始めに、月のように華麗な月宮殿で、四季の節会が行われました。その第一番目は正月です。まず官人が御代を讃えます。皇帝は大臣たちを従えて登場し、宮殿に座って、群臣から祝いの言葉を受けます。 ついで大臣は、毎年のように、鶴亀を舞わせることを奏聞します。亀は万年生き続け、鶴は千年生き続けることのできるというめでたい生き物。池の水際に遊ぶ鶴と亀は、皇帝の長寿を讃えてめでたく舞い納めると、皇帝も大喜びで、国土の繁栄を祈って、自ら舞い、やがて長生殿に帰ってゆきます。 今回は、大臣たちが皇帝に祝いの言葉を述べているところです。庭の砂は、まるで金銀のようです。扉は瑠璃で、階段はめのうです。そこにいる、鶴と亀はなんとめでたいのでしょう。 中国の桁はずれな宮殿は、今では故宮博物館となったかつての紫禁城などを見るとわかります。そしてその庭には、この謡の如く鶴と亀の大きな像が立っているそうです。
|
|
仕舞・高砂 「げにさまざまの舞姫の。声も澄むなり この謡い始めの文句の中に青海波というのがあります。模様にも青海波というのがあります。どういうものかというと、同心円を重ね、その弧を魚の鱗のように規則正しく並べたものです。そして、蒔絵、陶磁器、浮世絵等で多用されるデザインです。その名前の由来にもいくつかの説があるそうです。まず、名前の通り大海の青い波から取ったもの。次に「青海波」という管弦舞楽の装束によく使われたというもの。最後に江戸時代後期の蒔絵師に青海甚七という人がいて、この人が青海波を得意としていたということに由来するというものです。 しかし、名前の由来よりも、文様のほうが古いそうです。その起源は定かではないのですが四〜五世紀の女子埴輪の上着に、へら書きで付けられていたそうです。このように、着物等に使われていたり、名前に諸説あったり、多用されるということは、それだけ親しまれていたということでしょうかね。 今回、仕舞の所作で青海波の謡に合わせて「打ち込み」というものをします。自分の解釈ではこれは、一つ目の由来の通り、海、波を表すものだと思っています。そのつもりで舞いますので、注意して見てくださいね。
|
|
仕舞・菊慈童 昔むかし。中国が魏と呼ばれていたときのこと。山の麓から霊水が流れ出るというので、勅使が訪ねました。すると、山奥に一人で住んでいる少年を見つけます。迷子だろうか、それとも化物? 聞くと少年は周の王に仕えていた者だと言います。勅使は驚きます。周というのはもう数代も前の世なのですから。一体どういうことか? 少年は自分のことを話し始めます。王に仕えていたが、あやまって枕をまたいだため、この山に配流されたこと。哀れに思った王がその枕にお経を書いて与えたこと。そのお経を菊の葉に書き写し、その葉の露を飲んでいたこと。 実はその葉の露が霊薬となっていたので、このように少年は時を経ても若いままであったのです。少年も自分でびっくり。そして、ありがたいことですね、勅使さんも一杯いかが、と霊薬を勧めます。自分もその霊薬の酒を飲み、酔ってよろよろしたり、菊の上に臥したり。そして、魏の王に長寿の霊薬を捧げ、また山奥の家に帰っていくのでした。 この仕舞は謡と動きのつながりがわかりやすいと思います。そして、わかりやすい動作があるので、そのあたりをどうぞご覧下さい。
|
|
仕舞・籠太鼓 口論の果てに相手をあやめ、捕らえられるもすぐさま脱獄した関清次。清次の主人は身替りとして妻・おれい(仮名)を牢に入れる。清次の居所を明かせといかに迫られようとも、おれいは知らぬ存ぜぬで通す。 「あゝ、愛しのせいさんは今いずこ?」 おれいは嘆く。嘆きの深さに思いは乱れ、狂気の様相を呈す。その嘆きのわけを主人に問われ、おれいは答える。 「二世の契りを約した人と離れ、ただ一人牢に入れられ嘆かぬ者がありましょうか」 清次の行き先を言えば出してやる、と主人は再度言うが、おれいはそれを突っぱねる。 「私は知りません……たとえ知っていたとしても、言えばあの人は牢に入れられまた引き裂かれるのに、言うわけがありません」 牢には鼓が掛けられている。鼓を打って時を知らせつつ番人はおれいを見張る。鼓を見て、太鼓好きのおれいの目がキラリと光る。 「この太鼓……叩いてみてもよくって?」 清次を想いつつ鼓を打ち、舞うおれい。そしておれいには、清次の姿が見えてきて……。 「この牢を出るものですか。別れ別れになった今、私にとってはこの牢こそがあの人の形見。この中にいれば一緒にいるも同じ……」 実はおれいは清次の居所を知りながらかばっていた。清次の身を案じるおれいの心に打たれた主人は、ついに二人を許す。 おれいはすぐさま清次のもとへと行き、その後二人は末永く仲睦まじく暮らしましたとさ。太鼓叩きは嵐を呼ぶのよ。
|
|
素謡・吉野天人 すでに桜の季節は過ぎておりますが、このお話は都人が、桜の名所として有名な吉野山に、桜見物をしに行く場面から始まります。吉野山に着いた都人は、山いっぱいに咲き誇る桜を見て楽しんでおりますと、一人の女性と出会うことになりました。女性はこの近くに住む者で、都人と同じく、桜を楽しむためにこの山に来たと言います。同じく花を愛する者同士打ち解け合い、共に花の景色を楽しみます。ところが都人は、その女性がいつまで経っても帰ろうとしない事を不審に思うようになりました。女性にその事を尋ねてみると、実は自分は天人で、この桜咲く吉野山のおもしろさに惹かれて降りて来たのだと打ち明けるではないですか。そして続けて言うには、今夜、この場所で信心するのならば、天女が降臨して天衣の袖を五度翻して舞ったといわれる伝説の舞、「五節の舞」をお見せしましょうと言って、立ち去ってしまいました。 さて夜になり、都人が奇特を見るために、言われたとおりしておりますと、やがて虚空から音楽が聞こえ、天人が空から舞い降りてきました。そして天女は約束の通り、桜に戯れながら五節の舞を舞い始めます。その情景はまさに、 「天つ風雲の通い路吹き閉じよ乙女の姿しばしとどめよ」 と詠われたこと、そのものでありました。しかし、世にも美しい舞いもやがて終わりを迎えることになります。舞を舞い終わった天人は、雲に乗り再び天空へと消えていったのでした。 桜の名所吉野山は、作中の都人と同じく大勢の人が訪れる場所ですが有名な話として豊臣秀吉が文禄三(一九五四)年四月一七日、徳川家康ら大名を大勢引き連れ、豪華な花見の宴を開いたと記録にあります。ちなみに吉野山が桜の多い山となったのは、修験道の開祖・役行者が蔵王権現を桜の木に刻んで祀ったことから、桜を御神木としてあがめるようになったことに由来するようです。
|
|
素謡・橋弁慶 比叡山西塔近くに住む武蔵棒弁慶は、ある願事があって、五条の天神へ丑の時詣をしていました。今夜は満参、最後の日です。そのことを従者に話すと、気になることを言われます。 「昨日、五条の橋の上で、十二、三才の子供が人を斬りつけたそうです。まるで蝶か鳥のようなすばやさだったと。今夜の参詣はおやめください」 これを聞き弁慶は、何をおっしゃるうさぎさん、と言わんばかりに、大勢で捕まえればよいではないか、と言います。いやいや、奴はたぶん人間ではなく化生の者です。危険です、と従者に言い返され、弁慶も弱気になり、今夜の参詣をやめようとしました。ですが、 「いや、弁慶ですらおそれをなして逃げた、と言われたらたまらんぞ。俺が五条の橋へ行って、そいつを討ち取ってやる!」 と、出掛けていきました。 さて五条の橋の上。いました噂の人物、牛若丸。彼は今夜限りで都を去り、鞍馬山に上ることになっていました。夜も更けて、最後の相手を待っています。 そこに登場した、やる気満々の弁慶。大長刀を肩にして、我ながら強そうだ、と自信も満々です。そんな弁慶を牛若丸は見つけ、薄絹をかぶり、喜んで近づきました。弁慶も牛若丸に気が付きますが、なんだ女性ではないか、と思い、その場を去ろうとしました。すると、牛若丸が長刀の柄を蹴り上げます。怒った弁慶は斬りかかります。ところがどっこい。この牛若丸、本当に強いのです。弁慶は翻弄されてしまいました。そこで名を聞くと、源義朝の子、牛若丸であることがわかります。そりゃかなう訳がない、と弁慶は降参し、主従の契りを結び、一緒に帰っていったのでした。 この牛若丸(のちの義経)と弁慶がこの秋再び登場します! 十月十四日第六回淡海能・能楽『船弁慶』乞う御期待!
|
|
仕舞・小鍛冶キリ 伝説の刀匠、三条小鍛冶宗近。長刀鉾の長刀を始め、数々の名刀を打った彼も、このたびばかりは困っていました。帝から霊刀を打つように勅令が下ったのです。 「そのような優れた刀を打つには、私と同じ技量の相槌が必要なのです」 「いや、これは勅令であるから、なんとしてでも打つように」 勅使にそう言われ、困り果てた宗近は氏神である稲荷大社に祈願に出かけます。その途中、不思議な少年に出会いました。 「いいから、家で待っててごらん。いい相槌が見つかるよ」 少年の言葉を信じて、鍛冶場を整えて待つ宗近。するとそこへ、稲荷明神が現れます。祈りが天に通じたのです。 鍛冶が始まると、さすがは神様。宗近に劣らぬ腕前です。宗近を師、明神を弟子としてトンテンカンと刀を打ち始めました。 かくして霊刀を打ち上げ、表に宗近が銘を入れます。すると、稲荷明神もその裏に『小狐』と銘を刻みました。稲荷明神の神通力によって『小狐丸』は天叢雲剣もこのようであったのかと思わせるような、風を呼び、雨を降らせる霊力を得たのです。 「この力が有れば、五穀は豊作となり、国は豊かとなるであろう」 勅使と宗近に言い残し、稲荷明神は東山に帰っていったのでした。
|
|
仕舞・雲雀山 右大臣藤原豊成の息女・中将姫は成長するにつれて容姿端麗で英知に富み、何事にも優れていたので、帝から中将の官位を賜ったのである。ところが、姫を陥れようとしたものの言うことを信じた父・豊成によって、殺害されそうになる。姫を殺せと命令を受けた従者は、あまりに姫を哀れに思い、殺すことができず、乳母とともに中将姫を雲雀山にかくまうことにした。そして乳母は姫を養うために、里に下りては、人々に花を売って歩くようになる。 あるとき、豊成は雲雀山に狩りに出かけるが、そこで姫を思うばかりに、心が乱れた乳母が花を売っているところに出くわす。乳母は豊成一行に、花を買ってくれるように頼み、花や鳥に託して姫の境遇を語り、舞う。豊成は、花を売っているのが乳母だと気が付き、騙されていたとはいえ、自分が姫を殺そうとしたことを大いに悔い、その後、姫と無事に再会するのだった。 仕舞で舞うことになるのは、乳母が山中の生活を余儀なくされる姫の不憫な境遇を語る場面です。恋ゆえや、子を失って物狂いになる狂女者とは異なる、異例の狂乱であることが、この雲雀山の特徴です。 また、雲雀山は一名『太刀捨山』とも呼ばれており、これは雲雀山で姫を殺そうとした従者が、姫を殺すことができずに、太刀を捨てた事に由来しています。
|
|
仕舞・天鼓 少年は母が天より鼓の降るのを夢で見た時に懐妊したことから、天鼓という名を付けられた。やがて実際に天鼓の元へ降って来た鼓は、打つと美しい音を響かせ、人々を喜ばせたという。 噂を聞いた皇帝はぜひともその鼓が欲しくなり、臣下を送るたが天鼓は手放そうとしない。鼓を持って山中に逃げ隠れたが捕まり、鼓は奪われ、自身は川に沈められてしまう。ところがこの鼓、誰が打っても音が出ない。これでは意味がない、持ち主と離れ離れになった事を嘆いているのだろうか。皇帝は天鼓の父に鼓を打たせようと思い立つ。 物語はここから始まる。皇帝に遣わされた臣下は、天鼓の父に内裏へ来て鼓を打つように命じる。もしや我が子と同じように、私をも殺そうとの命令か。いや、例えそうであっても仇である皇帝の顔を一目見てやろう。天鼓の父は内裏へと向かう。 形見である鼓が目前に出される。なぜ自分はこの様に老いてなお生きのび、我が子は殺されたのか。涙を流してよろよろと鼓を打つとそれはそれは美しい音を奏でた。皇帝は哀れに思い、天鼓の父に数々の宝、天鼓には形見の鼓での弔いを約束する。 月の美しい夜、天鼓が沈められた川で弔いが行われる。しばらくすると波が大きくなり、川から天鼓の亡霊が現れた。皇帝の命令に背いた事から地獄で苦しんでいたが、弔いによって救われたという。この喜びを夜が明けるまで、愛器での舞楽で披露しよう。
|
|
仕舞・大江山 源頼光は、大江山に住む鬼――酒呑童子――を退治せよとの命をうけて、山伏に変装し、大江山に向かいました。鬼に捕まえられていたという女の手引きで、その住家に行き、道に迷ったと言い宿を求めます。酒呑童子は、頼光たちを少しも疑いません。身の上話をして、酒を飲み始めます。やがて、すっかり酒が回り、寝てしまいます。その姿を見てみると、それまでの愛くるしい姿ではなく、鬼の形相になっていました。そして頼光たちはすきをついて襲い掛かり、その首を取って都に帰りました。 今回の仕舞は、最初に「酒の肴には、なにがよいかなあ」と言います。そして酒を飲み、そのまま寝てしまうまでです。 何度も盃を口にして、顔もすっかり赤らんだようだ。でも、顔が赤いのは酒のため。鬼だからだとはお思い下さるな。と言っております。そして、有明けの月の頃にはすっかり酔ってしまい、足元がよろよろとしながらも、荒々しく障子を押し開けて、そのまま寝入ってしまうのです。 この「おおえやま」とは、丹波と山城の境の大枝山と、丹波丹後の境にある大江山との二説あります。そのどちらにも、このお話の主人公である酒呑童子にまつわる旧跡や名所が残っているようです。
|
|
附祝言・猩々 昔、親孝行者の高風という男が、夢のお告げ通り市でお酒を売ってお金持ちになりました。彼のお客には不思議なことにいくら飲んでも顔色の変わらない人がいました。彼は海に住む猩々だと言います。高風はその言葉を信じて夜、海辺で彼を待ちます。 再び会った時、彼は本来の真っ赤な妖精の姿でした。二人は酒盛りをします。元々赤いのですからいくら飲んでも顔色が変わるはずがありません。自分を信じてくれたお礼にと、猩々は高風に永遠に涸れることのない酒壷を贈ります。そこで高風は眠りから醒めるのですが…。 醒むると思えば泉はそのまま 尽きせぬ宿こそ めでたけれ 高風の家はいつまでも栄えたそうです。
|
|
お能でワハハ 小鍛冶とキツネと五行説 小鍛冶宗近と稲荷明神が打ち上げた太刀・小狐丸。なぜ、現世利益……商売繁盛の神様である稲荷明神が刀を打つのでしょう。また小狐丸が雨を呼び、五穀を実らせるとはどういうことなのでしょうか。実は、稲荷明神の使いがキツネであることが大いに関係していたのです。 その謎を解くために、最近人気の陰陽五行説を見ていきましょう。五つの属性、木・火・土・金・水に全ての事柄が分類できる、とされています。漢代の中国人による分類では、キツネは土に属しています。穴を掘って大地の中に住み、その体の色が土の色、黄色だからです。「キツネは油揚げが好き」というのも、土の属性が生み出した伝説。油揚げも黄色いでしょう? 念のため言っておきますと、タヌキは雑食ですが、キツネは肉食です。 五行説には、それ単独の性質の他に、互いの属性が影響を及ぼす関係が二つあります。一つは、木から火が生まれ、火から土が生まれ、土から金が生まれ、金から水が生まれ、水から木が生まれる、という五行相生説。もう一つは、木は金に滅ぼされ、金は火に滅ぼされ、火は水に滅ぼされ、水は土に滅ぼされ、土は木に滅ぼされる、という五行相剋説です。この二つの理論が宇宙を支配しているという考え方が、五行説なのです。 五行相生説で見ると、土は火より生まれ(火生土)、金を生む(土生金)。なんと、キツネは鍛冶向きの性格……というか性質をしているのです。鍛冶場には当然ながら火があります。鍛えられる鉄は金そのものである金属。火から生まれる土のキツネは、金属を自由に生み出し、操ることができると考えられたのでしょう。ちなみに、金には money の意味も含まれています。ここから現世利益の神になるわけですね。 しかし、相生説の説明だけでは、雨を呼んだり、穀物を実らせることはできそうにありません。そこで、五行相剋説を見てみましょう。土は水を妨げ(土剋水)、木に侵食される(木剋土)ことになっています。文字通り、堤防となって治水をし、五穀をはぐくむ土台となる能力を秘めていたのですね。それだけではありません。土そのものにも、「種まきと収穫」という意味があるのです。 小狐丸にはこんな逸話もあります。あるとき、小狐丸を帯刀していた九条経教の頭上に雷が落ちました。経教は電光石火の早業で小狐丸を抜き放ち、雷を打ち払った……といわれています。雷は「稲妻」「稲光」といわれるように、稲作と関係があるとされていました。見た目が稲穂に似ているから、ともいわれますが、夏の雷雨が大地を潤し、作物をはぐくむことが、雷を農業と結びつけたのでしょうか。 稲荷明神は元々、その頭文字の「稲」に表されているように、農業の神様だったのです(どうりで「おいなりさん」こと「いなり寿司」は米俵の形をしていますね)。農業の神様が創った太刀なのですから、農業に有利なように天候を――時には雷さえ――自由に操ることができる、と考えたのですね。 そうそう、稲荷明神は狐神だと思っている方も多いでしょう? 最初にも書きましたが、キツネはあくまで「お使い」なのです。伏見稲荷大社の祭神は「宇迦之御魂神」という人面蛇体の蛇神。元を正せば、倉庫に忍び込み、穀物を食い荒らすネズミを食べてくれるヘビが農業の神だったのですね。ちなみにヘビは水に属しています。は虫類らしく水辺にいることや、川の流れをヘビに見立てたのでしょうね。
|