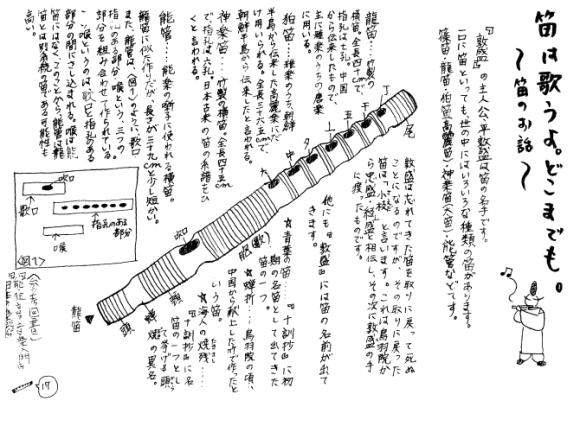
<八期生 M.I>
■第六回 あやめ会■
|
平成十五年五月二十四日(土) 十三時始
連吟 鶴亀 仕舞 竹生島 杜若キリ 柏崎道行 鞍馬天狗 素謡 吉野天人 仕舞 嵐山 清経キリ 雲林院クセ 羽衣キリ 素謡 土蜘蛛 仕舞 敦盛クセ 胡蝶 網之段 富士太鼓 猩々 終了予定 十五時頃
|
|
仕舞・竹生島 竹生島は琵琶湖の北に浮かぶ島です。この島には宝厳寺というお寺があり、西国三十三箇所の札所になっています。でも、このお話の主役は琵琶湖の龍神さまと弁才天さまです。 昔むかし、醍醐天皇に仕える役人が竹生島に参詣に出かけました。大津の浜辺に着くと、そこには舟に乗った漁師のおじいさんと海女さんがいました。役人はなんとかおじいさんに頼んで、竹生島まで舟に乗せて行ってもらうことになりました。 ところで、知ってますか? 波が立って荒れた琵琶湖を。湖際の道路を歩いていると波がかかるんですよ。そんな日はとても手漕ぎの小舟なんかだせません。あっという間に転覆してしまいます。だから、詣でた日は天気もよく、穏やかだったんでしょうね。旧暦の三月半ばとありますから、今でいえば四月の中旬に当たります。そんなうららかな日差しの中、一向は竹生島に向かいます。 島に着き、参詣をすると、おじいさんと海女さんは正体を現しました。実はおじいさんは龍神さま、海女さんは竹生島に祀られている弁才天さまだったのです。この二人はそれぞれめでたい舞を見せると、帰って行きました。
|
|
仕舞・杜若キリ 諸国一見の僧が、三河国八橋へやってきました。沢辺に杜若が今を盛りと咲いています。そこへ女性が現れ、僧に話しかけます。 ここ八橋は、在原業平が和歌を詠んだ場所。その和歌とは「からころも/きつつなれにし/つましあれば/はるばるきぬる/たびをしぞおもふ」という、「か・き・つ・ば・た」の五文字を一句一句の頭に置いたみごとなもの。業平は都に残してきた愛する人を思い、この歌を詠んだのです。業平は歌舞の菩薩の生まれ変わりでした。その為、業平が詠んだ和歌さえも経文となり、非情の草木までが成仏できるのです。 実は女性は杜若の精なのでした。彼女も業平の和歌のおかげで成仏できるのです。それこそが草木国土悉皆成仏。やがて夜も白々と明け始め、杜若の精は悟りを開き、消えてしまいました。 能には、業平物と呼ばれる一群があります。「杜若」はそのうちの一つです。今回の舞台、縁あって私のもう一つの仕舞も業平物の「雲林院」となりました。これも歌舞の菩薩の生まれ変わりの業平様のなせる業でしょうかね。これを機に、昔男の伊勢物語をざっと読んで(眺めて)みました。いやはや、歌物語とはよくいったものですね。私もさらさらと和歌を詠めるような人になりたいものです。
|
|
仕舞・柏崎道行 あら。そこの子たち。何? 何がおかしいの? 私の狂った姿がおかしいのですって? おお、嫌だ。情けある人ならば慰めてくれこそすれ、笑うだなんて。私はね、夫に先立たれたの。そして一人息子は父の死を儚んで出家してしまい、行方も知れないのよ。これでは狂わない方がどうかしててよ。 私を置いて逝くなんてひどい人。それより夫亡き後、何よりの形見となるのは子どもだというのに傍にいてくれないなんて薄情な子。それでも私はあの子の無事を祈らずにはいられないの。行かなくちゃ、この柏崎を出て……。 越後の国府へ着いたわ。人の多い所だけど私には人目に構ってる余裕なんてない。いつまでこうして狂えばいいのだろう、とは思うけれど。吹き過ぎる松風も淋しいここは常盤の里。三人の子を連れて旅する常盤御前の苦労が思い起こされるわね。木島の里。雉は己が身を焦がしても我が子を救うのよね。淡雪が降っているけど積もらないわ、ここは浅野だもの。東に見えているのは井上の山。ここから西へ進めば善光寺だわ。善光寺には生身の阿弥陀如来様がおわします。おお、阿弥陀様、どうか夫を浄土へお導き下さいませ。
|
|
仕舞・鞍馬天狗 鞍馬寺東谷の僧が稚児たちと西谷で花見を楽しんでいるところへ、一人の山伏がやってきました。それに興ざめしてしまった僧たちは、花見もそこそこにそそくさと帰って行きました。しかしそこに独り取り残された稚児がいました。そうです、彼が牛若丸だったのです。山伏と牛若丸は花見の友となり、京都周辺の花の名所を巡りました。そして実は自分は大天狗の化身であると明かした山伏は、いつの日か平家討伐の望みが達せられるように兵法を伝授することを、牛若丸に約束し立ち去りました。 さて、仕舞はここからです。鞍馬に名だたる大天狗が現れ、牛若丸に兵法を惜しみなく伝授し、「会稽をすすがん」と源家再興を前祝します。そして別れを惜しむ牛若丸に、将来の守護をも誓い去っていきます。 孤独な二人が心を通い合わせる、温かくも切ないお話です。
|
|
素謡・吉野天人 毎年春になると、花見に出かけることにしている都の者が、今年は吉野の桜を見ようと、仲間を伴い吉野山深くへとやって来ました。すると一人の里女が現れました。都人たちが怪しんで何者かと尋ねると、女は言いました。「自分はこの辺りに住むもので、一日中花を友のようにして過ごしているのだ」と。それを聞いた男は、「花を愛する心は同じだ」、と帰ることをも忘れしばらくの間一緒に花を眺めていました。しかしあまりにもいつまで経っても帰ろうとしない女を、いよいよ不審に思いました。すると女は、「実は自分は天女であり、花の美しさに引かれて地上に来たのだ」と言いました。そして「今夜ここに残ってくれるというならば、古の五節の舞を月明かりのもとで舞って見せましょう」と言って消えました。都人たちは月下に現れる天女の姿を信じ、日が暮れるまで待ちました。すると不思議なことに虚空に音楽が聞こえ、この世のものとも思えない香りが満ちて、天から花が降り落ちてきました。そして天女は現れ、花に戯れ美しい舞を舞って見せました。そして再び花の雲に乗り、どこかへと消えてしまうのでした。 ところでここ彦根城も桜が大変綺麗な所ですね。季節的には少し遅かったのですが、彦根城の美しい桜を思い出しながら、この謡を聞いてみてください。そして忙しい日常を少しの間だけ忘れ、この天女や都人たち、または私たちと共に時が経つのを忘れてはみませんか……。しかしここ彦根城博物館は五時閉館ですのでお気を付けて……。
|
|
仕舞・嵐山 今や、桜の名所として名高い京の嵐山。ですが、もとを正せばその桜は奈良の吉野から移されたもの。平城京で親しんだ美しい桜を、平安京の近くにも移そうと考えられたものなのです。 さて、天皇の花見の先遣として嵐山を訪れた勅使。桜の下では花守の老夫婦が掃除をしています。感心、感心。 ところが、老夫婦は勅使に言うのです。私たちは吉野から桜を守るためにやってきた子守明神・勝手明神の化身であると。驚く勅使を置いて、明神たちは正体を現し、桜を愛でて舞い始めます。すると、吉野の奥、金峰山にいらっしゃるはずの、蔵王権現までも現れるではありませんか。 嵐山も桜が満開だったため、世の中がきちんと治まっていることを知った蔵王権現は、世界を、人々を救おうと誓います。天から足を下ろして大地を踏みしめ、人々の苦悩を解消。天に手を挙げて、世界に渦巻く煩悩を浄化するのです。また、悪魔もたまらず降伏してしまう三つの目で、地上を、人々を見守り続けよう、と。 そうして、蔵王権現と子守・勝手明神は神通力をはたらかせ、嵐山を花へ、梢へと舞い遊びます。その様子はまるで、霊験あらたかな吉野山が、そのまま嵐山に移ってきたかのようではありませんか。なんともめでたい春の景色なのでした。
|
|
仕舞・清経キリ 源平の合戦により、都を追われた平清経の家を妻は寂しく守っていました。ある日、その妻の元へ使者が訪れました。名を淡津三郎と言うその男は、妻に清経が自害した事を告げると形見の遺髪を渡します。しかし自分を置いて一人で死んでしまった清経を恨み、妻は使者に遺髪をつき返してしまいます。 夜になり、夫の死を悲しみ、泣き伏している妻の枕元に清経の霊が現れます。清経は遺髪を受け取らなかった妻を責めたてます。しかし妻は戦か、または病で命を落とすのならともかく、私一人を置き去りにして自害するとは、と恨み嘆くので、清経はなんとか慰めようと自分が自殺した動機を語り始めます。戦に負け、追われる者の身となった焦りや、無益な抗戦への懐疑から、死ぬ事を決意し、月を仰いで好きだった笛を吹くと、念仏を唱え入水したと話します。そして修羅道に堕ちた苦しみを語りましたが、死ぬ間際に唱えた念仏の功徳のおかげで成仏する事が出来たと喜びます。 さて、その清経が堕ちたと言う修羅道とは。辞書によりますと、六道の一つで、現世で慢心・猜疑心の強かった者や、闘争を起こした者が死後に堕ちるという世界です。ここに堕ちた者は、怒り、恨み、憎しみの闘争を繰り返して、その苦しみを受け続けなければならない、という世界です。恐ろしいですね。
|
|
仕舞・雲林院クセ 「雲林院」とは、京都にあった天皇の離宮です。そこへ、公光という人がやってきました。ちょうど桜の季節でした。いずれ散ってしまうのだし、と公光は桜の枝を折りました。すると老人が現れ、それを咎めます。二人はそれぞれ和歌を引いて、言い合います。 ◇公光、素性法師の和歌 「見てのみや人に語らん桜花手毎に折りて ◇対する老人、藤原好風の和歌 「春風は花のあたりを避ぎて吹け心づからやうつろふと見ん」春風は桜を避けて吹いてくれ。桜が自分から散るものなのかを見たいから。 風流人対決ですねえ。桜の枝を折る人を見かけたら、言ってみましょう。ただし、このような風流人対決ができるかはわかりませんが。 結局、お互い桜を愛でる気持ちからの行為、といった訳で仲直りした(?)二人。公光は老人に、夢で在原業平と二条の后がここ雲林院に現れたため、やってきた事を話します。老人は公光に眠って待つように告げると消えてしまいました。 夜が更け、公光の夢に業平が現れました。そして伊勢物語の秘事、すなわち業平と二条の后の叶わぬ恋の物語を語ります。やがて夢は覚めてしまい、業平も消えてしまいました。
|
|
仕舞・羽衣キリ ある日のことです。漁師の 「いや疑いは人間にあり、天に偽りなきものを。」 白龍は反省しました。そして天女に羽衣を返し、天女はその羽衣を身につけ優美な舞を舞い始めます。 仕舞はこの辺りからです。天女は羽衣の袖を風になびかせて舞い、さらに国土に宝を降らせます。そして最後は天上に帰る時が来たと、三保の松原から浮島が原へ、さらに このように「羽衣」は天女の美しい舞です。私も天女のように美しくありたいと願う今日この頃です。
|
|
素謡・土蜘蛛 ある時、かの有名な源頼光は病に臥せってしまいました。典薬の頭から薬を預かった胡蝶は頼光のもとを訪れ、病のためか弱気になる頼光を励まします。 そんな頼光の所へ、深夜に怪しい僧侶が訪れました。 「いかに頼光、御心地は何と御座候ぞ。」 名も知らぬ僧侶がいきなり夜中に現れるとは、明らかに怪しい。頼光は 「不思議やな誰とも知らぬ僧形の。深更に及んで我を訪う。その名は如何におぼつかな」と、尋ねます。すると僧は正体を明かし、七尺(約二〇〇cm)もの大きさの蜘蛛となり頼光に襲い掛かります。しかしここは頼光。枕元にあった剣・膝丸を抜くと、臆せず蜘蛛に斬りかかります。蜘蛛も負けじと千筋の糸を投げかけてきますがついには姿を消してしまいました。 その騒動を聞きつけ、心配した独武者が頼光のもとへ駆けつけます。頼光は今しがた起こったことを独武者に語り始めます。深夜に見知らぬ僧が現れたこと。その正体が七尺もある土蜘蛛だったこと。そしてそれを膝丸で撃退したこと。頼光は土蜘蛛を撃退したことを称え、膝丸を蜘蛛切と名付けました。 さてさてそこで独武者はといいますと、頼光が斬りつけてできた土蜘蛛の血の跡を見つけ、頼光に土蜘蛛退治を申し出ます。頼光もそれを承諾し、独武者は土蜘蛛退治に出かけます。 数人の供を連れ、血の跡を追って行くと塚に着きました。独武者たちは塚を崩し石を反すと、塚の中から火焔や水が放たれます。しかし独武者たちはなおも塚を崩して行くと、ついに岩間の影から土蜘蛛が姿を現します。土蜘蛛は、自分が昔葛城山に住んでいた土蜘蛛の精であること、そしてこの世に災いをもたらそうと思い、邪魔な頼光を亡き者にしようと図ったが、却ってこっちがやられそうになった事を告げます。 その事を聞いた独武者は土蜘蛛に向かい斬りかかります。しかし流石は土蜘蛛。独武者たちに向かい糸を投げつけるとたちまち手足を縛って動けなくしてしまいました。これで終わりかと思われましたが、独武者たちは神の加護を信じ、再び土蜘蛛に斬りかかります。そして土蜘蛛が剣の光に少し怯んだのを機に一気に斬りつけると、ついにその首を討ち取ります。そして大いに喜んで都へと帰って行くのでした。
|
|
仕舞・敦盛クセ 治承・寿永の乱で平家が敗れてから数年の後、僧・蓮生は一の谷を訪れていた。彼の出家する前の名は熊谷直実といい、源氏の武将であった。彼は一の谷の合戦のときに、平家の若武者・敦盛を手にかけて世の無常を感じ、法然上人のもとで出家したのだった。 蓮生が一の谷に着くと、丘のほうから笛の音が聞こえてきた。それは丘で草を刈る男たちのうちの一人が吹いていたのであった。他の草刈り男たちが帰るなか、笛を吹いていた男だけは残っている。不審に思い、蓮生が尋ねると、彼は「念仏に導かれて来た」と答える。彼は蓮生に殺された敦盛の霊だったのだ。 一旦は去った敦盛だが、その夜蓮生のもとに再び現れた。そして、自分の最期の様子を語った。―一の谷での戦が敗色濃くなってくると、平家一門は船に乗り、落ち延びていった。しかし、敦盛は父から贈られた「さ枝」という笛を置いてきてしまい、それを取りに行っているうちに船は出てしまった。そうこうするうちに直実に見つかってしまった。直実も敦盛が少年だとわかると見逃そうとするのだが、そばに他にも源氏の兵がおり、それも叶わず敦盛は討ち取られたのだった。 敦盛の幽霊はしかし、自分を殺した直実を恨んでいなかった。むしろ、自分のために念仏を唱えてくれ、おかげで自分の罪も消える、と感謝して去っていくのだった。
|
|
仕舞・胡蝶 胡蝶の精は四季折々の花と戯れます。あっちの花からこっちの花へ。羽袖を風にたなびかせ舞い遊びます。 しかし、そんな胡蝶にも悩みがありました。それはどうしても会えない花がある事。まだ寒さの残る早春にそのつぼみを解く梅の花。甘い香りをかぐ事も、小さく可憐な花弁を愛でる事も、胡蝶の精には許されません。 どうしても、どうしても梅の花と戯れたい。胡蝶の精は梅の花に恋焦がれます。 そんな時、春が近づいては来たものの、まだ寒さの残るそんな季節に、吉野の奥に住む僧侶が都の一条大宮へとやってきます。梅の花が咲き乱れ、そのあまりの美しさに足を止め眺めていると、人間の女性に姿を変えた胡蝶が近づいてきました。しかしその女性が胡蝶の精だとは知らない僧は、この御殿や梅の花について詳しく語ってくれるこの女性の名を聞き出そうとします。すると少し渋った後、女性は実は胡蝶の精である事を明かします。そして自分が早春に咲く梅の花とは戯れられない事が悲しく、僧の読経によって功徳を得たいと頼みます。そしてまた夢の中で会いましょうと言い残すと姿を消してしまいました。 その夜、僧は胡蝶に言われた通り経を読むと、夢の中に梅の花と舞い遊ぶ胡蝶の精が現れます。そして僧に読経の功力によってやっと梅と会えたと感謝し、やがて明けてゆく空に、霞にまぎれて消えて行くのでした。
|
|
仕舞・桜川網之段 三年前。筑紫国で桜子という少年と生き別れた母親。流れ流れて、桜の名所・常陸国は桜川へとたどり着いた。 そこへ、僧侶と少年が現れる。母親は語る……。 風が吹けば花は散る。桜花は風を恨んでいるのでしょうか。いえ、花は切なく、風自身もやりきれない気持ちなのでしょう。花が散れば風が吹き、風が吹けば花は散る。それでも桜花は咲くのです。青々とした糸桜、霞のように見えるのは樺桜、その向こうに見えるのは吉野の山々でしょうか。 遠く離れた桜川で、こうしてたゆたう桜花をすくい上げていると、鮎が……吉野の「國栖魚」が足に触れてくるのです。そういえば小鮎は「桜魚」というのでしたね。 それにしても美しい景色。どちらを見ても真っ白な花、花、花。桜花がまるで雪のようです。こうして桜をすくってみれば、あの子のことが思い出されて……。 なんと、これは。これは桜木の花ではありませんか。私が探し求めているのは我が子・桜子。桜子や、どこへ行ってしまったの。ああ、桜子や……。 その時、傍らの少年がつぶやく。 もしや、あなたは筑紫のご出身ではありませんか。私は……。
|
|
仕舞・富士太鼓 「内裏での管弦のお役に選ばれたのは夫の富士ではなく浅間さんでした。けれど、浅間さんに劣らぬ自信のある夫は京へ押し掛けたために浅間さんの恨みを買い、殺されてしまったのです。 形見の舞装束を見つめ、私は思いました。恨むべきはあの太鼓、打って恨みを晴らしましょう、と。この装束を身に着けて、あの人と一緒に……」 「この撥は今や剣だ。怒りの炎は天に届くだろう。けれど天に届きたかったのは俺だ。お役を賜り雲上人になりたかった。在りようは富士颪に翻弄される桜みたいなもんだったが。この装束の模様はその散った桜かもな。こんな美しい装束では刺す動き引く動きもまるで舞の型だ。そうだ、舞には音楽がいるな。太鼓の役は当然、俺だろう。名声に恥じぬこの響きはどうだ、素晴らしいだろう? ああ、懐かしい……」 「打って恨みは晴れました。今は後生を願い五常楽を打ちましょう。それから君の長命を祈り千秋楽を、世の太平を願い太平楽を。西には日が沈み行きます。その山の端を眺めながらの日を招き返すという舞の型。その型には思いを込めずにはいられません。時よ戻れ、そしてあの人の命も、と……」 「おお、うれしい、敵が討てた。太鼓の音に耳を澄ませば心の煙は晴れていく。恨みを晴らした今、この涙は……」 「……うれし涙と思わなくては。これで私はお暇致します。ああ、でも最後に太鼓をもう一度、敵だけれど形見でもあるあの太鼓をもう一目見て……」
|
|
仕舞・猩々 中国に、高風というたいそう親孝行な男がいました。彼はある夢を見ました。それは市でお酒を売ればお金持ちになるというもの。夢の通りにお酒を売ると彼はお金持ちになりました。ところで、いつも市にやってきて、酒を飲む男がいました。この男、いくら飲んでも顔色ひとつかえません。高風が名を尋ねると、海中に住む猩々だと明かし、去っていきました。 そこで高風は入り江で酒壺を置き、猩々がくるのを待ちます。すると現れました猩々。高風に会うため、そして彼と酒を飲み交わすため、やってきたのです。ご機嫌な猩々は舞い、高風の素直な心を誉め、尽きることのない酒壺を与え海中に戻っていきました。 と、高風は目を覚まします。今のはすべて夢? しかし、猩々からもらった酒壺はありました。尽きることない酒壺のおかげで、高風の家は末代まで栄えたのでした。 この演目は祝言能でもあります。そのため、会の最後に仕舞をするときは、附祝言はありません。というわけで、本日の公演はこれにて終了です。また秋にお会いしましょう。
|