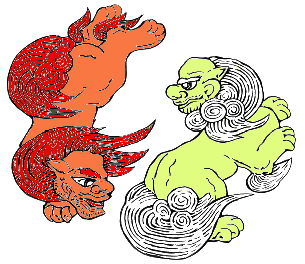
能楽『石橋』
| ◆あらすじ◆ |
| 中国は清涼山、文殊菩薩の浄土といわれる霊地でのお話。寂昭法師―俗名、大江定基―がはるばる日本からこの清涼山へ訪れました。ここには有名な石の橋があります。自然にできたものなのです。その石の橋を渡った先に文殊菩薩の浄土があるのです。寂昭法師はその石橋へたどり着きました。そして、向こう岸へ渡ろうと思いますが、まずはこの橋のことを誰か地元の人に聞いてからにしようと考えます。 折りよく樵の少年が現れました。寂昭さんの尋ねに答え、これこそ有名な石橋だと答える少年。しかし、寂昭さんが今にも渡ろうとするのを樵少年は止めるのでした。相当修行を積んだ人でないと無理ですよ、と。 この長さ10メートルたらずの橋、なんと幅はわずか30cmしかありません。しかもその表面は滑りやすい苔ですっかり覆われています。そんな石の橋が何千メートルもの谷の上に、わずかに岩に引っかかるようにしてかかっているのです。誰しもが息を飲む凄まじさです。 渡ることを思いとどまった寂昭さんに少年は橋の功徳を語って聞かせます。その時、向こうの浄土より笙歌が聞こえてきました。神仏影向の兆しです。もうすぐよいものが見られるからここで待っているように、というと樵の少年は消えていきます。 頃は五月。山は今、牡丹の花の真っ盛りです。そこへ現れたのは獅子でした。文殊菩薩の乗り物である獅子が山に咲き乱れる牡丹の花に戯れながら勇壮に舞います。その姿を寂昭さんに見せて、獅子は文殊菩薩の下へと帰っていくのでした。 |
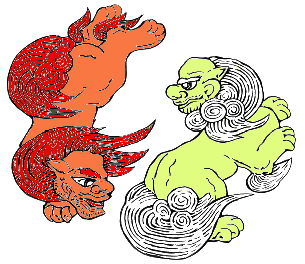
全文掲載(現代語訳付き)
左側が原文、右側が現代語訳です。
下に注釈がついています。
◆場面1・寂昭さん登場◆
*1 お父さんは大江斉光さん。大江匡衡さんは従兄に当ります。匡衡さんは赤染衛門の旦那さんです。赤染衛門は百人一首の「やすらはで寝なましものをさ夜更けてかたぶくまでの月を見しかな」で有名ですね。定基さん自身も有名人ですよ。今昔物語集、宇治拾遺物語などにエピソードが載ってます。文章・和歌が上手く、字もたいそうきれいな才人でしたんですって。定基さんの経歴を軽く説明しておきましょう。生年は分かっておりません。永延二年(988)に出家して寂昭法師と名を改め、長保五年(1003)に宋に渡りました。中国の皇帝から円通大師の号を賜りました。長元七年(1034)、日本へ帰ることなく中国の杭州で亡くなりました。七三歳だったともいわれています。とすると逆算して生れたのは961年ごろですね。27歳で出家かあ。出家の経緯などについてはまた別に改めて。すごいんだから。 *2 唐とは中国、天竺とはインドのことですね。寂昭さんが行ったころは唐ではなくて宋でしたし、インドまでは行っておられないんですけれど。でも語呂がよいですしね。 *3 中国の名高き仏教霊地の一つです。五台山とも言います。山西省にあります。ここは文殊菩薩さまの浄土があるところだとされています。『華厳経』の「菩薩住処品」にそう書いてあります。 *4 天然の岩が橋のようにかかっているところが本当にあるんです。それは、ずいぶん昔から有名でした。けれど、その有名な石橋は本当は清涼山ではなくて天台山(浙江省)にあるのです。天台山も有名な霊場です。けれど、この謡曲『石橋』ではこの橋は清涼山にあるとしてつくられています。 *5 文殊師利菩薩さま。智慧の仏さまです。梵語ではマンジュシュリー。釈迦三尊像で普賢菩薩さんと一緒にお釈迦さまの脇を固めてらっしゃいますね。文殊さんは獅子に乗っておられます。「獅子には文殊やめさるらん(玄象)」ですね。仏さまはいろんな方がいらっしゃいますが、この文殊さまのモデルとなった方、実在してらしたそうですよ。たいそう聡明なお方だったとか。 |
◆場面2・童子登場◆
*1 「山路に日落ちぬ 耳に満てるものは笙歌牧笛の声 澗戸に鳥帰る 眼に遮るものは竹煙松霧の色」という紀斉名さんの漢詩があります。詩のほうでは物理的に視界を遮る靄や霧のことをいっていますが、ここではそれを受けて人の生きていく道の前に立ちはだかるもののことに思いをなしているわけですね、童子くんは。なんだか難しいや。 *2 これは「山遠くしては雲行客の跡を埋む 松寒くしては風旅人の夢を破る」という漢詩から。これまた紀斉名さんの作。雲がきた道をもう見えなくしているよ、という状況の表現を借りてきたのですね。あとでわりと唐突に「松の風もなし」と言われるのは紀斉名さんの漢詩の方では夜の眠りを覚ますほどの松をゆする風が吹いているけど、ここでは吹いてないよ、ということなのでしょう。 *3 これもです。漢詩。「謬ちて仙家に入りて 半日の客たりといへども 恐らくは旧里に帰りて 纔かに七世の孫に逢はむことを」大江朝綱さんの作です。この詩は二つの仙境伝説をふまえてあります。一つは、仙人が碁を打つのを見ていてふと気がついたらそばにたて掛けておいた斧の柄が朽ちてしまっていた、という話。もう一つは、薬草を取りに天台山に入りそこで出逢った仙女さんと遊んで帰ったらもう、七代の孫の世になっていたというお話です。「実はここは仙境で、帰ったら浦島太郎状態なんじゃないかな?」とおののくほど美しい、神秘的ということなのですね。この作品はお花見をしていたときのものだそうです。よっぽどきれいだったのね、桜。 以上三つの漢詩は『和漢朗詠集』に収められています。講談社学術文庫のものを参考にいたしました。きれいな和歌や漢詩がたくさん載ってて面白いご本ですよ。 |
◆場面3・寂昭さん、通りすがりの童子に橋を渡ることを止められる◆
*1 本当に長い修行の上に橋をお渡りになった方がおられるそうです。東晋(317~420)のころの帛道猶さんという方。橋を渡ること以前に、橋のところまで辿り着くのも大変だったようなんですが……資料が漢文なので読むのにてこずってます。もう少し解読に時間をかけたいと思います。すみません。もっとはっきり分かったらここ書き直すからね。 *2 捨身の行とは身を捨てて修行に励むことです。悟りを得んがため、まさに捨て身でがんばるのです。 |
◆場面4・石橋の恐ろしさを語る◆
*1 一丈はおよそ3メートルとお考え下さい。といってもまあ、ここは「ものすごく長い」というふうに捉えていただければ。 *2 一尺は、時代によっていろいろ変動もありましたが概ね30センチとお考え下さればよろしいかと。 |
◆場面5・橋のありがたさを語る童子◆
*1 石橋が虹のようだということは『元亨釈書』で円珍さんがそこを訪れた時の描写に出てきています。「下華頂傍溪行至石橋。橋如虹梁跨深谷。其下萬丈水聲如雷。」"華頂"とは天台山の最高峰のことです。 *2 神様が天上界と地界とを行き来される時に使う橋です。古事記や日本書紀でおなじみのお話ですね。 *3 橋とは“こちら”と“あちら”を結ぶものであります。これを渡るとどこへ着くのかしらん、というような。けれどそんなことより、実際の生活においてはなによりも水の危険を避けて通るために作られているんですよね。そういうことをうっかり忘れていましたわ、私。そうですよね。橋がないと溺れてしまいますね。水で隔てられていないところへしか行けなくなりますし。橋ってありがたいものですね。 |
◆場面6・神仏の影向を待てといって童子は消える◆
*1 妙なる音楽が鳴り、美しい花びらが降りしきるのは菩薩さまや神様が来られるときのしるしなのです。菩薩さまがおられるところはきっといつでもそうなんだろうなあ。で、あといい匂いもしているというのがお決まりなのですがここではもちろん、牡丹の香り、ですよね。くんくん。 |
| ◆場面7・<アイ狂言>◆ |
| 舞台ではここでアイ狂言による語りが入りますが省略いたします。舞台を見てお話を聞いてくださいね。 |
◆場面8・獅子登場◆
*1 「獅子」とは舞楽の曲名です。日本にもいろいろな形で伝わる獅子舞のルーツです。お正月の獅子舞だとか越後獅子だとかいっぱいありますね。この能楽の獅子舞も、もちろんそこから派生したうちの一つです。獅子舞を能楽に取り入れる試みがなされたのがこの『石橋』なのです。 *2 「団乱旋」も舞楽の名前です。「とらでん」と読みます。「とら」の音と獅子の友だちの「虎」とをかけてここでは出されているのです。 *3 このように牡丹の豪華絢爛名美しさをうたった漢詩からの引用です。そのタイトルも「牡丹芳」。作者は白居易さんです。冒頭を少し紹介しておきますね。 「牡丹芳、牡丹芳、黄金蕊綻紅玉房。千片赤英霞爛爛、百枝絳■(豊+盍)燈煌煌。照地初開錦繍段、當風不結蘭麝嚢。仙人琪樹白無色、王母桃花小不香。………(もっと長く続きます)」 |