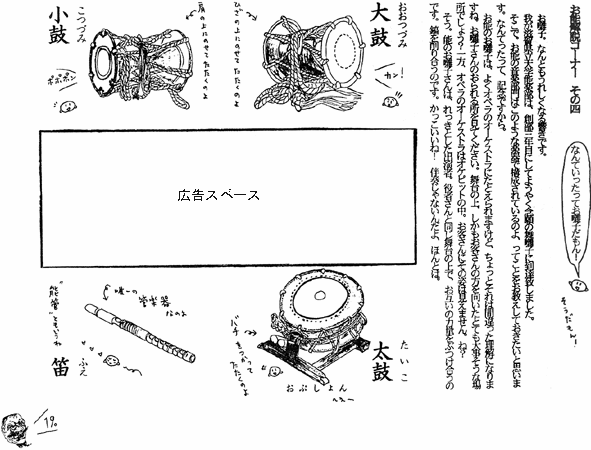
<一期生 R.M>
■第二回 淡海能■
|
平成九年九月二十八日(日)午後一時始
素謡 鶴亀 仕舞 嵐山 小袖曽我 花月クセ 舞囃子 玄象 吉野天人 羽衣 招待校出演 京都橘女子大学能楽部 素謡 大仏供養 招待校出演 佛教大学能楽部 舞囃子 敦盛 胡蝶 猩々 連吟 竹生島 番外仕舞 菊慈童 鞍馬天狗 附祝言 終了予定 十六時半頃
|
|
学長挨拶 能再論 滋賀県立大学学長 日高敏隆 この前の号にぼくは、能とはシンボリックな芸術ではなく、すべて謡いによって説明された物真似である、というぼくの研究の結論を書いた。 じつはこれは、今ぼくが考えていることであって、もっと前には能についてぜんぜんちがうことを考えていた。それは、能は動物の行動と同じなのではないか、ということだった。 もう三十年近く昔、ぼくはあるフランスの動物行動学者を能に連れていった。フランス語しかしゃべれない、かなり俗っぽいそのフランス人の男が日本に来たからにはぜひ日本の能を見たいというので、どこかの能楽堂へ見にいったのである。 始めのうちは、彼はかなり興奮して舞台に見入っていた。そのうちにだんだん飽きてきた。ぼくは売店にいって、その曲の台本を買い、謡の大要をフランス語で通訳してあげることにした。そうすれば、話の筋が少しはわかるだろうと思ったからである。 観客席を見まわすと、見ている日本人たちの多くは、たいてい眠っている。ぼくもだんだん退屈してきたし、えんえんとつづく動きの鈍い舞は、大筋を説明してあげても、フランス人にはまったくわからないらしかった。 実はぼくが能を見るのはこれが初めてだった。お恥ずかしいことに、それまでぼくは能というものを一度も見たことがなかったのである。 けれどぼくは、これは前にも見たことがあるような気がしてきた。それも一度や二度ではなく、何度も見てきたような気になってきたのである。 なぜだろう?と考えているうちに、ぼくははっと思い当たった。そうだ、これは動物の行動と同じなのだ。動物の行動はちょっと見ただけでは何のことかわからない。けれどその一つ一つの動作には約束事としての意味があり、それを知っていればその動物が何を言おうとしているのかがわかる。 そうだ、能はこれと同じなのだ。舞や所作の約束ごとの意味を知れば、筋もわかり、感動もできるのだ。 そういうことに気がついたとき、能は終わっていた。能楽堂を出ながらぼくは、フランス人に聞いた。「おもしろかったか?」「とてもおもしろかった。」「また見たいか?」「いや、もう見たくない。」 その後ぼくは、このことを新聞のコラムに書いた。それはぼくの本にも収められている。ぼくはこの思い付きに、かなり自信をもっていた。 けれどそのうちに、これは二流の動物行動学者の言っていることと同じであることがわかってきた。だいたい能にはそんな「約束ごと」などはごく少ししかない。手を目の前にかざすのは泣いていることを示す、などというのは俗論だ。 ぼくは能がまたわからなくなってしまった。十年ぐらい悩んだ末、当時、京大の研究生で、言語の動物行動学をやってみようとしていた桃木暁子さんと、本格的に能の退屈さの研究を始めることにした。前号に書いたのは、この共同研究の当面の結論である。 |
|
顧問挨拶 滋賀県立大学能楽部顧問 脇田 晴子 今週、二回目の淡海能が、彦根城の能舞台で開かれることになりました。部員の皆さんの活動の賜物です。 能楽は今、新しい注目の時代を迎えているといわれています。Tシャツの背中に、能面が描かれていたり、「卒塔婆小町」という劇団があったり、能楽を見ないでも、能楽的雰囲気を楽しむ風潮が出てきました。新しい国風文化の時代といいましょうか。 明治以来、西洋近代に伍して、追いつけ追い越せと頑張った日本近代は、学校教育もすべて西洋近代風にして、音楽も西洋音楽一辺倒にして、邦楽は切って捨ててきました。音階も絶対音階ではないと、未開人の音楽だということになってしまいました。能楽は絶対音階ではないので、やはり評価は低かったのです。 このごろは「フアジイ」という言葉がはやりだして、この日本的な曖昧な微妙で繊細な味が、評価されるようになってきました。外国人でも熱烈に好きな人と、全く嫌いな人にはっきり別れるようです。外国人の日本文化研究者には、熱烈なファンが多いし、能楽研究者の比重は相当多いといえます。 能楽は永い間、公武の貴族の封鎖的世界の中で生きてきたので、素晴らしいけれど、中に一歩、足を踏み入れた人でないとわからない難解な芸術になっているようです。 しかし、能楽は十四・五世紀から始まる伝統芸術の根幹で、当時は津々浦々、村々長々の年中行事には、どこでも能楽が上演されたもので、大衆芸能だった時代もあるのです。後の時代の歌舞伎も文楽人形浄瑠璃も、すべて能楽を基本として、展開していくものです。また、能楽を媒介として源氏物語などの平安王朝の物語の世界や源平合戦の歴史物語も大衆の教養に受け入れられました。日本文化を理解するには、能楽を見るのが、そして、やってみるのが一番早いと、私は思っています。奮って見に来て下さい。 |
素謡・鶴亀
鶴は千年。亀は万年。
何故に鶴さんと亀さんはめでたいのでしょう。
カメは確かに長生きするようです。
アルダブラゾウガメ。そんなおまじないのような名を持つカメがいます。
そんなカメが、百三十年間、人間の手で育てられたという記録があります。
しかも、捕獲されて時にはすでに、生れてから四、五十年は経っていたというのです。
するとですな。百八十年ぐらいは生きていたという計算になるではありませんか。
カメの長生き話をもう一つ。
ご存知、ダーウィン。彼がガラパゴス島へ探検に出かけたときのこと。
彼はゾウガメの甲羅に印をつけました。
そして彼がガラパゴス島を去ってから九十年の月日がながれました。
月日は百代の過客にして行きこう年もまた旅人なり。
とある探検家がガラパゴス島へ行きました。
そしてダーウィンが印をつけたゾウガメの生存を確認したのです。
ツルのことは存じません。
玄宗皇帝が大勢の家臣に囲まれて、新春を言祝ぐお話。毎年恒例の鶴さんと亀さんの舞もあり、皇帝はご機嫌で、自分も舞います。めでたしめでたし。能天気め。極楽とんぼ。それだから……。おい。
<一期生 R.M>
|
仕舞・嵐山 嵐山はとってもかっこいいお仕舞です。けれど、私が舞うとかっこいいかどうか…。私は去年の淡海能に吉野天人、春のあやめ会では班女、となんだか女っぽい仕舞ばかりでしたが、今回は豪快な男の神様です。名を蔵王権現。正式なお能では、この神様は真っ赤な髪をふりかざし、ギラギラ光る装束を着ています。顔もちょっと恐い。その上男の神様なので威勢が良く、飛んだり跳ねたりします。 今までのお仕舞とは歩き方から違って、外股で大きく歩くのですが、練習のとき、つい癖で内股になってしまい、変な格好になってよくみんなに笑われました。こういうところに、つい私の品のよさが出てしまうのね。というか、意識していなかった自分の体の動きに練習で気づくことはよくありました。やっぱり普段から姿勢とか、歩き方とかがきちんとしてないと、いきなり舞うときだけきれいにはできないものです。私は猫背を直すようにがんばっています。 それにしても嵐山はやっぱり難しい、というのを練習のたびに思います。お能にはいろんな動きの型があるんですが、この嵐山は今までやったことのない型が多いうえ、動きも速いので型がきちんと出来ないと、とってもかっこわるくなってしまう。だから私にとって彦根城の能舞台で嵐山をするのはなかなか怖いことです。本番は下手すると「飛び返り」という技でコケてしまうかもしれませんが(これが一番不安)、どうか優しく見守っていて下さい。
|
|
仕舞・小袖曽我 これは曽我十郎・五郎の仇討ちの、ほんの少し前のお話です。 頼朝の富士の裾野での巻狩に参加し、父の敵、工藤祐経を討つことを決めた二人。しかし、この時五郎は母親の勘当を受けていました。彼らの許しを乞いに相模の母のもとを訪ねます。 母は最初、頑として五郎を許そうとはせず、一時は十郎までが勘当を言い渡されてしまいますが、二人の熱心な態度にとうとう勘当を解くと声をあげるに至ります。 さて場面は一変し、狩場への門出を祝う宴となり、酌をし合って兄弟で相舞を舞い、最期は宿願の成ることをほのめかし、勇んで門出をするのです。私が仕舞として舞っているのはこの最後のあたりです。 この後、仇討ちは成功しますが彼らもまた殺されてしまう運命にあります。(この辺は能『夜討曽我』を参照)兄弟の母はそれが分かっていたからこそ、なかなか勘当を解かなかったのかもしれません。 とはいえ、仕舞は父の仇が討てる晴れがましさと意気込みが感じられる場面です。武士の勇ましさなどが表現できるといいなあ。
|
|
仕舞・花月クセ 昔々、清水寺に喝食(お寺さんで食事などの世話をする人)をしていた美しい少年がいました。名は花月。本名ではないが彼は、そう名乗り、恋の小唄などを謡います。さて、清水寺にひとりの僧がやって来ました。実は花月の父親で、花月は七つの時に天狗にさらわれたんです。そして、再びめぐりあいめでたし、めでたしで終わります。 これが能としての花月の流れだが、今回のお仕舞は、直接の流れには、関係ない。ではどの部分を部分を舞うかというと、美しい少年花月が清水寺の縁起を謡う部分が今回のお仕舞である。そのお仕舞の話をさせて頂くと「皆人手を~」という所で手を真横にする所が大きくて好きだ。他にもあるが紙面の都合で…カット。 <おまけ>
|
|
舞囃子・玄象 “玄象”というのは、琵琶の名前です。玄象は、中国から伝わった、ちょっとただ者ではない琵琶です。鬼に盗られたことがあるとか、上手に弾かないと腹を立てて鳴ろうとしないとか、内裏が火事になった時、誰も持ち出していないのにひとりでに庭に出ていた、などという不思議な話が『今昔物語』に出ています。何だか魂が宿っているような感じがしませんか。実を言うと、ここまでの話は、本筋とは全く関係ありません。題が「玄象」というくせに、玄象はほとんど関係ないのです。玄象は、あと二面の琵琶・青山と獅子丸とともに中国から伝えられました。青山は、平経正の愛用の琵琶だったことで有名ですが、獅子丸は日本に来る途中、嵐で海底に沈んでしまったのです。能「玄象」は、この獅子丸が後半にメインで出てきます。 太政大臣・藤原師長は、天下に並ぶ者なき琵琶の名手。琵琶の奥義をさらに極めようと渡唐を思い立ちます。途中、摂津国須磨の浦に立ち寄った師長一行は、海士の老夫婦の家に一泊します。老夫婦に請われ、師長が琵琶を奏でていると、村雨の音が演奏を妨げます。すると老夫婦は、苫で板屋を葺き、雨の音を師長の琵琶の音の調子と合わせてしまいます。驚いた師長が一曲を所望すると、尉は琵琶を、姥は琴を見事に演奏します。師長は、上には上がいたことを悟り、渡唐を断念して去ろうとします。二人はそれを引き止め、「今は何をかつつむべき。われ玄象の主たりし村上の天皇梨壷の女御夫婦なり」と正体を明かして消え失せます。やがて再び村上天皇が現れ、龍神に命じて龍宮にある獅子丸を持って来させます。そして師長にそれを授け、秘曲を伝えて、飛行の車に乗って立ち去ります。 舞囃子は、初めてなので覚えることもたくさんありました。舞の形にも初めてやるのものがあったり、笛に合わせて舞うので「ホウホウヒ」とか「リウヒ」というように笛の音を歌のように覚えたり…。頭の中には「ホウホウヒ」達がグルグル回っています。私が能楽部に入って初めて舞った仕舞が「玄象」だったので、「玄象」は特に愛着があります。うれしいです。「獅子には文殊や~」から始まる短い仕舞から始めて、ついに舞囃子をやるところまできたんだなあ(仕舞もまだまだ未熟だが)。まあ、どのくらい進歩しているかはわかりませんが、とにかく頑張ってやろうと思います。
|
|
舞囃子・吉野天人
|
|
舞囃子・羽衣 うららかな春の朝。漁師の白龍が仲間たちと三保の浜に釣に出ます。そこで白龍は、よい香りのただようのに気付きます。見回すと松の木の枝に、見たこともない美しい衣が掛かっているではありませんか。 羽衣を手に取って家宝にしようと考える白龍。と、女が現れて、それは自分の物だから返してほしい頼むのでした。話を聞きますと、女は天人、衣は羽衣。これではなおさら返す気になれない白龍です。天人は、羽衣がなくては天に帰れぬと嘆き、天上世界を偲んで悲しむのでした。 その様子を見て白龍の心は動きます。で、天人の舞を見せてくれるなら返そうと申し出る白龍。天人は喜び、承知します。けれども白龍は、羽衣を返せばそのまま逃げてしまうに違いない、と疑います。「いや疑いは人間にあり、天に偽りなきものを」と答える天人。白龍は恥ずかしく思い、羽衣を天人に返すのでした。天人は羽衣をまとい、月の世界の舞を舞います。地上に七宝充満の宝を降らせ、舞昇っていきます。天高く富士の高嶺を越え、春霞に紛れてはるか天空へと消えてゆくのでした。 三保の松原の白砂と海の青さと、富士の高嶺を背景に、ひと誰しもが抱く空への憧れを描き、白衣黒衣三十人の天女が奉仕する月宮殿の有様を物語る美しい舞…。いやあ、実に優美です。特に、天女さんが地上のけがれにまみれることなく天へ還っていくという設定がなんだか目出たくて良いですね。 さて、あらすじを一通り終えたところで全く関係ない話をします。摺り足の話です。能では、どんなに早く動きまわる場合でも、摺り足で運歩します。ものすごく基本的なことなのですが、実は私は出来ていないのです。身体全体を腰でまとめ、滑らかかつ重厚に運ぶ。その運びの歩幅・早さ・加速度・強弱などによって舞のリズムが生まれ、役の性格、感情などが表現されます。私の勝手な思い込みかもしれませんが。舞囃子を習い始めてから摺り足について考えるようになりました。何せ天人なもので動きがすご~くゆっくりです。ゆっくり動くというのは、身体が安定していないとなかなか難しいのです。摺り足がしっかりとできていないとフラつきます。う~む、天人三回目にしてようやく気づくなんて…。とにもかくにも羽衣総仕上げ、丹田に力を集中させて一気に放出します(?)。
|
|
素謡・大仏供養 平家一門が壇ノ浦の戦いを最後に西海の藻屑と成り果てた、これはその後のお話。 平家が滅んだとは申しましても、何も平家方のサムライが根絶やしになったわけではございませぬ。 そう。ここに恐るべき男が残っておりました。その名も悪七兵衛景清。 当時、「悪」という文字は、今の世に想起されるようないわゆる「わるい」という意味合いよりは、「並外れて強い」といったような意味合いの方が強うございました。 その悪七兵衛景清。兜の錏(しころ。首のまわりにあるびらびらした部分)をつかんでひきちぎったという逸話が残っているほどの猛き武者にございます。 その景清の話。彼は京の清水寺へ参拝した後、奈良に住んでいる母のもとを訪ねました。母はさすがに鋭い。「あなた、東大寺にくる頼朝さんを殺そうと思っているのではなくて?」 ――勿論。頼朝を殺せば西海に沈み行った仲間たちへの弔いになる。 景清は年老いて気弱になった母に別れを告げ、東大寺へ大仏供養の人込みに紛れて侵入しました。 しかし、天下を取ったほどの男、頼朝にそうそう油断のあるはずもありません。景清の、歴戦の勇士といった風貌はいやでも目に付いたと思われます。程なく頼朝の警護の武士に気付かれました。 景清は機が悪いと見るや、「悪七兵衛景清である」と名乗りをあげ、近くに来た一人を斬り殺して何処かへと消えました。 「今日はこのくらいにしといてやらぁ」 「覚えてろ」 と、捨てゼリフを残して。 ――と、これがこの謡曲の話。なんだかすっきりしない終わり方です。頼朝を殺せてたらねー、景清もかっこいいのですが「覚えてやがれ」ではね……しかし頼朝はあまりにも有名すぎますから、史実をうんと離れるわけにはいかないのでしょうよ。 史実を離れるといえば。どうもこの景清の東大寺乱入事件そのものがちと本当のことと違ってるようです。景清は、この東大寺に来た際、行って名乗りをあげることはあげましたが、頼朝に降ったらしいのです。うーん。ま、いろいろと伝説が多くて何がほんとかはっきりしないといえばしないのですけど。 しかし、強かった、という伝説はかなりあったようで、それで、このようなお話を作ってもらえたりしたのでしょう。お話なのですから、事実と違ってもいいのです。そう、虚構の世界です。うむ、謎が多いというのもよいものですな。
|
|
舞囃子・敦盛 僕はね、本当はあんな時代になんかに生まれてきたくなかった。だって、僕、戦はちっとも得意じゃないんだもの。なのに、戦わなくちゃいけなかったんだ。平家の子だからね。 僕が得意なのはね、笛。自慢みたいだろうけど本当だよ。僕、謙遜は嫌いなんだ。上皇だってね、僕の腕前を認めて小枝を下さったんだもの。この、笛がうまいっていうのは血筋かな。お兄ちゃんもね、琵琶が上手なんだよ。そら、君も聞いたことがあるだろう? 青山の話。あれを賜ったのが僕の自慢の兄、平経正さ。もちろん、お兄ちゃんにとったら僕が自慢の弟なわけだけど。 なに? 一の谷のこと? うーん、あれはね、僕、船に乗り遅れちゃってさ。そう、安徳天皇の乗ってらした船とか。源氏がもう迫ってたからね…。それで、船の行っちゃった方を見てたら後ろからひずめの音がして。そう。それが熊谷直実だったってわけ。僕、平家の御曹司だからいい鎧付けていい馬に乗ってるだろ? もう、これじゃ逃げも隠れもできないよね。化粧もしてるし。だから、うん。 そうなんだ。熊谷さんね、いい人なんだよ。後世に僕のことがいろいろ物語になってるんだってね。あ、今僕に聞いてるのもそれのことで? ふーん。うん、熊谷さんさ、僕と同じ年頃の息子さんがいてね、小次郎くんっていうんだけど。だから、よけいにね。 ううん、恨んでなんかない。だって、熊谷さんは僕のために出家までしてくれたんだもの。そう、蓮生法師って。でね、会いに行ったこと一度あるよ。ああ、その時のことがお話になってるんだ? 熊谷さん、出家した後一の谷に来てくれてね。いきなり出て愕かしちゃ悪いから最初は草刈り少年のかっこして、笛吹いて。熊谷さん、笛ほめてくれてさ。初めは黙ってるつもりだったんだけど。ついね、うれしくてさ。僕だ、って言っちゃって。 で、夜にちゃんとほんとのかっこしてまた訪ねて、あの頃の思い出とか聞いてもらったの。へぇ、そこを舞で表現するお話なの? 面白そうだね。僕は舞もうまいんだよ。歌舞音曲の才があるからね。ちゃんと舞ってくれるのかな。こっそり見に行こっと。 うーん、そうだね。全く恨んでなかったかっていったらそれは嘘だね。これでも武士だし。やられたときは悔しかったよ、そりゃあ。もっと笛うまくなりたかったもの。まだ十六才だったからね。でも、修羅道に行かなくてすんだのは熊谷さんのおかげだもん。それに、笛は今も続けてるし。そう、今は仲良しなんだ。
|
|
舞囃子・胡蝶 旅中の僧は古都を訪ねました。今を盛りの梅の花が僧を出迎えますと一人の女性が現れます。「実は私は胡蝶の精です。四季に咲く花々と戯れることができます。けれども残念なことに早春に咲く梅の花とは縁がありません。どうか読経によって私を成仏させてください。」そう言い残して消え去るのでした。 その夜のこと、僧が彼女のために回向しますと夢の中に胡蝶の精が現れ、御仏の力によって梅の花とも遊ぶことができるようになったと喜び、胡蝶の舞を舞うのです。 ――四季折々の花々に飛び交う華やかな蝶の精はやがて、菩薩の姿で、早春の梅花に戯れることができたのでした。軽やかな中に命短い胡蝶のはかなさを描いた作品です。 火の光に照らされた胡蝶の羽の素敵なこと。京都平安神宮でお目に掛かった胡蝶さん。驚きましたわ。(六月一日薪能 於・平安神宮)カラフルな卵模様のその立派な羽がうらやましかった。去年の淡海能冊子の私ときたら…。お恥ずかしいです。あなたのような素敵な羽を持って多くの花を虜にさせる蝶の精になれるよう見守っていらしてね。 ただ今お囃子のお稽古に励んでいるのですが私は本当に覚えが悪く深野先生に多大な迷惑をおかけしております。こんなにも親切丁寧な御指導にもかかわらず「ササッ。」と舞えない自分がとても情けなくて。けれどもこの情けない姿も今だからまだ自分の中で許せる所もあるのです。右も左も分からなくて困った顔でたたずんでいる私よりもずっと情けなくはない姿なんですもの。 ――ケセラ・セラもいいけれど。 最後に広告掲載に御協力頂いた皆様方に心を込めて「ありがとうございました」を言いたいです。ほんとなら私達は舞台の中で「ありがとう」を伝えなきゃね。
|
|
舞囃子・猩々 秋です。猩々の季節です。お酒、飲んでますか? 猩々は妖精です。お酒がとても好きで、海中に住んでいます。いくら飲んでも顔色が変わりません。姿は少年のようです。 このお話の舞台は中国です。金山の麓、揚子江のほとりに高風という名の親孝行者がおりました。彼はある日、不思議な夢を見ました。市に出て酒を売れば、お金持ちになって地位も得るという夢です。教えの通りにしてみると、次第にその通りになっていきました。もう一つ不思議なことは、市ごとに来て酒を飲む者がいました。しかしいくら杯を重ねても顔色が変わりません。不審に思い名を尋ねると、猩々だと答えました。 高風は、月の美しい夜に潯陽の江に行き、菊花の酒を壷の中にたたえて猩々を待ちます。(猩々菊というお酒ありますよね。)やがて海中から猩々が浮かび出て酒を汲みかわします。猩々は舞を舞い、いくら汲んでも尽きるコトのない酒壷を与えて消えるのです。 月のきれいな秋の夜。お酒を飲んで気持ちよくなってしまうという、なんともイイ感じな演目ですね。 ところで、猩々物として他に大瓶猩々というのがあります。こちらのほうは猩々がたくさん、わらわらと登場します。一畳台に大壷をしつらえ、壷の酒を汲みほし、相舞となります。お酒を囲んで複数の猩々が酔いしれ、舞うのです。酔っぱらいがいっぱい。聞くだけではたちが悪そうですが、めでたい演目なのです。 能楽部というのは、お稽古事のようなものなのですから、続けていると御多分に漏れず、難しく(より高度に)なっていきます。去年の淡海能ではお仕舞で舞わせていただいた猩々。今年は舞囃子でお届けします。難しいっス。がんばるでぃ。
|
|
連吟・竹生島 ご存知ですか? あの琵琶湖にぽっかり浮かぶひょっこりひょうたん島、竹生島を。そう、このお話はここ、近江の竹生島が舞台なのですね。なんだかうれしゅうございますね。 あの島は浅井姫命の切られた首で出来ているだけありまして、女の神様がおられるのですよ。その名は弁才天。七福神の紅一点でもある人気者です。 ――京からお参りに来た人をお船に乗せて連れていってくれた漁師のおじいちゃんと海女のお姉ちゃんは実は龍神さんと弁才天さんだったのでした――と言うお話なんですけれどもね、これは。 京の人が知ったかぶりして言ったんですね、島に着いたらお姉ちゃんも上陸しようとしたのを見て。 「女人禁制とちゃうんけー」 これだから困ります。おじいちゃんは島の由来をくどくど述べて説明しますが、まどろっこしい。お姉ちゃんは見かねて言います。 「この島にいるのはね、弁才天さんなの。神様からして女の子なのに、なんで女の子が島に入っちゃいけないのよ?」 いや、恥ずかしい。知ったかぶりはやめましょう。他山の石。 しかし、それでちょっと頭に来た(かもしれない)二人は正体を明かしたのですから、得をしたのでしょうかね。世の中理不尽なことも多いですな。 でもね、よその女の神様には、やきもちやいて女の人がくるのを嫌がる方もおられるんですよ。ま、そりゃかっこいい男の人がくるならいいけど○○○○な男の人よりは美人のほうがあたしはずっといいけどなぁ‥‥‥きっとそういう神様は美醜での差別はなさらないのですね。そういうところは私なぞにしたらものすごく素敵でいいお心だと思うけど、やはり‥‥‥。心が広いのか狭いのか。わかりませんな、神様ってお方は。
|
|
番外仕舞・菊慈童 舞台は中国であります。魏の文帝の家臣が、とあるお山の麓にきました。帝に「噂の薬水を調べてこい」と言われたからです。 かなり人里離れたところであります。だのに。少年が現れて家臣はびっくり。「どうしてこんなところに人間がいるのだっ! 貴様、さては化け物だな」少年は答えます。「ちがうよ。僕は周の穆王に仕えていた者だよ」ふーん、ああ、そうですか。しかし。皆の衆、だまされてはなりませんぞ。こんなのちっとも言い訳にならないのであります。何故か、とお聞きになる? それは、周の穆王さんは魏の文帝さんより七百年も昔の人なのですぜ。(お能の本では七百年前、ということになってますが、史実では千二百年前です。うわぁ。) でも、少年の言うことは本当なのでした。家臣はそりゃびっくりしましたが、慈童も驚いた様子。そんなに年月がたっていたなんて知らなかったのでしょうね。で。なぜ少年が七百年も若さを保ち生き長らえていたかというと。このお山にやられるとき、帝が枕にありがたい文句を書いてくれてたんですね。で、その文句を菊の葉に書いたらその葉に降りた露が不老不死の妙薬になったらしいのです。 そうと分かった少年は大喜び。薬水を飲んでうかれて(この薬水、お酒みたいです)家臣にもすすめ、七百年もの寿命を帝に奉げると菊をかき分けてお家に帰っていきましたとさ。 なぜこの少年はお山に追いやられたのかというと、どうも帝の枕をまたいだ罰らしいです。でも、帝はわざとしたんじゃないことを分かっていたから、かわいそうに思ってありがたい文句を書いた枕をくれたのでしょう。立場ってもんがありますからねぇ。偉い人もつらいのです。
|
|
番外仕舞・鞍馬天狗 春、花の盛り。京の北にある鞍馬寺の御一行が花見に出かけます。すると、そこでは一人の山伏が休んでおりました。 鞍馬寺の人々は、よそもんを煙たがって山伏を邪魔者扱い。どこかへ行け、と追い払いまでします。んまぁ! 桜は鞍馬寺の所有物なんかい! 桜はだれのものでもないのにね。仏に仕える身とは思えぬ所業ですな。まったくもって不届千万。仏教徒の風上にもおけやしない。 山伏さんもそう思ったんでそう言います。感じ悪いよ、って。すると、その意に賛成してくれた一人のお稚児さんをのぞいてみんな帰ってしまいます。痛いとこをつかれたんでしょうな。図星を指されると人は誰しもうろたえるのです。 山伏はその一人残ったお稚児さんに関心を持ちます。「みんな帰ったよ。君は?」そのお稚児さんこそ誰あろう、沙那王、後の義経くんなのですな。 今の世は平家全盛期。寺の稚児仲間のうちでも平家の御曹司が幅を利かせていて沙那王くんは日々肩身の狭い思いをしているのです。 山伏はそんな沙那王くんの境遇を察します。そして実は自分は天狗であることを明かし、沙那王くんに兵法の極意を教えて、後に平家を滅ぼす天才軍師・源九郎義経への第一歩を踏み出させるってわけですね。そして、平家との戦いの際には力添えすることを約束し、すがる沙那王くんを振りきって何処へかと消えて行くのでした。 しかし。この天狗さん、義経くんの生涯にわたっては力添えしてくれなかったんですね。だって……源氏さえ復興すればよかったのかしら。いやいや、諸行無常ですか。
|
|
附祝言・高砂 ♪ 高砂や この浦風に帆をあげて…… 高砂は、結婚式などで謡われるおめでたい歌だということは、皆さんご存知かと思います。 なぜおめでたいかというと、これは仲良しの老夫婦のお話だからです。「共に白髪の生えるまで」ずっと一緒に歳を重ねていった理想の夫婦像なわけです。 このおじいちゃんとおばあちゃん、実は松の木の精なのです。おじいちゃんは兵庫県高砂市あたりの松の木。おばあちゃんは大阪市住吉区あたりの松の木。場所は離れてますが、距離に引き離されるような愛ではないのだそうです。のろけられちゃいましたね。 なぜこの二ヶ所の松の木は相生の松、夫婦とされるようになったのでしょうねぇ。と、思いましたのでちょっと調べましたが、ほんとにちょっとしか調べてないのでわかりません。 ですが「古今和歌集」に、それぞれの松を詠い込んだ歌がいくつか載っていまして。 かくしつゝ世をや尽くさん 高砂の尾上に立てる松ならなくに たれをかも知る人にせん 高砂の松も昔のともならなくに 住江のまつほど久になりぬれば あしたづのねになかぬ日はなし 住吉の岸の姫松 人ならば いく世か経しと問はましものを どちらも、とても古いもの、という認識があったらしいですね。と、そういうことは読み取れましたが。 さて、相生・相老いの老夫婦は今も生きておられるのでしょうか。もう、昔の面影もないほど景色が変わっちゃったかな……
|
|
お能でウフフ 祝! やったね 第二回 淡海能! やほ。毎度毎度、「お能でウフフ」などと銘打ちながらお能とかけ離れたことばかり話しておる私ですが、それでもいいじゃないすか。お能という一つの分野から、知的好奇心は各方面へと。これぞ学問だね。ま、自分の興味ある分野とお能を無理にくっつけてるという見方もありますけど、それでもいいさね。世界は決して一面的ではありえないのだからして。してといってもシテではないのだからして。 だけどね、今回は違うよ。ほんとにお能のことについて教えてあげますぜ。よかったね。これでこの冊子を読んだ甲斐があるってぇもんだ、しみじみしじみ。 では、本題に入ろう。今日は、お話のならべ方の話。そう言われてもピーンとこない人は黙って指くわえて読んできなさい。後で分かるから。さぁ、ついておいで! お能にはいろいろなお話がありますな。その数何と二百以上! そんだけたくさんあると、何らかの方法で分類しなきゃやってらんない。分類の仕方は数通りあるようだけど、その中でも一番有名なのが、番組構成上からの分類だ。いわゆる能組五番立、という曲種で分けたやつだね。 この番組は、江戸時代にできたんだ。あのころはみんな暇だったから(というと怒られるかな)、それは、能を七番と狂言を四番演ずる実に大きなものだったのだね。きっと一日掛かりだよ。その順番は、こう。 ① 翁 ② 脇能 ③ 脇狂言 ④ 二番目修羅能 ⑤ 二番目狂言 ⑥ 三番目鬘能 ⑦ 三番目狂言 ⑧ 四番目雑能 ⑨四番目狂言 ⑩ 五番目切能 ⑪ 祝言能 なんてゴージャス! こうして正式にされることは、今の忙しい世の中ではほとんどないね。だがしかし。この曲種による順番というのは、守られてますのさ。狂言をぬいてお能だけで考えると、翁・脇能・修羅能・鬘能・雑能・切能・祝言能という並びになるね。そして、その中の最初と最後を除いた五番、これが五番立になるわけだ。簡単に「神・男・女・狂・鬼」といわれてる。じゃ、それぞれの内容を説明しておきますか。
ほら。大体五番立の順番にそってますね? なに、玄象は切能なのに一番目じゃないか、ですとな? それは良いところに気づきなすった。確かに本籍は切能。だけど、略式に、脇能として扱うことも可能なんだね。こういう曲を「略式脇能物」といいますのさ。ちなみに、小袖曽我は略式二番目物、羽衣は略式五番目物。そうすると、 ほらほら。並び方にはちゃんと意味があるんでさぁ。そして。やっぱり始まりは翁・神能のようにおめでたくいきたいから鶴亀ではじめてるってぇわけ。さぁて。ここまで来ると、附祝言もどういうものか分かってくれましたね? そう! 略式化された祝言能なのですな。ウフフ。
|
|
いかごはん梅子がおくる 仏でオホホ 第二回淡海能を祝して 皆様、ご機嫌いかが? 無事、第二回淡海能開催の運びとなりまして、実にようございましたわね。お祝い申し上げます。 挨拶はそのくらいにいたしまして。さて、祐筆Rさんがまたまた助け船を出して欲しがっていらっしゃいましたので及ばずながら再びお力になりたいと思っておりますの。Rさんよりはいくらかは詳しいですからね、仏教に関してのことなら。オホホ。 今回のお話は、『菊慈童』に関してのことですの。きちんとここまでこの冊子をお読みになった方なら、どなたもお気になさっておられるかと思いますのね、私。 「ありがたい文句って何なの、どんな文句なのよ?」 ね? その文句を記した菊の葉に降りた露が、不老不死の妙薬になったというのですから。もちろん、この謡曲では「菊はいいよ」ということのほうが曲の主題なのでしょうけれど。と、私は思うのですけどね。 こほん。では、お教えしましょうね。 出典は『妙法蓮華経 観世音菩薩普門品第二十五』。いわゆる法華経の中の、観音経ですね。読み下すと、こうなります。 一切の功徳を具して 慈眼をもって衆生を 福の これは観音さまのことをおっしゃっておられるわけです。観音経は、その名のとおり観音さまのことをお記しになった本でして、観音さまを信じたらこんなにいいこと、素敵なことがありますよ、と実例を示して教えて下さっているのです。そういう本(お経)の中の一節なのですね。 観音さまは、あらゆる所へお心を配っておいでなのです。ほんとに、それは徹底しておやりになっておられて、様々に姿形を変えていたるところに現れて下さいます。私共人間の姿をとってくださる場合もございますし、人々の様々な願いをよりよく聞き届けるに適したお姿になって下さることもございます。 「徳を備えていらして、優しくみんなを見守ってくれる。海のように限りなく大きな愛。だから、そんな素敵な観世音菩薩さまを信じなさい」と、そういうことでしょうかしら。とってもありがたいじゃあございませんこと? 皆様も、今夜さっそく菊の葉にお書きになってみてはいかがかしら。では、これで失礼致しますわ、オホホ。
|