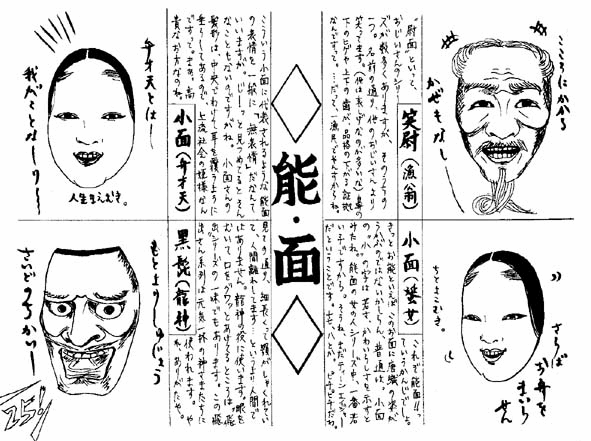
能楽「竹生島」
能面
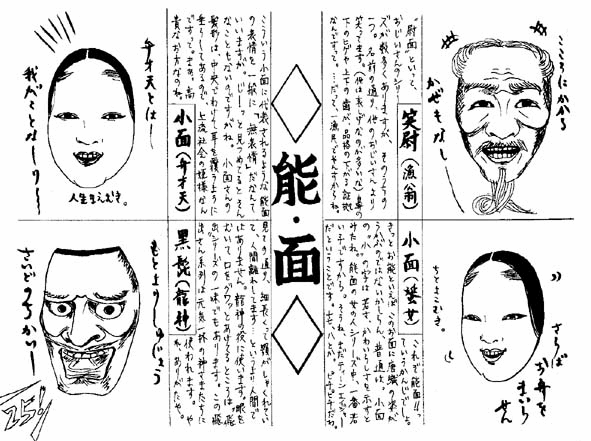
作り物
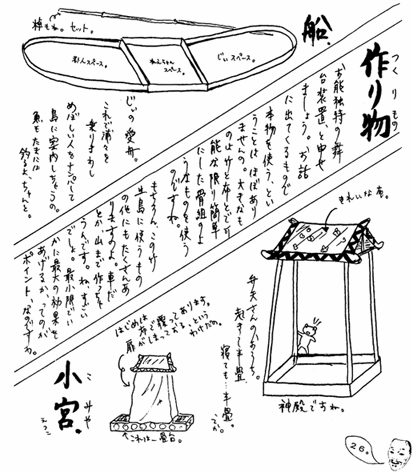
装束
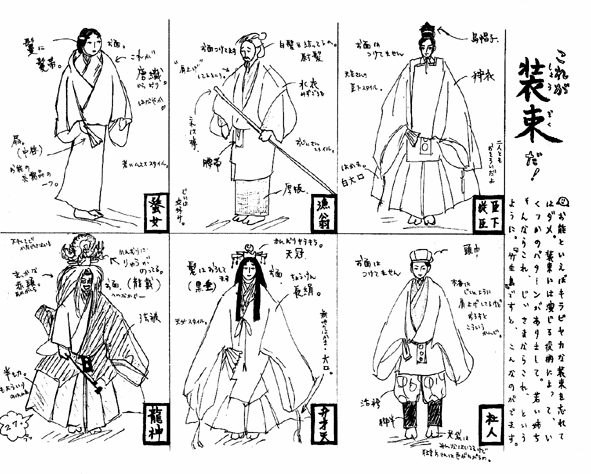
場面一・都人、竹生島詣に出かける
*1 西暦にすると九〇一〜九二三年の間になりますね、醍醐さんの治世は。醍醐さんのお墓は京都市伏見区醍醐にあります。肝試しでよくお世話になりました。 *2 弁才天さんは仏教・神道で分けると仏教側のお方なんですけど、ご存知の通り、ほら、日本は神仏混淆と申しましょうか、ありがたいのならみんな好き、という感じで長らく生きてきましたので、表現がごちゃごちゃなのですな。でも、それでいいのだ。今のように分けたがる風潮になってからの方が歴史は浅いのだ。 *3 走井餅、食べてますか。 *4 醍醐さんの四男との噂のある蝉丸さんがいて、琵琶を弾いておったかもしれませんね。琵琶は弁天さんも得意ですしね。 *5 実際たったの一、二分。能は時空にとらわれないのですじゃ。ふはは。おそれいったか。 |
場面二・漁師の老人と海女の娘、登場
*1 旧暦ですので、今の暦でいうと四月半ばくらいかしら。 *2 天智さんは西暦六六二〜六七一の間、天皇さんをしてました。大津は六六七〜六七二の間、都でした。期間は短くとも、都は都。五年でも、十年でも。 |
場面三・老人と娘、都人と出会う
*1 いわゆるあの世です。この世は *2 「乗る(乗り)」と「 |
場面四・湖上の旅
*1 こうしてジィはみごとナンパに成功してまんまと舟にお客を乗せたのでありました。しめしめ……って感じにも思えませんですかね、ここのところだけ読んでたら。 *2 言ったのは在原業平さんです。「時知らぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ」 *3 この詞章が、前場のヤマともいうべきところなのですが、このお魚とウサギの竹生島は、昔から皆のお気に入りだったみたいですよ。 「緑樹影沈魚上木/清波月落兎奔波/霊灯霊地無今古/不断神風済度舟」建長寺の自休蔵主さん。 「緑樹影沈魚上木/月浮海上兎奔波」弘法大師さん。 「緑樹影沈んでは金鱗枝頭に上り、桂輪浪に落ちて玉兎湖上に走る」三国伝説より。 「緑樹影沈んでは、魚も梢にのぼり、月海上に浮かんでは、兎も浪を走れり」乱曲島廻より。 誰が一番最初に考えたんだろう。すてきな表現ですよね、うぉー。 |
場面五・竹生島到着
*1 九生如来さんとは、阿弥陀さんのこと。阿弥陀さんは皆の衆に大人気を博しておる「ホテル・弥陀浄土」のオーナーとして有名ですね。その死んだ者のみ入室を許されたホテルには九段階のランクがありましてね。上品・中品・下品の大まかなランクがまたそれぞれ上生・中生・下生に分かれているのです。つまり、上品上生から下品下生までの九段階ね。で、これは生前の行いに応じてどのお部屋に入れてもらえるかが決まっちゃうのだ。お迎えに来てくれるときに、サインでそれを示しながら来てくれるんだけどね。こういうシステムのことを「九品浄土」っていいます。で、それを九生とも言ってたかもしれないなー、ってのが九生如来のさんを阿弥陀さんだとする際の説の一つ。実は、この九生如来さんという名前は仏関係の資料には一切載ってないのであります。この謡曲『竹生島』だけにしか見られない名前でして。それに、昔はこの歌詞は漢字だったのが読み(カタカナ)に書き換えられて伝えられて、そのカタカナに「九生」と漢字を当てたのは後世の人の考えなのね。他の流派(私達が教わっているのは観世流です。その他、四つの流派があります。)には違う読みで伝わってたりもするし。だから漢字も違うんだけど。他に大日如来さんだとする説もあるのね。でもあたしは阿弥陀さんだと思うんだけどさ。というわけで、分からないっちゃあ分からないんだけども、阿弥陀さんとすると後の話の展開に無理がないからそこからこじつけて……って考えてると、それこそ海女のおねえちゃんに「そんなややこしいこと、言わんでよろし!」って叱られそうだな。……って、私のいわんとすること、わかります? |
場面六・正体をほのめかして消える二人
*1 阿弥陀如来さんは、四十八の誓いをたてました。その三十五番目に、それまでは不浄ゆえ成仏できないとされていた女性をも、必ず成仏させるぞ、というものがあるのです。いやぁ、いい人だ。 |
場面七・お宝、そして神秘の業
*1 景行さんは日本武尊のお父さんです。 *2 仏教界では、世界は水に浮いてることになってるんですが、この竹生島だけは、ふかーいふかーいところから生えてるって事です。 *3 このお宝たち、ほんとに竹生島にあるんですよ。そのほか、経正くん使用の琵琶の撥もあります。ファン垂涎の品ですな。 |
場面八・弁才天、登場
*1 音楽が鳴り響き、花びらが降ってくるっていうのは、まぁ、神さまや天女さんが現れるときの決まりのようなものですな。なんか、かっこいいでしょ。あとね、いい匂いもしてたと思うよ。 |
場面九・龍神登場
*1 弁天さんが持っている宝物の一つです。何でも欲しいものが出せるって噂です。いいな。 |