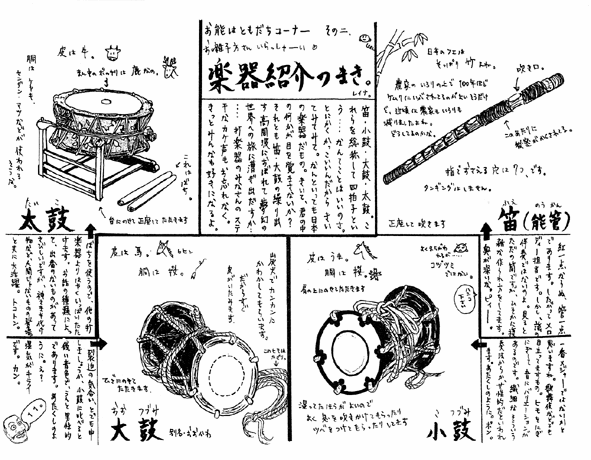
��������@R.M��
����O��@�W�C�\��
|
�����\�N�\���\�l���i���j���ߎn�@
�@�f�w�@���ٌc �@�����q�@���� �@�@�@�@�@�����]�� �@�d���@�Ӓ� �@�@�@�@�́X �@�����q�@�Z �@�@�@�@�@�Ɣn�V�� �@ �@���ҍZ�o���@�ŋ���w�\�y�� �@�ږ�o�������q�@�O�������_�_�y �@���ҍZ�o���@���s�k���q��w�\�y�� �@�ԊO�d���@�O�䎛 �@�@�@�@�@�@�V�� �@�\�y�@�|���� �@���j�� �@�I���\��@�\�Z���\�ܕ���
|
|
�@�w�����A �@ ���ꌧ����w�w���@�����q�� �@ �\�Ƃ����̂͂����������̂��A���̔\�̂悳�A���������킩��Ȃ��Ă͂��߂��A�Ƃ����̂��\�������蕑�����肷��Ƃ��̐S���ł��낤�B �@ ����͂������悭�킩��̂����A�ǂ������Ȃ��ɂ��Ă����Ȃ��̂��\�̃e���|�ł���B���̂�����肵�������́A���Ȃ��Ƃ������̌���̃e���|�Ƃ͂�������Ă���B�\�����܂ꂽ����̐l�X�́A���������e���|���ǂ������A�ǂ��Ƃ߂Ă����̂��낤���H�@�ڂ��͐̂��炻�ꂪ�C�ɂȂ��Ă��������Ȃ������B �@ �\�̊W�҂ɂ��̋^���b���Ă݂�ƁA���낢��ȓ������������Ă���B �@ ���Ƃ��A�u�̂̐����̃e���|��������肾��������A����ł�����ł��v�ƁB �@ �������ɂ�����������Ȃ��B���͂��ׂĂɂ����ăe���|����������B���m���y�����āA�����O�܂ł͂����Ƃ�����肵�����̂������B���{�̉̂����Ă������B�ЂƐ̑O�ɗ��s�����t�H�[�N�ȂǁA�Ȃ�Ƃ������Ƃ������̂��������B�x�g�i������f���̂Ƃ��A���́u�E�B�E�V�����E�I�[�o�[�J�[���v�Ƃ����t�H�[�N�̃e���|���A�l��̕��������ƈ�v�����A���������f�������Ƃ��v���o���B �@ ����������Ȃ�A�\�ƕ���ʼn������鋶���̃e���|�͉����낤�H�����āA�\�́u�̂����v�Ƃ��̌ۂ�w�̑����e���|�͉��Ȃ̂��낤�H�@�u�̂���͂����v�Ƃ������Ƃ́A�ׂɃe���|�����������邱�Ƃł͂Ȃ��B �@ ���̈���A�����������������������Ƃ�����B�u�\�̃e���|�͂������Ă������ȂȂ��̂ł���B�ق�̂�����ƕ������M�𑆂������Ǝv���ƁA���═���̍��ɒ����ɂ��邤�A�Ɨw���������肷���ł�����B�v �@ ������������ɂ������B�w�ɏq�ׂ�ꂽ�Ƃ���A�����Ƃ����Ԃɏꏊ�͕ς��A�Ƃ��Ƀ^�C���X���b�v�������Ă���B���̖��ɕς�����A�ŐV�̉�蕑����g���Ă��������������I�y���Ƃ́A��������|�p�Ȃ̂ɁA�܂�ňႤ�̂��B �@ �������\�̂��������̕��̃e���|�ɂ͂��Ă����Ȃ��Ƃ�������B�w�̂��Ƃ��ďI�c�������Ă������ł��A��͂��ɂ������邱�Ƃ�������B��͂�ڂ����\�̊y���ݕ�������Ă��Ȃ����炾�낤���H |
|
�@�ږ����A �@ �W�C�\�ɂ悹�� �@���ꌧ����w�\�y���ږ�@�e�c ���q �@ �W�C�\�����N�ŎO��ڂ��}����B�����\�y�������������w���������A�����͂�l�ɂȂ��āA�₪�Ă͑��Ƃ��}���鎖�ɂȂ����B������L�O���āA���N�͔\�y���㉉���鎖�ɂȂ����B�܂��ɉ����Ƃ����ׂ��ł���B �@ �\�y���Ŕ\�y���㉉���邱�Ƃ��A�����Ƃ����ƕs�v�c�Ɏv���邩������Ȃ��B����܂ł̉�́A�\�y�̈ꕔ���Ƃ����ׂ��w��A���̈ꕔ�����d���A����ɚ��q���t�������q�ł������B�\�y�Ƃ����̂́A�\�ʂ𒅂��āA�d�������h�ȑ��������āA�����q�ɚ����Ă�����đS�Ȃ��̂ł���B����A���y��ŃA���A���̂��Ă����̂��A�I�y���ɒ��킷��悤�Ȃ��̂ł���B���߂łƂ��I�@�������F���Ă��܂��B �@ �Ȗڂ́A�ߍ]�̔\�y�u�|�����v�B�ߍ]�ɏZ�ސl�Ȃ���i�ɂۂ����蕂���Ԓ|������m��Ȃ��l�͂Ȃ����낤�B�������A�\�y�u�|�����v�������l��A���̂��炷����m���Ă���l�͏��Ȃ����낤�B�����͂��̃p���t�ɏ�����Ă���Ǝv������͂�����āA�ȒP�ɂ����A�|�����̗쌱���炽�������Ĕh������Ă������g�̑O�ɁA�ΐ��̗����ƒ|�����Ր_�ٍ̕��V���O��ł͉���̎p�������A���ɂ͖{���̎p�������ĕ����A�Ƃ����b�ł���B�����ʔ����Ǝv���̂́A���̏��ɉ��g�����ٍ��V���A���ɏオ���Ă����ƒ��g����߂āA���l���ł͂Ȃ��̂��Ƃ����ƁA���́u�ٍ��V�͏��̂ɂāA���̐_�������炽�Ȃ�V���ƌ������͂��܂��A���l�ƂĊu�ĂȂ��A�����m��ʐl�̌��t�Ȃ�v�Ƃ����āA�Вd�̔��������ē����Ă������A�Ƃ����Ƃ���ł���B �@ ���̋Ȃ��ł�����������́A�����ɂ�������悤�ɁA���̗͂��オ���Ă�������ł���B�����Ȃǂł��������߂������A��ɋߍ]�ł͑��������Ǝv����B���̐l�����̐M�����W���ĎQ�w�������A�������t���Ă��炨���ƁA���̐l�X�ɋ����Ăт������̂��A���̋Ȃ̗��j�I�Ȕw�i���Ǝv���̂ł���B��������Ȓ|�����̘@�؉�Ƃ����Ղ�̏����̂��̂ŁA�����ŌÂ̘@�؉�ٍ̕��V�́A���̂�����̐퍑�喼���v���i���s�̕v�̒����̕��j�̐���̉i�\��N�i��ܘZ�Z�j�̖�������B���͒j���哱�̘@�؉���A���̍��͏��̐l����ɂȂ��čՂ������s�����Ƃ��������̂ł���B �@ �\�y�u�|�����v�́A����Ȕ��i�̗��j��̌����Ă���B�W�C�\�����ɂӂ��킵���Ȗڂł���B �@ �Ȃ����̑��A�O�ȉ��̐��X�̋Ȗڂ̗͉�������B�����w���ƈꏏ�ɂȂ��āi�H�j�������ƂɂȂ��Ă���B�F����A���Ђ������茩�Ă��������B |
|
�f�w�E���ٌc �@ ���ɗL���ȕ����V�ٌc����͔�b�R�̐����̖T��ɏZ��ł��܂����B����͈ȑO����̊肢�����߂Ă̎Q�w�̍ŏI���ł��B����������͂肫���čs�����A�Ƃ���ٌc����ɂ����̕��͌����܂��B �@ �u�ߍ��A���̋��̏�ɏ\��A�O�̏��N������A���������g���A�l�ԗ��ꂵ���f�����Ől���a���Ă���̂ł��B�댯�ł��̂ŁA����͂��~�߉������B�v �@ �����ŕٌc����A����͎~�߂Ƃ������ȁ[�A�Ǝv���܂����A�����œ����Ă͒j��������B�������̏��N��߂܂��Ă�낤�A�Ǝv�������܂��B �@ ����ė��܂������̏�B�\�̏��N���Ƌ���ۂ���͐l���a��s�ׂ��ɊЂ߂�ꍡ�����œs�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B�������ĒN���ʂ�Ȃ����Ƒ҂��Ă��܂��B�ٌc����͂��V����ł��̂ŏ����Ƃ͊ւ��Ȃ��悤�ɒʂ�߂��悤�Ƃ����Ƃ���A�ˑR�����̕����R��グ���܂��B �@�u��������I�@�n���҂߂��A�ڂɂ��̌����Ă�����I�v �`�����`�����o���o���`�����o���o���B��l�̐킢���n�܂�܂��B����������ۂ���̐g�y���A�f�����ɕٌc����͋�킵�܂��B�����Đ��̂����ɂ͂���Ȃ��Ȃ�A���N�������̌��̎҂ƒm��̂ł��B�~�Q�����ٌc����́A����ۂ���̈ʂ��������C������������C�ɓ���Ɛb�ɂ��Ă��炢�܂����Ƃ��B �@ ���`�o�ƕ����V�ٌc�̌������ꂽ��]�W�͗L���ł��ˁB�����ɒǂ���`�o��s���֏���ʂ�Ƃ��A���̂��ꂻ���ɂȂ����̂� �@�u���܂������`�o�Ɏ��Ă��邩��^��ꂽ�ł͂Ȃ����I�v �ƁA�ٌc���S�ŋ��������`�o��ɂ߂���b�Ƃ��B�`�o����邽�ߕٌc�͌\��{�̖���ė����Ȃ���▽�����b�Ƃ��B��������]���ł��˂��B��]�̉��͎O���̋@���Ƃ������āA�O���E�����E������ʂ��ĂȂ����Ă��邻���ł��B���Ȃ݂ɐe�q�͈ꐢ�A�v�w�͓̉��ł��̂Ŏ�]�W�������ɐ[���ł����̂�������܂��ˁB���l�͐��ɘA��Ă������Ƃ͂ł��Ȃ�����ljƐb�͂����ꏏ�A���ʂƂ����ꏏ�ɂȂ����肵�܂��B�M���������ĂȂ��Ǝ�]�W�͐��藧���܂���B�`�o�ƕٌc�͂����Ǝ�]�W�����ׂĂ悩�����ł��ˁB�Ȃɂ�������ꂽ��`�o�͓s������A�ٌc�͎Q�w���I����Ă����̂ł�����B�^���̓�l�ł��ˁB
|
|
�����q�E���� �@ �G�߂͏t�A��㍑���h�̐_��F�����s�ɏ��r���A�d�����̍����̉Y�ɗ�����菼�߂Ă��܂����B�����֔����̘V�l�v�w�����āA���̖؉A��|�����߂܂��B�F���͂��̘V�v�w�ɍ����̏��Ƃ����̂͂ǂꂩ�Ɛq�ˁA�܂������̏��ƏZ�g�̏��Ƃ͍����u�ĂĂ���̂ɂȂ������̏��ƌĂ��̂��A���̗��R��q�˂܂��B �@ �u�R���ݗ����u��ǂ� �@�@�@�@�@�@ �݂��ɒʂ��S�����̖��w�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͉����炸�v �@ �V�l�͕v�w�̈��������A����ɗl�X�Ȍ̎��Ȃǂ������č����̏��̂߂ł��������������܂��B�₪�Ď������������̑����̏��̐��ł��邱�Ƃ𖾂����āA�Z�g�ɂĂ��҂����܂��Ƃ����A�M�ɏ���ĉ��̕��֏����Ă䂫�܂��B �@�����ŗF�����M�ɏ��A�Z�g�ւƋ}���܂��B�Z�g�ɒ����ƁA��قǂ̘V�l���Z�g���_�Ƃ��Ė{�̂������A����ݍA���y�������j���A�D�u�Ƃ߂ł��������܂��B �@ ���͎��ۂɁq�����̕v�w���r�����Ă݂����Ȃ�A���Ɍ������s�ւƍs���ĎQ��܂����BJR�P�H�w����R�z�d�S�ɏ�芷���A�����w�ō~��܂��B��������������Ə\�ܕ��B�����̌Â������݂��A�������撅���������_�ЁB�C���킵���s�X�n����O�ꂽ�C�݊��ɁA�Ђ�����Ƃ��̐_�Ђ͂���܂����B �@ �Â����牏���т̏ے��Ƃ��Ēm��ꂽ�����̏��͊��x���͂�āA���ܑ͌�ڂ��`�𐮂��n�߂Ă��܂��B�\�y�w�����x�ł��������̏��́q�����̏��r�Ɓq�Z�g�̏��r�̓�{�̏��̂��ƂȂ̂ł����A�����Ō������̓N���}�c�ƃA�J�}�c�����������o�����ł����B�����Ƃ������̒ʂ�A���Y���A������Đ������Ă������Ȃ̂ł��ˁB���ł����̒��ǂ����̑O�Ō��������������邻���ł��B�����Ƃ��̐ȏ�ł͕v�w���ƒ����̗��z������킵���߂ł����ȁA�w�����x�̈�߂��N�X�Ɨw���Ă���̂ł��傤�B �@ ����ɂ��Ă��c�O�Ȃ��ƂɁA�C�݈�̂ɂ͍H�ꂪ�������сA�F�������߂��������̔����������̕l�����邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�u�N�������m��l�ɂ����̏����̗̂F�Ȃ�Ȃ��Ɂv�̂̐l�͂ǂ̂悤�Ȍi�F�����āA�̂��r��ł����̂ł��傤���B
|
|
�����q�E�����]�� �@ �����ŕ����q���ł���������ɂ͂��Ⴂ�ł������B�B���̑�ς��ɋC�Â����ƂȂ��u���܂��I�v�Ɛ������킹�Ă��������c�c�B�Ƃɂ�����l�ň�B��l���Ȃ��Ǝn�܂�Ȃ��B�v���̂܂܁A�Ƃ͌��ꓹ�f�B�����ɍ��킹��ׂ����B�|�Z��A���ǂ����͔����������ȁi�H�j�B �Z�E�]��\�Y �@ ���̒�E�ܘY�̊����������ꂽ�B����ɂ��Ă������Ɏ��铹�̂�̒����������ƂƂ�������Ȃ��B���B�\��̌Z�킪����̋w�����ߕ�ɕʂ�������悤�ƁA�������ĖK�˂͂������̂́A���̐����ɂ���قǂ̎����o�Ƃ��Ƃ́B �@ �\�\�m���ɕ��͌ܘY���o�Ƃ��������ł������B������������Ƃ����ČܘY�������Ȃ���Ƃ́B���ɂ͂ǂ����ĉ���ʂ̂��B���B�Z��͂ǂ����Ă�����̋w�������̂��B���̓x�s����x�m�ł̎��ɎQ�����āA���̕���̋w�E�H���S�o�Ƃ��ƌ��߂��̂��B���̂��߂ɌܘY�͌��������B������l�̌��ӂ͌����ĕς��Ȃ��B �@ ���̂��܂�̂������ɁA���⎄�B�Z��̐S���悤�₭��ɂ��ʂ��āA�����������ꂽ�ܘY�Ǝ��͂��̊������ɗ܂𗬂����B�����Ď���ւ̖�o���j�������Â����ƁA���Ɗ�т̎����ނ��킵�A�Z��ő������Ď��B�͂�������ւƕ����̂ł������B �@ ��E�ܘY�ɂ͖{���ɖ��f�������܂����B���߂�ˁA�E�b�`�[�B����Ȏ����܂��������킹�Ă��炦�āA���������Z���Ȃ�ĂˁB �@ �������̊Ԃɂ��l�B�[��搶�ɐS���犴�ӂ����߂Ă�����ł���悤�A���܂ň�Ԕ[���̂������̂ł����Ăق����i�B �@ �݂�Ȃ��肪�Ƃ��B�����Ă��ꂩ�����낵���ˁB
��E�]��ܘY �@ ��E�ܘY���v�킹�Ă��������܂��B�ł���������ł��B��͂͂́B �@ �w�����]��x�̂��b�ɂ��Ă͌Z�E�\�Y�S���iM.K�j���������Ă��܂��̂ŁA���́w�����]��x�Ƃ͂��܂�W�̂Ȃ��b���B �@ ���̌Z��̋w�����ɂ́A�P���ȕ��Q�ł͂Ȃ��̂ł́H�@�Ƃ��������������ł��B�ܘY�������������̉G�X�q�e�͌�Ɏ����Ƃ��Č��͂�����k�������ŁA�����ꂽ�H���S�o�͌������̂��C�ɂ���̉Ɛb�B�c�c�E���Ő����������Ă��Ă����������Ȃ��ݒ�ł��ȁB�������w�����̍ہA�ܘY�͕߂炦��ꂽ��ɏ��Y����Ă��܂��܂����B�\�Y��\��A�ܘY�\��̎��ł��B�ނ�̂��܂�ɑ������Ƃ����܂������U��m���āA�����u�����Ƃ����Ɗ撣��˂v�Ǝv���̂ł����B �@ ���ĕ����q�ł��B�����ł��B�����A�����܂œ���Ƃ͎v���܂���ł����i���j�B���܂������Ƃ������ǂȂ��B �@ �w�͂̐��ʁA���Ă���������Ɗ������ł��B
|
|
�d���E�Ӓ� �@ �́X�A���闷�̑m���s��K��܂����B���傤�ǔ~�̉Ԃ����J�̋G�߂ł����B���̔������Ɍ��Ƃ�Ă���ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ���l�̏���������܂��B�����͂��̔~�̂��������A�w�V�Í��a�̏W�x�̔~�Ԃ̉̂��������肵�܂��B�����Ď����̐��̂𖾂����܂��B �u���͎��͐l�Ԃł͂Ȃ��Ӓ��̐��ł��B�����̔������ԒB�ƐS��ʂ킹�A�Y��邱�Ƃ��ł��܂��B����ǒg�����Ȃ�Ȃ��Ɛ��܂�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł܂������G�߂ɍ炭�~�̉ԂƂ����͉������ׂȂ��̂ł��B�v�����Q���ď�������܂��B �@ ���m�͌Ӓ��̐��̂��߂ɂ��o�������܂��B�₪�Ĕޏ��͍Ăёm�̑O�Ɏp�������܂��B �u���Ȃ��ƕ��l�̎��ߐ[�����͓Y���ɂ���ĔO��̔~�̉ԂƂ��Y��邱�Ƃ��ł��܂����B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�v�K����t�̔ޏ��͐������A�̕��̕�F�̖ʉe���c���ĉ��̒��ɏ�����̂ł����B �@ ����܂��A����͂悩�����˂��A�Ƃ����̂����̍ŏ��̊��z�ł��B�����A�ŏ��̓X�g�[���[�����������̂��d��������̂����߂��̂ł��B�Ӓ��̐��Ƃ����̔������ƁA���邭��܂���Ă��킢��������ŁA�Ƃ�����y���̌��t�Ɏ䂩�ꂽ�̂ŁE�E�E�E�E�E�B����������Ȃ��B������ւ���Č���Ȃ��ʼn������ˁB �@ ���āA�|�p�̉��l�Ƃ����̂͏��A����ł͂Ȃ��Ă��̐��E�i����j���������������ɂ���悤�ɕ\���ł��邩�ł��Ȃ����Ō��܂邻���ł��B�����玄���������Ȃ�����т�̑S�̂ŕ\�����A�Ӓ��̔�����������l�ɑi����悤�E�E�E�E�E�E�w�͂͂��܂��B
|
|
�d���E�́X �@ �F�����́B �@ �@ �́X�Ƃ͊C���ɂ��ށA���N�̎p���������D���̗d������ł��B���̂��b�̕���͒����ł��āA���R�̘[�A�g�q�]�� �@ �����͌��̔���������H�z�̍]�ɍs���A�e�Ԃ̎����ɂ���܂�Ɠ���đ҂��܂��B����ƁA����~�����A���F�B�����������́X���C�����畂���яo�āA��l�͒��ǂ��y�����������ނ݂��킵�܂��B �@ �@ �����́X��
|
|
�����q�E�Z �@ ����߉�Ɉ��������A�Z���܂��B �@ ����ǁA����߉�Ƃ͈ꖡ�����Ⴂ�܂��B���܂ł��Ă����u���d���v���烌�x���A�b�v�����u�����q�v�o�[�W�����̗Z�Ȃ̂ł��B�v���̐搶�����A�w�Ƃ����q�����Ă�������̂ł��B �@ ����͗Z�̑�b�i���ƂǁA�Ɠǂށj�̂����~�ՁA�Z���͌��@�B��l�̗Z�͊��ɖS���Ȃ�A�Z����������ł������~���Ղ��p���l���Ȃ��A�r��͂ĂĂ��܂��Ă��܂��B �@ ���H�̖����̓��A���̑m��������K��܂��B����Ƃ����ֈ�l�̘V�l������A�����͗Z�̂����~�Ղł���Ƌ����Ă���A������̖����Ȃǂ��ē�����ƁA�ӂƂǂ����֏����܂����B���͂��̘V�l�����Z�̖S��ŁA�m���Q�Ă���ƍĂсA���x�͍݂肵���̋M���q�̎p�Ō���܂��B�Z�͖����̉��A���Ă̓��X���Ȃ����݁A����炤�z�������߂ĕ����܂��B�閾�����K���ƗZ�͌��̓s�ւƋ����Ă����܂��B �@ �ȏオ�w�Z�x�̂��b�̑S�̂ł����A���̕����Ƃ���͘V�l�̕������Ƃ��A�u�M���q�v�̗Z�ł���܂��B ���͍���A���߂Ă����q�ɍ��킹�ĕ������Ƃ����܂������A�Ȃ��Ȃ��C���̗ǂ����̂ł��B������Ɓu���̂��Ƃ��X�^�[�ƌĂ�ł�����v�Ƃ����悤�ȋC���i�H�j�B�M���q�����B �@ ���i�̂��m�Âł͂����q��^�������e�[�v���g���ė��K���Ă��܂��B���N���߂ĕ����q�������l���\�����킹�i���n�[�T���j�̎��A�u�������B����ς�{�������͂��Ⴄ�I�v�Ɗ������Ă����̂ŁA�����Ɩ{�Ԗ{���̂����q���ŕ����̂́A�܂��i�ʂ̋C���Ȃ̂ł��傤�B �u�{��������A�ْ��œ����^�����v�Ƃ����\��������܂����A����ȋ@��͐l���ɂ���������̂ł��Ȃ��ł��傤����A�u�X�^�[�v�ȋC���𑶕��ɖ��킢�����Ǝv���܂��B
|
|
�����q�E�Ɣn�V���@ �@ �w�Ɣn�V��x�́A����Y�`�o���܂��Փ߉��Ɩ�����Ă������̂��b�ł��B �@ �`�o�ɂ̓G�s�\�[�h�������A���@�̋Ɉӂ��������̂́A�V�炾�Ƃ����Ă��܂��B���̓V�炪���́w�Ɣn�V��x�̑�V��ł��B �@ �`�o�͗c�����A�Ɣn���ɗa�����Ă��܂����B���̈Ɣn����s���A�t�A�Ɣn�R�ւ���Ă��܂����B�F�ł킢�킢���Ȃ���y����ł���ƌ��m��ʎR��������Ă����ł͂���܂��B���ԓ��ł��̏ꏊ���߂��Ȃ��̂��C�ɂ���Ȃ������̂��A��s�͎Փ߉����c���ċA���Ă��܂��܂��B�c���ꂽ�R���A�Փ߉��݂͌��̐��̂𖾂����A�V��͕��Ɠ����ɗ͂�݂��Ɩ��܂��B �@ �����āA�`�o�ɕ��@�̋Ɉӂ������A���낤�Ƃ��܂��B�����~�߂悤�Ƒ������ގՓ߉��ɁA�u�����͂����e�Ɠ����悤�ɑ��ɂ���v�Ƃ����A���c�������ɋ����Ă����Ă��܂��܂����B �@ �t�̂���߉�ł͎d���Łw�Ɣn�V��x�����܂������A����͕����q�ŕ����܂��B �@ �Ɣn�V��̕����q�́u�����v�ƌĂ����̂ł���A����͎�ɗ��_�E�V��E�S�{�Ȃǂ̈А����������̂ł��B���́u�����v�ɂ͑��̂��́i�����A�����Ȃǁj�Ƃ͑傫���قȂ�_������܂��B����͕����Ƃ��ɓJ�̉��ɍ��킹��̂��A���ۂ̉��ɍ��킹��̂��Ƃ����_�ł��B���ʂ̕����q�́A�O�҂̓J�̉��ɍ��킹��^�C�v�ŁA�u�z�E�z�E�q�[�v�Ƃ����t���[�Y�ɍ��킹�܂��B�u�����v�́A��҂ő��ۂ́u�z�[�E�e���e���v�Ƃ����t���[�Y�ɍ��킹��^�C�v�ł��B �@ �ȒP�Ɂu�z�E�z�E�q�[�v�u�z�[�E�e���e���v�ɍ��킹��A�Ƃ͂����Ă͂��܂����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ�����B�Ȃ��Ȃ炱�̃t���[�Y�́A�J�E���ۂ̋[����Ȃ̂ł����A�l�ɂ͂���ȕ��ɕ������Ȃ��̂ł��B���ɓ��ŗ����ł��Ă��̂��������Ƃ��܂���B�Ƃɂ����A�����āA�����āA�����܂����đ̂Ɋo�������邵���Ȃ��̂ł��B�i���̂�����͂قƂ�lj^�����B�����_������Ŋ������ɂȂ�Ȃ�����K���܂����B�j �@ �撣��܂��̂Ō��Ă��������B
|
|
����o�������q�E�O�������_�_�y �@ �O�ցA�Ƃ́A�ޗǂɂ��邨�R�̖��O�ł��B�O�֎R�́A�_�l�Ȃ̂ł����A�������ł����H�@�Î��L�ɂ́A �@ �O�ւ̂��R���Ă����Ă��邨�V����̂Ƃ���ցA�������l�֕����邨�����^��ł��鏗�̐l������܂����B���̏��̐l������H�̓��A�����Ȃ��Ă����̂ň߂�������Ȃ����A�Ƃ��V����ɂ��˂��肵�܂��B���V����͂ǂ����A�Ƃ����Ĉ߂������܂��B���̐l�͊�сA���ɂ��܂��A�Ƃ����܂��B���V����͌Ăю~�߂ĉƂ͂ǂ����ƖK�˂܂��ƁA �@�@�@�u�킪���͎O�ւ̎R���Ɨ������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�З��܂������Ă��v �ƁA�Í��W�̉̂������āA���̗����Ă�����ڈ�ɗ��ĂˁA�Ə����Ă����܂��B �@ �C�ɂȂ�܂���ˁB�ŁA���V������A�T���ɂ����̂ł����A���̐�́A�O�ւ̐_�_�̒��Ȃ�ł��ˁi�O�֖��_����́A�R�S�̂��_�l�Ȃ̂ŁA�_�a�͂Ȃ��̂ł��B���R�S�����_��Ȃ̂ł��ˁj�B�����̓�҂̐��̖Ɋ|���n�������A��ɁA���������V���������߂��|�����Ă�̂ł��B����B����Ƃ����ցA�O�ւ̏��_������܂��B�����āA���V����ɎO�ւ̓`��������Ă�������A�V�Ƒ�_�����Ă����Ă��܂������̓V�̊�˂ł̂��b�������Ă�������A�Ƃɂ�������������₩�ɕ����V��ŁE�E�E�E�E�E�ƁA�����������b�ł��B �@ �O�ւ̏��_�������Ƃ��낪�����q�ɂȂ��Ă��āA��炪�ږ�̘e�c���q�搶�������ĉ������܂��B�e�c�搶�͉�X�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�������āA����͌��Ă������������ڗđR�ł��傤�E�E�E�E�E�E���y���݉������B �@ ����A�O�ւ̐_�l���Ēj����Ȃ��́A�Ƃ��v���ɂȂ�����������܂���ˁB�����ł��ˁB���������`���̕����L���Ȃ̂ł����v��ꂪ���ł����ǁA�������A�Ƃ������b�����邻���ł���B���ꂢ�ȏ��_����̂ق����O�ւ̓`�������ɂ͂ӂ��킵���A�ƍ�҂̕��͎v�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���ˁB���������v���܂�����B
|
|
���O�d���E�O�䎛 �@ �s���s���ɂȂ����q�ǂ���T���āA���̐l���x�́i�É����j���狞�̓s�ւ���ė��܂����B�����āA�쌱���炽���Ȑ��ω��̂����鐴�����֎Q�w���܂��B�q�ǂ��Ɉ���������S�ŋF�葱���鏗�̐l�́A�q�ǂ��Ɉ�������������O�䎛�֍s���悤�ɁA�Ƃ̖������܂��B���̐l�͊�сA�O�䎛�ւƋ}���܂��B �@ ����A���̂���O�䎛�ł́A���V���݂�Ȃŏ\�ܖ�̂����������Ă���܂����B�����ɂ͂��V����̒�q�ƂȂ����A�g���̂Ȃ����N������܂����B �@ �S����āA���̐l�͋�����ߍ]�ւƋ}���܂��B������̌i�F�����Ă��A�v���͉̂䂪�q�̂��Ƃ���B�����ցB�����������������c�c�B���̉����������Ă��܂����B�O�䎛�̏��̉��ł��B �@ �O�䎛�̏��́A���_���U�����ɂ��������̂������ŁA���͂��߉ނ���̋_�����ɂ� �@ �ςȂ������ď���ɏ���˂��������A�Ƃ����̂ŁA�݂�Ȃ͎~�߂ɗ��܂��B����ǂȂ��Ȃ��ǂ����āA���̏��̐l�͒m�������邵�A�݂�ȁA�b���o���̂ł��ˁB���̂Ƃ��A���N���A���̏��̐l�̌̋���m�肽����A���V����ɕ����Ă���A�Ɨ��݂܂��B �V�u�ǂ��̕��ł����v ���u�x�͂̍��A�������ւ̂��̂ł��v �q�u�������āI�@�������ցH�v ���u�����A���̐��͂܂������䂪�q �݂�Ȃ͂��̉R�����߁A�Ƃ����߂�̂ł����A���N���~�߁A�g�̏���������܂��B�ނ͂܂������疞�ŁA�l�����ɔ����ĕ�Ɛ����ʂ�ɂȂ��Ă������̂ł��B�悩�����˂悩�����ˁA�܂������O�䎛�̏��̌����ł���܂��B��q�͋��ɋA���Ă����܂����B �@ ���d���́A���̐l���q���v���ď����V�[���ł��B�����Ƃ��邺�B
|
|
���O�d���E�V�� �@ �����́A�����Ɛ̂̂��b�ł��B �@ ����Ƃ���ɁA�V�ˏ��N�A�V�ۂ����܂����B�ނ͂��̖��������Ƃ���A�ۂ̖���ł��B���ł��A�ނ͂��ꂳ�V����~���Ă����ۂ������̂Ȃ��ɓ������A�Ǝv�����琶�܂ꂽ��q�������ŁA���������܂ꂽ��A�ق�ƂɓV����ۂ��~���Ă����̂ł����āB�����āA�V�ۂ���Ɩ��t����ꂽ�ނ͂��̌ۂƂƂ��ɑ傫���Ȃ�܂����B �@ �Ƃ��낪�B���̍c��́A�f���炵�����F�̂��̌ۂ�~������܂��āB�����ǓV�ۂ���́A�����̑厖�Ȍۂł����́A�n�������āA�R���ۂ������ē������̂ł��B��������A�c��͉��ƁA�V�ۂ�����ɒ��߂ēM�������Ă܂ŁA�ۂ�D������Ă��܂����̂ł��B �@ �ł��A�������́A�V���牺���ꂽ�ہB�ۂɂ����ĐS������܂��B�V�ۂ�����ł���A���̌ۂ́A�N���@���Ă��A��؉���炳�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�c��́A�����̔��m��܂����B�����āA�V�ۂ���̂�������ɒ@���Ă݂Ă��炦��悤�g�����o���Ƃ��납��A���́w�V�ہx�̂��b�͎n�܂�܂��B �@ �c��ɌĂ�A�N���@���Ă���Ȃ��Ȃ����ۂ�łĂƂ̖�������������B���̋��낵���ƁA�S���q���v���S�Ƃ��������āA�������݂�܂��B�������B�V�ۂ���̌ۂ́A�������@���ƁA�̂Ȃ���̐����F���o�����̂ł����B��������邨�����A������̂̋���ł��܂��B �@ �c��́A�nj��u���Â��āA�V�ۂ���̗�����Ƃɂ��܂��B����ƁA���y��D�����N�̓V�ۂ���̗삪�������Ɍ���A���ӂ̎v�����q�ׂA�y�ɍ��킹�ĕ���x��܂��B�������A������ۂ�ł��Ȃ���B�������E���Ă܂Ōۂ�D�����c������ނǂ��납�A���ɔw���Ă��߂�Ȃ����A�Ƃ����f���ȓV�ۂ���̐S���A�f�G�ȉ��y�݁A�����킹���l�X���K���ɂ���̂ł����B �@ �S���Ђł��c�邾��A�Ǝv���Ă��܂��Ȃ����ł�����ǁA���̂��b�ő厖�Ȃ̂́A�V�ۂ���̊�т̕����Ȃ̂ł����āB�����āA���̕������A�d���ɂȂ��Ă���܂��B�ǂ����A�V�ۂ���ƈꏏ�Ɋ��ʼn������B
|
|
��������ŕ�����Ȃ��Ȃ�Č��킹�Ȃ��I �@�@�@�@�@�@�@�X�y�V�������@�\�@�w�|�����x �@ �Ȃ�Ɛ\���܂��Ă��X�y�V�����ł�����B�u���\�Ȃ�Ă�[�v�Ƃ��荞�݂Ȃ�������A�ǂ����ǂݐi�߂ĉ������ȁB�����ƁA���̊��Łw�|�����x�Ȃ番����͂��I�@�z���g�͕������ĂȂ��Ă��Ȃ��������C�ɂ͂Ȃ��͂��I�@���Ƃ����̂ł����ǂˁB�܂��͂��炷�����炢���Ă݂܂��傤�B���̂��ƁA�S��������Ă���܂��̂ŁA�����������������ڂ����̂ł����B���������ȕ��͂�������ǂ����B �@ ���͕��������B���̉ԍ炭�̂ǂ��ȏt�̓��ɔ��i��K�ꂽ�s�l�B�ނ�͑��V�c�Ɏd����g�ł��邪�A�s�ł��]���̒|�����֎Q�w�ɗ����̂ł���B�|�����ٍ͕˓V�����킵�܂����Ƃŏg�ɗL�������A���ٍ̕˓V�A���̐_�A�|�\�̐_�ł���Ɠ����ɕ��_�̐��i�����킹���Ƃ������ƂŁA�e���ʂ���̐M���Ă��B�l�C�҂Ȃ̂��B �@ ���āA�s�l�B���i�܂ł͗������̂́A���ւ͏M�ɏ��˂ΎQ�邱�Ƃ����Ȃ�ʁB�����ܗǂ������킹�����z�̒ނ�M�B���ƂƂ���V�l�E���̍D�ӂɂ��A�M�ɕ֑D�ł��鎟��Ƃ����Ȃ����B �@ ��Â��牜���i�ɒ����܂��܂���n�E�|�����ցB�n���������̒ނ�M�ōs���̂����獡�Ƃ͈Ⴂ�A���Ȃ莞��v�����͂��B�������A����B�^�����ɋP���A��Ƃ����܂������ɍʂ�ꂽ���̎R�X���B���ʂɉe�𗎂Ƃ��[�̒|�������B���Ƃ��ґ�ȌΏ�̗��ł͂Ȃ����B �@ �M���|�����ɒ����B�������ɓ����Ă������Ƃɕs�R������s�l�B�����A���n�������͏C�Ƃ̒n�Ƃ����̂́A�����̗���������ւ�����̂Ȃ̂ł���B�����A���̒|�����͈Ⴄ�B�������A�ٍ˓V�͏����̂��p���Ƃ��Ă����邵�A���̖{�n���́A���l�����̐����𗧂Ă�ꂽ�̂ł��邩��B �@ ���͂��̖������|�����ɏZ�܂��ٍ˓V�ł���A�V�l�͔��i�̎傽�间�_�ł������̂��B���̂��ق̂߂����ē�l�͎p�������B�����ցA��b���Q�w�ɗ��Ă���ƒm�����|�����̎Аl����������Ɍ���A�|�����̔����Љ��B�����āA���ɓ`���C�Ƃ̈�A���т�������B�R�̏ォ��ΐ��ւƔ�э��ނƂ����r�s�ł���B �@ �����ē������āB��a��������ɗh�炬���������Ǝv���ƕٍ˓V������A�V���̕���������B�g�������n�߂�Ƃ�������͗��_������A�s�l�ɕ��������ƁA�ٍ˓V�Ƃ��ǂ������Ă������B
�ڂ������������ �@�@�E�� �@�@�E��蕨 �@�@�E���� �@�@�E�S���f�ځi������t���j
|
|
���j���E��D �@ �\�w�|�����x�ŁB���_���A��A�s�̐l���A���Ă����āB��������A�n�w�̐l�X���w���o���܂���A�W�C�\�̍Ō������ɂӂ��킵���A���̂��߂ł����w���B �@ ���t�W�ɁA����ȉ̂�����܂��B
�V�T�����A���Ái�Z�g�̋߂��ł��B��������̉�����̂ˁj�ɂ���Ă��Ȃ������A�Ƃ������b�����ƂɂȂ��Ă���̂ł��B �@ �V�c���A�ےÍ��Z�g�̉Y�Ɏs�𗧂ĂāA���N�⒆���̕��Ȃ����A�ƉƐb�ɖ����܂��B����œs�̐l���Z�g�ɂ���Ă��܂����B �@ �s�͑�ςȐ����ł��B�l�������ς����܂��B���̒��ɁA�s�l�͕s�v�c�Ȑl�������܂����B�i�D�͒����l�Ȃ̂ɁA��a�̌��t��b���q�ǂ��ł��B��ɂ͋�Ղɏ悹�����������Ă��܂��B���̎q�́A�߂ł������Ȃ̂ŁA�ƕ���s�̐l�ɂ���܂����B���͂��̎q�ǂ������A�V�T���������̂ł��ˁB�V��E�̂�����ڂ�����D�𑆂��ł������l�ł��B���̂𖾂����ƁA�q�ǂ�����͏����Ă����܂����B �@ �����ցA���_������܂����B�����āA�V�̊�D���������炦�����ƈ��������Ă��܂����B��D�ɂ́A����������ς��ς�ł���܂����B�D�݂͊ɒ������A�^�яo���ꂽ����͕����ʂ�R�̂悤�B�Ȃ��߂ł����ł��ˁB
|
|
���\�ŃE�t�t�@�@�ߍ]�̔\�B �@ �J�͂�����������H�B�F���܁A���̂��H�ׂĂ܂��H �@ ���āA����A�܂��O��𐔂��邱�ƂƂȂ����W�C�\�B�ڋʂ͂Ȃ�Ƃ����Ă��A�\�w�|�����x�ł���܂��傤�ȁB���̎����\�ł�����A�������������Ƃ��̂悤�ɕ����オ���Ċ��ł���̂ł���A���ǂ��́B �@ ���āA�\�Ƃ������͎̂�������Ɋψ����������e�q���听�����A�Ƃ���������̂��Ƃ͂Ȃ�ƂȂ��F���܂������m�ł��ˁH�@�������゠����Ƃ���A�����܂ł��Ȃ������̒��S�n�͋��̓s�B���̎����������������A����܂ł��A�ˁB �@ �ŁA���\�Ƃ����͍̂�҂��ݏo�����̂ł͂Ȃ��A�J�Ԃɂ悭�m��ꂽ�`���E�`���������Ƃɍ���Ă���̂ł��B������F�̏O�̂悭�m���Ă���l�����o�ꂷ��̂ł��B�L���ǂ���ł́A�l�����̂��̂���҂̊G�����̔@���`�o����B�ނ̏o�Ă��邨�b�͂���Ƃ���܂��āA�V��ɏo�����ĕ��@�̋Ɉӂ���������w�Ɣn�V��x�ɂ͂��܂��āA�w���ٌc�x�w�G�X�q�܁x�w�����x�w�D�ٌc�x�w����x�w�ۑҁx�w�����x�ƁA���\�����Ŕނ̐l���͂��悻������ˁB�ނ��o�ꂵ�Ȃ��Ă��A�ޏ��̐Â����̏o��w�g��Áx�Ȃŗ��b��������d�g�݁B���Ƃ͌�������̂悤�ȉˋ�̕�������n�ɂ���Ă܂��ˁB�܂��A���ƕ���̍��M�ň���ȕ��Ƃ̕������Ă̂���l�C�B�����������l��肠�����Ă��H�@�܂��A���\�͏����Ė��I�@�Ƃ������͕����Ď���ł������҂Ɏ�����킹�c�c�Ƃ�����������̂ł��ˁA�����D���Ȃ���ŁB�����畉�����l�͂����ς������Ă܂����A�������l�́A�������̎O�l�B������A���g������Ύ傽��e�[�}�͏��������Ƃɂ͂Ȃ��̂ł��ȁB���̃e�[�}���C�ɓ����Ă��\�ɂ�����A���܂������Ă������A�Ƃ����悤�Ȋ����ŁB �@ �́B���͉��������Ă���̂ł��傤�ȁB�����������Ƃ��������������킯�ł͂Ȃ��̂ł���A�^�C�g������Ε�����ł��傤���ǁB���������A���������̒��S�n����������A����ɂ�����i�͑������ǁA�w�|�����x�̂悤�ɋߍ]������ɂȂ��Ă邨�b������ˁB���ꂪ����̂���ł��B�Ƃ���\�̎�����{�Œ��ׂ܂����Ƃ���A��܍�i������܂����i���s�Ȃ̂����A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���{������̂��͓̂�Z�Z�ȏ゠���ł����ǂˁj�B����������A�ߍ]�̖�������������Ă���ł��ȁB�ƁA�����������Ƃ��������������̂ł��B �@ �|�������l�A���_����̏o�Ă���w���E�x�́A������E���_������B�ߍ]�����ɂ���܂��ˁB�w�|�����x�̗��_����Ɠ������Ȃ�ł����ˁB �@ ��Â͂������������ݒn�B�����ς�����܂��B�֎��߂��ɂ͔N�V���Ă��珬�쏬�����Z��ł����悤�ł��ˁB�w�_�������x�w�֎������x�B�������ꂪ���܂ꂽ�ΎR�����A�������ɂȂ��Ă܂��B�������̏o�Ă���w�������{�x�B�S�l���́u����₱�́c�c�v�̉̂ŗL���ȁA���̖����Y�o���w��ہx�B�s�����A�������̊ւ�����B�S�l���ɑI��Ă��Ȃ��唺���傳��́A�u�ꖾ�_�ɂ��Ȃ肾�����ł���A�w�u��x�B���Â�ɂ������b�ɂ͖ؑ]�`���̔ޏ��̕���w�b�x�ƁA���b�̕���w�����x������܂��B���ꂩ��A�ԊO�d���ŕ����Ă����������w�O�䎛�x��Y�ꂿ�Ⴂ���Ȃ��ˁB��Â͋��ɂ��߂��A�������L���ł�����ˁB�������A��b�R��ɂ������̂�����܂��B�V�炪���߉ނ���̌��e�������Ă����w���x�A�{�鐛�����^�̗�A�w���d�x�B���i�͑厖�Ȍ�ʘH�ł����ˁB�D�œ����悤�Ƃ���l�����������~�߁A�\�͂��ӂ�킸�|�ŏ������~���o�����`�̖����̖`�������A�w���R���m�x�B �@ �ΐ��𗣂��Ƃ��܂�Ȃ��̂ł����A��ɂ������܂����w�G�X�q�܁x�B�`�o�̌����̒n�͋ߍ]�̋��̏h�A�Ƃ����Ƃ���Ȃ̂ł��B�Δ���������Ƃ�����܂��B�����āA�w�����̕���w�]���x�͎�R�̏h������B �@ �������Ă݂Ă݂܂��ƁA�����̋ߍ]�Ƃ����̂́@�@���i�@�A�֏��Ƃ��̎��ӂ̎�������@�B�X���Əh��A�Ƃ����O�̃|�C���g�𒆐S�ɂƂ炦���Ă����悤�ł��ˁB�Ȃ�قǁB����A�����A�Ƃ������A����͍����ς��Ȃ��̂����B���[��A�����Ƃ��낢��Ƒf�G�ȂƂ��낪������ǂȂ��c�c���傢�ƁA�F�ɂ��炵�߂������悢��������܂���ȁA�E�t�t�B
|
|
���ꌧ����w�\�y�����z���g�̔\�y���ɂȂꂽ���B �@ �����āA�m��Ȃ������̂��B�\���o�������Ȃ������ɢ�\�y����Ǝ��̂��邱�Ƃ������Ɍ��疳�p�̏��Ƃł��邩�ȂǁB�\������Ă���l�ɋ����Ă��������Ă��邩��A�\�y���B�\�̌o���̂���搶����\�y�͂�����棂Ƃ����ĉ��������̂ŁA�\�y���B���ꂪ���������ȂǂƂ͎v�������Ȃ������B�f���Ƃ����Ε������͂������A���������P�זE�̂��炢�́A����B �@ �������\�̂��Ƃ������A�O�i�Ƃ����Ƒ傰�������j�ɂ��i�o����悤�ɂȂ��āA���Ԃɂ�����Ȃ��Ŕ��f���Ă��邱�Ƃ̋��낵���ɔۉ��Ȃ��C�t�����ꂾ�����B�r������B�����֔��B�̂̐l�͌������Ƃ������Ă���B�܂���������Ȃ̂��B�u�\�y���v�u�W�C�\�v�Ɩ�����Ă��܂��A�ނ�������̓��ɂ͈Ŗ���o�b�N�ɂ������ʂɓ��D�̂��o�������т������Ă���̂����肠��Ƃ킩��B�������A������ɂł���̂͗H���Ƃ͂������ꂽ�d���E�f�w�����B�����Ƒ����̐l�ɁA�u�\�A���Ă���Ȃ���H�v�Ǝv�킹�Ă��܂����ɈႢ�Ȃ��B�͂Ȃ͂��S�ꂵ���B�u�����A����͎d���Ƃ������̂ť���\�͏H�ɂ���ł����ǂˁB��낵��������A���ɗ��Ă��������ȁv������������ǂ�Ȃɂ��A�ǂ�Ȃɂ��\�\�B�`�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���������g�ŏ������邵���Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��B�������Ƃ��Ȃ��A�Ƃ����̂͂�ނȂ��ɂ��Ă��A����\�����Ȃ��̂ł́A�b�ɂȂ�Ȃ��B�����A��邵���Ȃ��̂��B �@ ���ꂩ��A��X�̐킢�͎n�܂����\�\�Ƃ����Ίi�D�͂������R�ɂȂ�B���l�L�����ށB�ǂ����܂�ď��߂Đ^��������l������B���߂Ă����ł����Ă����Υ���Ɨ��ɐ��Ɏ�����킷�悤�Ȃ��Ƃ��炵�Ȃ������B�������A���͒����ɕ��݂�i�߂�B�l�͕����ɔN���Ƃ�B
�@ �S���̗]�k��O��̖����Ȃ������B�@�؉�Ƃ́A�|�����̍�̖��ł���B���N�����\�ܓ��ɍs���Ă���B�̂͘Z���\�ܓ��ɍs���Ă����������B���̐_�ł���ٍ˓V�ɉJ�������̂��B�@�؉�ł����������́A���N�A�ٍ˓V�����V������[����Ă����B�e�c�搶���ږ∥�A�ŏq�ׂĂ�����u�����ŌÂ̘@�؉�ٍ̕˓V�v�Ƃ́A���̂��Ƃł���B�����A�|�����ɂ͐��́A���␔�\�ٍ͕̂˓V��������̂��B�����ȓ��ɂ��ӂ��V���B���ɉF��_���悹���A���]�̍����ł���B�F��_�͘V�l�ŁA�͎̂ւł���B���ꂪ�A�ٍ˓V�̓���łƂ���������A�����^�̍̕��Ԃ���j�R�j�R�Ƃ���������Ă���B�ނ͈�̐_�ł���B��̐_�ƁA���̐_�B�ď��E�ߍ]�Ɏ��ɂӂ��킵���B�Ă��D���Ȃ�A��x�͂��Q�肳��邪�悩�낤�B �@ �����āB�����A�\�y���͏��߂ċ����āu���ꌧ����w�\�y���ł������v�Ɩ���邱�Ƃ��ł���B�u�W�C�\�v�̊Ŕɂ��A�����A�U��͂Ȃ��B����߂���_��A��������͐��Ȃ��B
|