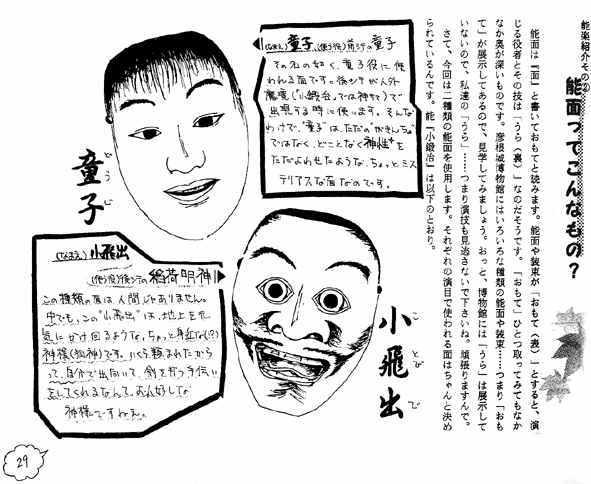
能楽「小鍛冶」
能面
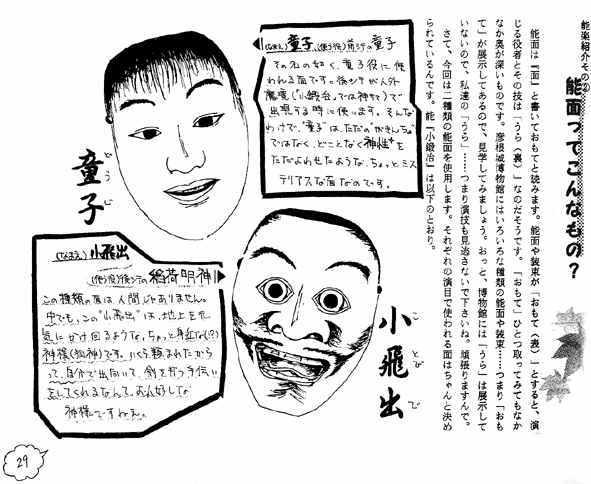
作り物
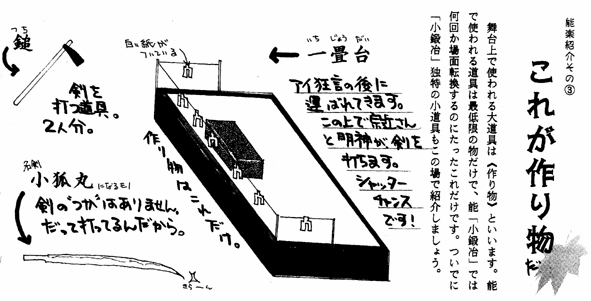
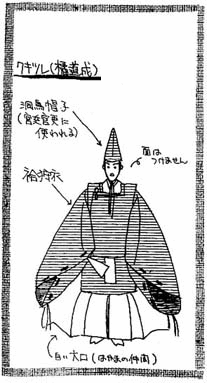
*1 橘道成さんは残念ながら架空の人物のようです。以上。 *2 “小鍛冶”というのは宗近の称号のようなものです。宗近は実在の人物で、やはり一条天皇の時代に、京都に三条に住んでいたようです(三条には代々鍛冶師が住んでいたらしい)。それで三条の小鍛冶宗近。なるほど。 宗近は腕のいい鍛冶師だったようで、鞍馬に奉納した彼の刀を後に源義経がもらいうけたとか、いくらかの書物にも載っています。名刀“小狐丸”も実在し、彼が打ったようです。稲荷明神と、かどうかは分かりませんが。 蛇足ですが、“小狐丸”には別の言い伝えもあるんですね。ここには書きませんが。どちらにしろロマンのある物語です。 |
*1 刀というものは、弟子と師が向かい合って互いに鎚を打つもの。相槌を打つ、なんて言葉もありますよね。相手の言葉に同意してうなずく、話に調子をあわせるという意味です。 |
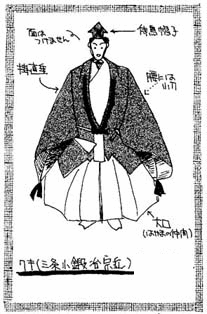
*1 一条天皇は、まさに藤原氏による摂関政治の全盛期の天皇です。彼の奥さんに仕えていた清少納言であり紫式部。彼の時代には宮廷文化が花咲き、多くの歌人や賢臣が彼のもとに集い、、また彼自身も学問を好み詩才にも富んでいたとか。かれの時代は聖朝とも呼ばれました。 |
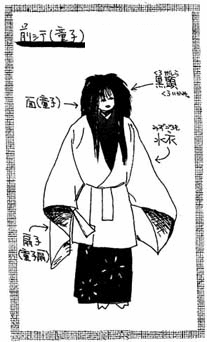
*1 住んでいる土地の鎮守の神……だと思うんですけど。 *2 神様というものは、例え変身してもどこか神秘性をかもしだすものなんでしょうか。まあ本当にその辺で遊んでそうながきんちょに化けても、宗近さんは本気で聞いてくれないでしょうから。 |
|
*1 仕舞「鶴亀」参照。 *2 この人は幽霊です。試験に落ちて憤死したんですが、玄宗皇帝に手厚く葬られたので皇帝を守護するようになったと、そういうわけです。 |
なんか話が飛んだような…と思った人がいるかもしれませんね。演能の都合上、少し謡がカットされています。そうなんです。 |
| どうでもいい話…。 倭健命(日本武尊)は、本名は小碓命といいます。景行天皇の皇子で、その勇猛さに恐れを抱いた天皇は、倭健命を休みなく反対勢力の討伐に行かせて都から遠ざけようとするんです。童子が語る皇子と草薙の剣の活躍物語もそんな遠征のひとつ。皇子は「いつになったら都に帰れるのか」と嘆きつつも数々の激戦や苦難を乗り越えていきます。東へ旅立つ前に、伊勢神宮で伯母の倭姫命から草薙の剣を受け取ります。 アイ狂言が言うんですが、草薙の剣はもとは天叢雲剣とも言い、皇子が草を薙ぎ払って難を逃れたことから草薙の剣と改名した、とか諸説あるんですけど、童子の話では最初から草薙の剣です。 で、見事に勝利を治めるわけですが、後にこの剣を手放した事で皇子は命を落とし、都に帰ることはできなかったんです。悲劇の英雄ですね(涙)。 もし、話の途中で童子に倭健命がのりうつったのだとしたら、童子がふっと遠山を眺める場面は、遠い都を思っているのかもしれませんね。 |
*1 めでたいってそりゃあ天皇の霊夢に出てくるような剣だしねえ。 |
このページには訳がありません。あしからず。でも何となくわかるでしょ?でしょ?

*1 一度口にしたこと君主の言葉は、汗が再び体内に戻らないように取り消すことができない、という意味。 *2 イザナギの命とイザナミの命の息子さん。乱暴者で、事件を起こして追放され、出雲に来た、という話。 *3 名剣、という意味。古代中国で、「干将」「莫耶」というふたつの名剣があったそうな。ちなみに、「干将」は剣を作った刀工の名で、「莫耶」は、これを助けた奥さんの名前からとったとか。 |
*1 多賀大社にまつられている神様方。天照大神と須佐之男命や、国土、山川草木の神様方の両親。 *2 日本の刀剣の祖と伝えられている。伝説上の刀工。大和の人。 |
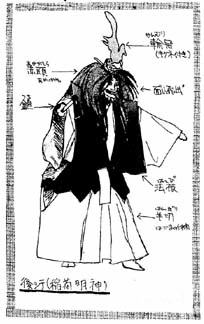
*1 もちろん、一条天皇のこと。 *2 「謹上、再拝」というのは神様に祈る時の決まり文句みたいなものだそうです。 |
*1 刀剣には製作者の名前を入れるんです。それが銘です。彦根城博物館にも刀剣が展示されているので、見てみてください。 |
| どうでもいい話…。 稲荷明神は、鍛冶をつかさどる神様じゃありません。すべての食物をつかさどり、田の神様(農業の守護神)ともされています。そんなわけで、稲荷明神は、刀鍛冶に関しては素人…? 謙虚に相槌として出てくるのも頷けます。農業の守護神が打った剣ですから、そんな剣で国を治めれば、五穀豊穣は間違いなし。武器なのに武力的な特殊効果ではなく、豊作間違いなし、なんて平和な世の中だからこそですね。こんな武器なら大歓迎です。 ちなみに、狐は稲荷明神の使者だそうです。 |
|