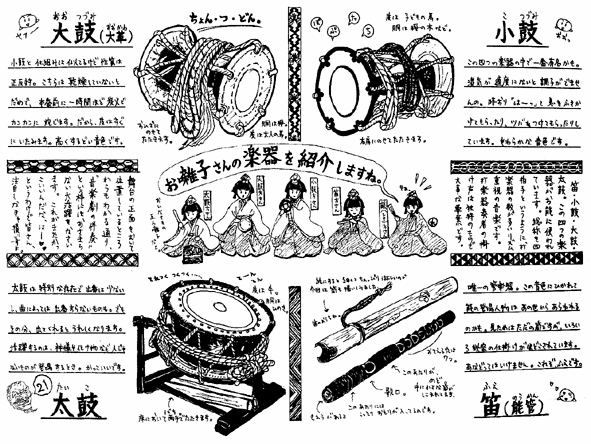
<一期生 R.M>
■第四回 淡海能■
|
平成十一年十月十五日(金)正午始
連吟 竹生島 素謡 土蜘蛛 舞囃子 胡蝶 菊慈童 仕舞 鶴亀 敦盛クセ 班女クセ 小袖曽我 羽衣キリ 舞囃子 海士 猩々 OG会出演独吟 経正 招待校出演 佛教大学能楽部 顧問出演舞囃子 船弁慶 招待校出演 京都橘女子大学能楽部 番外仕舞 花筐狂 鉄輪 能楽 小鍛冶 附祝言 終了予定 十六時十五分頃
|
|
学長挨拶 マンガと能 滋賀県立大学学長 日高敏隆 あちこちからどんどん送られてくる本、雑誌、PR誌などの山と、半ば闘うようにしながら目を通していくのが、ぼくの深夜のしごとである。かなりしんどいこととはいえ、ときどき目を洗われるような記事にぶつかって、思わずひきこまれたり、考えこんでしまうたのしさもある。 先日、中部電力が出しているPR誌「交流」に、漫画家の里中満智子さんと詩人の永田弘氏との対談が載っていた。 里中満智子の次のような発言がおもしろかった。 「活字、マンガなんていわれますけどおかしいですよ。活字とか文字とか言葉がなければ、マンガは成り立たないですね。」 これは能にもいえることではないか? ぼくはすぐそう思った。 前にも述べたように、能は謡で成り立っている。謡が舞を意味づけているのであって、それは世阿弥がいっているとおりだとぼくは思っている。 大学祭のときの能楽部の能を、ぼくはいつもたのしみにしているが、開けた空間の、ときにはかなりの風も吹く野外舞台で舞われる能は、謡がよく聞きとれない。 それなら閉じた空間である能舞台で、という問題ではない。舞い手が小さなマイクをつけるとか、観客にイヤホーンをもたせるとか、何らかの方法を考えてみることはできないものだろうか? 脇田晴子先生の「マニュアル化」の話も思い出しながら、一人、こんなことを考えて、つい夜の更けるのも忘れていた。 |
|
顧問挨拶 滋賀県立大学能楽部顧問 脇田 晴子 早いもので、淡海能も今年で第4回を迎えます。そして去年からは、文字通りの能楽会として、4年生が能楽「竹生島」を出し、今年も能楽「小鍛冶」を出すこととなりました。創立間もない滋賀県立大学の創立間もない能楽部ですが、進歩の速さにはびっくりします。これはひとえに深野新次郎先生の懇切な御指導の賜物ですし、部員の皆様の熱心さのいたらしむる所でしょう。 近江はもともと近江猿楽の発祥地であり、猿楽=能楽の隆盛な土地でした。佐々木道誉等の能楽の愛好者もいたので、文化程度が高く、近江能楽は幽玄をもととしており、大和猿楽は「ものまね」をもととしているといわれています。能楽の大成者、世阿弥は日吉猿楽の犬王道阿弥を激賛しております。天女の舞を「さらりささと、飛鳥の風にさたがふがごとくに舞ひしなり」と書いています。源氏物語の六条の御息所の生霊が光源氏の正妻葵上に取りついて殺すという話に取材した、能楽「葵上」は、近江猿楽の曲だといわれていますが、その「葵上」の犬王道阿弥の演技も世阿弥は褒めています。鎌倉末期とか南北朝期の人といわれる人ですが、この「葵上」の後場でも使う般若の面などの名作を残した面打師の 私も近江の地に勤めることになって、いろんな所に能楽が根づいていることを知って、びっくりすることがあります。たとえば、近江に残る「おこない」といわれる村共同体の新春の言祝ぎの行事も、みんなが宴会をして、一言づつ謡を謡うのがメインの行事になっています。まるで能狂言の中の酒宴で、ひとりひとりが順に小謡を謡う場面のようです。ああ舞台のなかで見たような場面が、現実に生きているとびっくりした次第でした。 能楽は「猿楽の能」といわれたように、能芸すなわち劇的な筋立てで、神や昔の人が示現して舞を舞ったり、いにしえを語るということが、世の人々に迎えられて、隆盛になったと思われます。しかし、歌舞伎や文楽を経た現代から見るとやはり、能楽のすじだては単純です。しかしその面白さは、その単純さにあると思えます。私は中世が専門だから、中世らしい素朴さが大好きです。直截な演技、香り高い文章、そのなかにはずいぶん精緻な演技も隠されているのですが、それが表にあらわに見えると下品だということになります。しかし、だからといって何の演技もないのは退屈です。そこが能楽の難しいところなのでしょうか。どれも同じように見えて、その表現が微妙に、曲によって役柄によって違うところが、面白いと思います。 大陸の中国や韓国から渡来した舞楽の影響を受けつつ、日本固有の伝統のなかで発達してきた能楽、それ以後の伝統芸能は多かれ少なかれ、能楽の影響を受けています。能楽が日本の伝統芸能の基本の型を決定したということは動きません。 皆さん、能楽を見て、舞い謡って、日本の伝統芸能にふれるよすがにしてほしいと思います。皆さん、淡海能を見に来てください。もっと熱心な人は、能楽部に入って下さい。 |
|
連吟・竹生島 昔、延喜帝(醍醐天皇)に仕える朝臣が、霊験豊かな弁才天がおられるので有名な竹生島にお参りに行きたくて、琵琶湖畔までやって来ました。丁度そこに、老人が若い女性を伴い釣船を出しているのを見かけます。それに、便船を頼み、乗せてもらいます。 のどかな春の景色を楽しみ、竹生島に着きました。老人は、朝臣を神前に案内します。そうすると、女も一緒に来るので、ここは女人禁制のはず、おかしいと思い尋ねます。すると、弁才天は女性の姿であり、女人を分け隔てはしないと語り、二人は実は人間ではないと言って女は神殿ヘ、老人は波間に姿を消しました。 その後、弁才天の社人が出てきて、朝臣に宝物を見せます。そうしている間に、社殿が鳴動し、光輝き、音楽が鳴り出したと思うと、弁才天が現れ舞います。続いて、湖上が波立つと、水中から龍神が現れ、朝臣に金銀珠玉を捧げ、激しい舞を見せます。そして、弁才天と龍神は、国土鎮護を約束して、弁才天は社殿へ、龍神は湖水へと飛んで入りました。 去年も来て下さった方は、記憶に残っておられるかもしれません。今年は、最後の部分を謡います。皆様は、竹生島に行って、弁才天と龍神に会えましたか。まだ私は会えていないので、行かなくては。
|
|
素謡・土蜘蛛 「私は胡蝶と申しまして、源頼光にお仕えする者でございます。 さて、頼光様も人でございます。突然ご病気になられたのです。私は 「余が伏せっておると、真夜中だというのに体調を聞いてくる者がおる。どうにも見覚えのない僧じゃ。『我が背子が それを見るよりも早く、枕元にあった刀・膝丸を抜き放ち、二太刀ばかりくれてやると、すうっと消えてしもうた。……これはきっと膝丸の霊力のおかげに違いあるまい。これからは『蜘蛛切』と呼ぶことにしよう」 「殿がなにやら叫ぶ声がしたので、この これを追うと、怪しげな塚に続いておった。『我こそは源頼光に仕え、腕利きと呼ばれる独武者だ! いかなる天魔鬼神なりとも、その命を断ってくれるわ!』と叫び、塚を崩すと、岩の陰から火炎を放ち大水を吹き出しながら、土蜘蛛が現れたのだ。 土蜘蛛は『ワシは昔、葛城山に住んでいた蜘蛛の精である。この世に災いをもたらさんと、頼光に呪いをかけたが、かえって逆効果であったようだ』と言う。そのようなこと、許すわけにはいかぬ。一斉に仕掛けたところ、糸を繰り出され、手足を縛られてしまった。だが、神の威徳を信じて斬りかかると、剣の光を恐れるので、怯んだところを斬り伏せ、首をとることができたのだ」 源頼光は実在の人物で、かの源頼朝の先祖に当たります。彼は四天王( 「我が背子が〜」という和歌は「古今和歌集・
|
|
舞囃子・胡蝶 胡蝶の精には秘めたる思いがありました。恋しいあの方に一目でいいから会いたい。できれば一緒に戯れたい。けれど、二人(?)は住む世界が違いすぎました。暖かくなって初めて生まれてくる胡蝶と、まだ寒い頃、どの花よりも先に咲く梅とでは。それでもあきらめきれない思いを抱えた胡蝶の精は、ある日一条大宮の満開の梅を眺めている僧に出会います。都に住む女性になりすまし尋ねると、僧は春になったので吉野から都見物に来たそうです。せっかくなのでその梅の由緒などを語ってあげると、僧は感心し、彼女の名前を尋ねます。なんとか正体を隠そうとするのですが、あまりに何度も聞かれるので終に胡蝶の精だと明かしてしまいます。そしてさらに支那(中国)の荘子が夢の中で胡蝶となった話や、光源氏が童に胡蝶の舞をさせた話をします。その際、紫上が秋好中宮に詠んだ「秋が好きな貴方は春に生まれ、春を生きる胡蝶までお嫌いなのですか。」という歌を詠み、僧の夢に現れることを約束して姿を消します。 僧は半信半疑ながら、梅下でお経を読み、眠ろうとします。そこへ現れたのは胡蝶の精。美しい本来の姿です。前述の秋好中宮から紫上への返歌、「いえいえ、貴方の心にお隔てがなければ、私は胡蝶の舞を見たいと思っているのです。」というように、二人(?)の間の隔てはなくなり、戯れ遊ぶ仲になったのです。これもみなありがたいお経のおかげです。そうして胡蝶の精は喜びの舞を披露し、明けゆく空にひらひらと消えていくのでした。 私は昔から蝶々が大好きでした。しょっちゅう近所にアミとカゴを持って、捕えに行っていました。捕えるという行為が好きだったのかもしれません。そして(もっと四季折々の花に戯れていたかったのでしょうが、)カゴの中に死ぬまで閉じこめていたことも多々ありました。つぐないになるとは思いませんが、今日はあの蝶々たちの分も、梅と戯れ喜び舞いたいです。
|
|
舞囃子・菊慈童 「なに? 慈童が、王の枕をまたぎおったと…」 「なりませんぞ、王。お庇いになられては…」 「他のものに示しがつきませぬ」 「ならば、せめてこの妙文を…」 七百年の時を越え、今なお生き続ける慈童。 具一切功徳慈眼視衆生。 福聚海無量是故應頂禮。 菊咲き匂う谷間で、少年は仙人になった。 思い出深き枕を携え、昨日も今日も、明日も菊の中。 妙文の記された菊の葉。 伝うしずくが集まり薬水をたたえる泉となる。 それは、命を永らえる芳ばしき酒水。 「穆王、私は元気です。 王にいただいた妙文と菊のおかげで 私は今でも、あの頃の姿のままです…」 人里離れた山奥に通うは穆王の心か。 狐狼野干の棲む山に届くは観音の慈悲か。 あくなき人間の欲望をかなえる夢の谷の出現。 不老不死…ついに、文帝の宣旨が下された。 水源に分け入った家臣がそこに見たものは。 永遠の童子・菊慈童。そして菊・聞く・菊・効く・菊。 罪を犯した者と罰する者。 それぞれに思いは切なく、哀しい。 さあ、東の籬の下に咲く菊を摘もう。 悠然と南の山に目を向ければ、ほら… 陶淵明も渇仰した菊源郷が、(ウソ) 今日ここに再現される! かどうか… 旧暦重陽の節句を前にあなたのレイナがお送りする 愛とときめきの、そしてめでたき菊・ファンタジー。 観世音菩薩も照覧あれ! 乞う御期待。
|
|
仕舞・鶴亀 新春、穏やかな気候の中で一年で番最初の行事行われようとしている。ここは唐、玄宗皇帝の建てた月宮殿である。今日この日の公事のために朝廷に仕える役人、高官が一億百人以上集まった。玄宗皇帝をたたえる彼らの声ははなはだ大きく天に響き渡った。 月宮殿はすばらしい作りである。庭の砂は金と銀、宝石を連ねて敷き、幾重にも重ねられた錦の床。瑠璃をあしらった扉、シャコ貝の輝きを持つ桁、階段は瑪瑙である。そして極めつけは庭の池で飼われている鶴と亀だ。さながら蓬莱山のごとき月宮殿にて、正月の慣例行事である、鶴と亀の舞が行われる。そして玄宗皇帝に自らの長寿を授けるのだ。 玄宗皇帝は鶴と亀を褒め、ごきげんで自らも舞う事にする。仕舞はこの部分である。 月宮殿と国土の繁栄を称え、皇帝らしく堂々と舞った後長生きできる、と言う意味を持つ長生殿へと還っていくのであった。 「鶴亀」という題名にだまされて鶴と亀の舞だと思わないで下さい。主役はあくまで玄宗皇帝です。彼が一言謡って舞だせばそこはもう月宮殿、前述の豪華絢爛たる建物を想像しつつご鑑賞下さい。
|
|
仕舞・敦盛クセ 一の谷で、平家の公達平敦盛を討ったことを痛ましく思い、出家して蓮生法師となった源氏の武将・熊谷直実が、一の谷に向っている。自分の討った敦盛を弔うためである。 一の谷に着くと、仕事の帰りに草笛を吹く男達に出会う。その中に一人だけ帰らない男がいた。蓮生法師が理由を問うと、十念(南無阿弥陀仏を十回唱えること)を、行ってほしいとのこと。聞けば、敦盛の縁者であるという。 その名を聞いて心打たれた蓮生法師は、心から念仏を唱え始める。すると男は、感謝し、自分の名はいわなくても分かるはずだと言って、どこへともなく消えていく。 その夜、敦盛の菩提を弔う蓮生法師のもとに、軍姿の敦盛の霊が現れ、自分は法師の回向によって成仏できた、と礼を述べると、懺悔のため、昔語りを始める。 彼は平家がおごりたかぶっていたこと、都落ちをしたさまを物語り、思い出の舞を舞い、戦いの前に笛を吹いたことを述べる。 そうした物語をした後、敦盛の霊は仇を恩で報いてくれた蓮生法師に重ねて礼をいう。そして、すでに二人は敵同士ではなく、ともに蓮台に生まれ変わる身(成仏する身)であることを告げ、今後も回向してくれるよう頼むのだった。 今回舞うのは、敦盛が昔語りをしているところである。
|
|
仕舞・班女クセ 初めてするお仕舞が、狂女です。先輩のお話をきいて、よく分からないけれども、これに惹かれました。その内容とは。 美濃国野上宿の可憐な遊女で、 そうしていたら、宿の主人に口汚く罵られ追い出されました。しかし、少将への思いは募る一方で、狂女となってしまいます。そして、下賀茂の社で神に祈願を捧げていると、なんと少将が参脂に、やってきました。 そのお供の者が、バカにし、舞ってみよと言うのです。花子、形見の扇を手にし、班女と同じ身の上を悲しみ、少将のつれなさを恨み、狂おしく舞いました。そうしたら、扇に少将は気づき、お互いに逢う事ができ喜びました。めでたしです。 私が舞う部分はまだ会える前で少将への思いを込めて舞っているところです。元々「班女」とは前漢武帝に愛されたが、後に捨てられた女の人です。秋の扇のように捨てられて嘆きの詩を作りました。扇の果たす役割とはすごいものです。悲恋の象徴として、また恋人との再会の契機として働きます。 ところで、「班女」とは待つ女です。その優美さが少しでも出せるようにがんばります。
|
|
仕舞・小袖曽我 十郎 しかし、ついに満江は折れて五郎の勘当を解き、形見に小袖を与えます。兄弟は喜び勇んで別れの舞を舞い、祐経が出席する巻狩に遅れないよう、急いで出立するのです。 「吾妻鏡」には『廿八日癸巳。小雨降る。日中以降は霽(晴)る。子の剋、故伊東次郎祐親法師が孫子、曽我十郎祐成・同五郎時致、富士野の神野の御旅館に推参致し、工藤左衛門尉祐経を 私の役は兄・十郎。五郎役と二人で舞う「相舞」という舞い方も有りますが、「仕舞」は一人きりです。彼は生きている若武者なので、この前後の仕舞の中では最もリズミカルで勇壮な舞だと思います。問題は、私にリズム感がないことですが……努力と気合でなんとかしましょう!
|
|
仕舞・羽衣キリ 今日もいい天気。三保の松原に白龍という漁師が釣りにやってきました。のどかな春の浦を眺めていると、空中に花が降り、音楽が聞こえ、良い香りがします。どうした事かとあたりを見ると、一本の松に美しい衣がかかっています。白龍はその衣を家に持って帰ろうとします。すると 「その衣は私のものです。返して下さい。」という女性の声が。聞けば女性は天女で、衣は天人の羽衣であるとの事。それを知った白龍はそんなに珍しい物を返すものか、と言います。天女は住み馴れた空を懐かしみ、羽衣がないと天へ帰れない、と悲しみます。その姿はあまりにも痛々しいので白龍は衣を返すことにしました。そのかわり、天女に天人の舞楽を見せてほしいと頼みます。天女は喜び、舞うためには羽衣が必要だから先に返すように言います。白龍は羽衣を返したら舞わずに帰ってしまうのだろう、と言うと、天女は「天に偽りはない」と言います。白龍は自分の疑いを恥ずかしく思い、羽衣を天女に返しました。かくして天女は約束どおりに美しい舞をみせて天へ帰っていったのでした。 お仕舞では天女がひらひらと天へ帰っていく場面を舞います。我ながら似合わない役なのですが、このお話の舞台は駿河国、つまり静岡県です。私は静岡県人なのです。自分のふるさとのお仕舞ですから特にがんばってやりたいと思います。
|
|
舞囃子・海士 「ああ、ありがたいお弔いでありますこと。この御経に導かれて、五逆の罪を犯した その御経とは法華経。「提婆達多品第十二」の章には、悪人成仏と龍女成仏についてえがかれていて、日本においては法華経の中でも特に尊ばれ読まれてきた。 その章にて、龍王の幼い娘である龍女は仏を讃えて「深達罪福相、編上於十方、微妙浄法心、具相三十二、以八十種好、用荘厳法身、天人所戴仰、龍神咸恭驚」と唱え、三千大世界に値する宝珠を釈迦に献上し、女人の成仏を信じない者たちの前で忽然と男児に変じて成仏を果たす。 さて、前場において海女が再現して見せたのは、奪われた宝珠を水底の龍宮から取返す劇的な場面である。もしも成功すれば藤原の大臣淡海公は二人の間に生まれた我が子を跡継ぎにすると約束した。深い海底にて、死人を忌み嫌う悪龍たちを退けるために、海女は乳の下をかき切って、盗み取った玉をそこに押し込めて合図をすれば、人々はその命綱を引き上げる。海女の命は失われたが、宝珠は取り戻され、約束通りに息子の房前は大臣の跡継ぎとなった。 その息子による母への供養の場にて、法華経の中で幼い龍女が仏を讃えたあの言葉を、龍に殺され龍女となった海女も唱え、その御経のありがたさを讃えて舞を舞う。(今回の舞囃子はこの部分です。) 我が子の栄達のために自らの命を捨てても宝珠を取り戻した海女と、釈迦に宝珠を捧げたのち南方無垢世界へと成仏した八歳の幼い龍女の姿が、重なりあう。 やがて、法華経の功徳によって「天竜八部、人与非人、皆遙見彼、龍女成仏」の経文のままに、龍女となった海女も成仏することができたのだった。
|
|
舞囃子・猩々 秋の夜、月は美しく菊の花もまた艶やかでございます。ここは潯陽の江。高風は壷に菊花の酒を湛えてお酒が大好きであり、彼のよき友である猩々が現れるのを待っておりました。一人で先に一杯やりながらね。 このお話の舞台は昔々の中国。高風は揚子の里、金山の麓辺りに住んでおり、親孝行で大変評判がようございました。 ある晩彼は、市へ出て酒を売ったらお金持ちになっちゃった♪という夢をみました。早速その夢の通りに市へ出てお酒を売りますと、まぁ何と羨ましいことかな、本当にみるみるお金持ちになってしまったのです。 もうこれだけでも充分不思議なことですけどね、彼には他にもちょっと気になることがありました。市が立つ毎に彼の店に来てお酒をさんざん飲んで帰って行くお客さん。この人の何が不思議かって言うと、そう、いくら飲んでも顔色ひとつ変えないの。不思議に思った高風はその人に名を尋ねました。 猩々、海に住んでるんだ そう言い残してそのお客さんは帰って行きました。 これがお二人の出会いなのでございますね。 さぁ、高風は一人で銘酒を飲んで楽しんでおります。そうして待っていると、ほら、おいしそうな銘酒に釣られて(もちろん良き友に合うために・・・・・?)海の中から猩々が現れたではありませんか。二人で酒を酌み交わし、おいしいお酒にすっかりご機嫌の猩々は、秋風の気持ち良さにもつられてか、ピラピラと一舞なさいます。 そして別れ際に猩々は素直な心を持つ高風に汲めども尽きぬ酒壷を与え、海の中へと帰って行きました・・・。 今回の舞囃子では、猩々がご機嫌に舞って海へと帰ってゆく場面を舞います。舞囃子をやらせて頂くとは恐れ多いほど全く成長しとらん私ではございますが、自信を持って自分なりに満足し、悔いが残らぬよう立派に舞いたいと思っておりますのでどうぞご覧下さい。
|
|
OG会出演独吟・経正 仁和寺にて管絃講が行われています。管絃講とは管絃を用いた法事のことです。普通の法事よりにぎやかそうでよいですね。で、誰を弔っているかというと平経正を、です。経正は平清盛の弟である経盛の息子で平敦盛の兄でもあります。琵琶の名手であり、音楽を愛した風雅な公達、経正は源氏との争いで命を落としたのです。彼を幼少の頃から寵愛していた法親王は嘆き悲しみ、管絃講を行うように命じました。用いる絃楽器は琵琶「青山」です。これは唐から伝来した名器で、一時法親王が経正に贈ったものです。しかし経正は争いの中での紛失を恐れ、「青山」を返し戦場へ向かいました。 さてその「青山」の音に魅かれて現れたのはもちろん、経正の幽霊です。現れた、といってもいるのかいないのかはっきりしない幻です。名前につね(経)という字は入っているけれど、今ははかなくつね(常)でない姿なのです、とうまいことを言っています。こうして幽霊と生きている人間が言葉をかわせるのも管絃講のおかげ、引いては仏さまのおかげなのです。また経正は幼少の頃から目をかけ、「青山」まで下さった法親王に感謝し、周囲の人々には見えないけれど、その「青山」を奏します。その調べは切々と人々の心へ届いてゆきます。しかし名残が尽きないまま修羅道(戦さをした人間が堕ちる地獄)の苦しみが再び襲ってきます。その苦しむさまを人々に見せたくないという羞恥心から暗闇を照らす灯し火に自ら飛び込んで消し、再び修羅道に帰っていったのでした。
|
|
顧問出演舞囃子・船弁慶 お能のお話のなかには、源義経さんが登場するものがたくさんあります。「鞍馬天狗」「橋弁慶」「烏帽子折」「安宅」などなど。義経さんと武蔵坊弁慶が五条橋で出会って主従の契りを結ぶ「橋弁慶」などは有名ですね。今回紹介するのは「橋」ではなく「船弁慶」。これも義経さんの登場するお話です。 平家討伐に大活躍した義経でしたが、戦が終わると兄である源頼朝にほめられるどころか疑いをかけられ、追われる身となってしまいました。義経は弁慶や従者と共に都を出て西国へ落ち行こうとし、今の兵庫県である摂津の国、尼崎大物の浦に着きます。そこへ義経を慕い彼の彼女であった静御前もついて来ます。しかし弁慶は静がこの先、自分達と同行するのはよくないと思い、静を都へ返すよう、義経に勧めます。義経はそれを了承し、弁慶は静にそのことを伝えます。静はそのことを聞き驚きます。そしてこれは弁慶の計らいであって、義経様がそんなことおっしゃるわけないわっと思いますが、義経から直接都へ返るように言われ、従わざるをえず、泣き伏します。 やがて別れの宴が行われ、静は別れを惜しみながら舞をまいます。そして船出する義経を見送り、自分も去っていったのでした。 名残惜しそうな義経でしたが、ゆっくりもしていられず、弁慶が船頭に出船を命じます。はじめはのどかな海であったのに、にわかに六甲山の辺りに黒雲がわき起こり、風も出てきて、波も立ち、船は大きく揺れてきました。と、はるか海の向こうに平家一門の亡霊が浮かび上がります。そして平知盛(平清盛の四男)が怨みをはらさんとばかりに長刀をかまえ義経に襲いかかったのです。しかし。ここはさすがの義経さん。少しも驚かず、知盛の亡霊と応戦したのです。亡霊に対しても一対一の戦いを受けて立つとは、いやはやあっぱれですね。でも相手が亡霊だから直接攻撃が効かなかったのか、どうか知りませんが、弁慶が数珠を揉んで祈祷すると、亡霊は波間に消えていったのでした。 今回はラストの知盛の亡霊が長刀を持って義経に襲いかかる場面が舞囃子になっています。それはそれは恐ろしい、でもかっこいい舞囃子を顧問の脇田晴子先生が舞ってくださいます。ぜひご覧ください。
|
|
番外仕舞・花筐狂 男大迹部皇子の皇位継承は突然のことであった。すぐさま都に上がることになった皇子は、寵愛していた照日の前に手紙と形見である花筐を届けさせた。今はこう離れ離れになったがまた必ず逢おう、とつづられた和歌を読み、花筐をひっしと胸に抱く照日の前であった。 しかし約束は果たされないまま月日は流れ(今は継体天皇となった皇子を思うあまり)照日の前は狂女になってしまう。そして雁に導かれるまま、侍女に花筐を持たせ都へやって来る。そこへ偶然にも紅葉狩りにやってきた継体天皇の一行と出会う。二人はお互いにまだ気づいていない。一目で狂女だと認識した朝臣は、照日の前と侍女を追い払おうとしてその手の花筐を打ち落としてしまう。怒り狂い、泣き伏す照日の前。その彼女に朝臣は、一行の先を清めるという狂女の舞をしろと言う。言われるがまま前漢の帝と李夫人との愛の深さを表した舞を舞った後、花筐を見せるようにと命じられ、おずおず花筐を差し出したとき、二人はお互いを認め合う。照日の前は、正気に戻り、継体天皇は彼女を召抱えると決めるのだった。 お仕舞は花筐を落とされ(照日の前が)怒り乱れる部分である。 こうして
|
|
番外仕舞・鉄輪 恋の炎が燃え上がっていた頃は永遠に変わる事なく一緒にいられると信じていたのに。男心はなんと移ろいやすく、男女の仲はなんともろいものか。 女は離縁された元夫を怨み、神罰を与えるべく毎夜神社に参詣していました。ある日、女に神託が下ります。願いをかなえたければ その頃、元夫は悪夢ばかり見ることで悩み、陰陽師の所へ相談に行きます。陰陽師は彼を一目見ただけで女の怨みをかっていることが原因であると突き止めます。さらに彼の命が今夜にも危ないことに気づき、彼と新しい妻の身代わりを作らせます。そうして祈祷を始めるとやがて女の生霊が現れます。女は身代わりを元夫と新しい妻だと思い込み、怨み言を吐きかけ、さんざんに打ちすえます。そうして、いざ命を奪おうとしたその時、陰陽師の呼んだ三十もの日本の神々が現れ、女の神通力を奪ってしまいます。あともう少しのところだったのに。女は今日のところは見逃しといてやるけど、また必ず現れてその命もらい受ける、と言い捨て消え去るのでした。 今年の番外仕舞は両方男のために狂う女が主人公です。愛の深さゆえに狂う女達の舞、どうぞご覧下さい。(舞って下さる先生方は二人も男性ですが。)
|
|
能・小鍛冶 前シテ…怪しい童子 後シテ…稲荷明神(狐霊) ワキ…三条小鍛冶宗近 ワキツレ…勅使・橘道成 アイ…宗近さんちの下人 ある時一条院は不思議な夢を見ました。宗近という刀鍛冶に剣を打たせればすばらしい剣ができる、というのです。院はさっそく臣下の橘道成を勅使として宗近の屋敷につかわします。 能は道成が宗近をたずねて来たところから始まります。一条院の命令に宗近は困ってしまいました。院の所望するような名剣を作ろうとすれば、彼に劣らない優れた腕を持つ相槌(一緒に打つ相手)が必要で、そして残念なことに彼にはその心当たりがないのです。 困った時の神頼み。宗近は己の氏神である稲荷明神に参りに行くことにします。 さて、そんな宗近を不思議な童子が呼び止めました。童子はどういうわけか事情をよく知っていて、彼に日本や中国の名剣の話を語ってきかせ、これにも劣らぬ立派な剣ができると励まします。そして、準備をして待つように言うと稲荷山の方へと消えてしまうのです。 さて、宗近が言われた通りに準備をして待っていると、現れたのはなんと氏神の稲荷明神。神様を相槌として打ち、裏表に互いの銘をも打つと、《二つ銘の剣》とも《小狐丸》とも呼ばれるすばらしい剣が出来上がります。稲荷明神は、みずから勅使の橘道成に剣を捧げると群雲に飛び乗って稲荷山へと帰って行きましたとさ。 詳しくはこちらへ ・面 ・作り物 ・装束 ・全文掲載(現代語訳付き)
|
|
附祝言・高砂 肥前阿蘇の神主である友成が、京へ行く途中、播磨の高砂の浦に立ち寄った。そこで松の掃除をしていた老夫婦に出会う。話を聞くと、高砂の松と、対岸の住吉の松は夫婦松・《相生の松》だという。そして、私たちはその松の精である、とも言う。住吉の松である翁は友成に「住吉で待つ」と言い、小船に乗って漕ぎ出して行く。友成も後を追うと、なんと住吉大社の祭神・住吉明神が現れ、勇壮な舞を見せ、天下泰平を祝福するものであった。
こちらは結婚式で有名な『高砂』です。友成さんが翁を追っていく場面のものです。おめでたい謡が多い『高砂』ですが、附祝言で謡うのは最後の部分である、住吉明神が天下泰平を祝福しているところです。 結婚式場でも目にする、翁がサラエ(熊手)、嫗が杉箒を持った人形がありますが、この組み合わせも、『高砂』の小道具として登場するのです。 これにて公演は終了となります。本日はご来場ありがとうございました。
|
|
お能でウフフ 菊は効くと聞く。 秋です。秋真っ盛り。夜になるとリリリリリ、なんて虫の音も涼やかですからつい読書にふけったり、句の一つもひねって見ようかな、なんて思ったり……ちょっと乙女チックになって本来の私の姿に戻ることができる、そんな季節ですね。 秋といえば、何を思い浮かべましょうか…そう、お花でいうなら秋の七草なんてのはどうかしら。いかがです、みなさんそらで言えるかな? なあに、春の七草なら言えるけど…だってお粥に入れるから、ってそんな事を言っていては真の文化人にはなれません。 これさえ覚えていれば秋の主要な花はおさえたも同然! とはいきませんな、しかし。それはタイトルを見たら分かっていただけますね。そうです。菊ですね、きく。菊を忘れちゃいけないな。 舞囃子『菊慈童』は、主人公が菊の精でしてね。その子は人としてこの世に生を受けたのですが、故あって山奥に追いやられ、菊の花や葉にたまった雨露をたっぷりと含んだ川の水を飲み続けているうちに、仙人になったのです。まぁ、その葉っぱには法華経普門品第二十五の二句の偈文が書かれていて、もちろんそれによる観世音菩薩のご利益もあるのですが(観音さんのご利益については第二回淡海能冊子をご覧下さいな)、菊でなくてはここまでうまくはいかなかったようです。 もともと、菊のいっぱい咲いている谷から流れでる水を飲みつづけている長寿村がある、というお話はありまして。菊は体によいもの、特に長寿になる効き目があるとされていたのですね。和名でも齢草、だとか延命草、なんて思わせぶりな名前がついてます。さてさて、そもそも菊にはほんとに薬効があるのでしょうか? 答えをあっさり言いますと、あるのです。 主な薬効は高血圧防止。肝臓の機能を調整してくれます。その他、視力回復や頭痛・関節痛の鎮静、めまい、不眠症にも効果あり。それから、白い花は髪の毛がツヤツヤになるのだそうですよ。これは、もう食べるしかないですね。もともと日本へはお薬として伝わったといいますし。 九月九日は、菊のお祭・重陽の節句です。お酒に菊の花を浮かべて飲んだり、菊に綿をかぶせて匂いを移し取り(きせわた、って言います)、その綿で体をなでて長寿を願ったり……なんだか楽しそうでしょ。この節句は一月七日七草粥、三月三日ひな祭り、五月五日端午の節句、七月七日たなばたさま、という五回シリーズの第五弾なのですが、昨今では他の四つに比べてなんとも影が薄いですね。一体どうしたことなんでしょう。 それは、暦のせいではないかしら。昔は旧暦でしたから、今とはかなり日付がずれてるのですね。今の九月九日では、菊の盛り、というのはいささか辛いのかもしれません。だって、今日(十月十五日)が旧暦では九月七日なのですよ。そうなのです、真の菊の節句は明後日に迫っているのです! さあ、菊を育てるという高尚な趣味を持たないあなた、かっぱらう菊のめぼしは付きましたか? なあに、買うですって? いやいや。殺虫剤まみれですぜ、だんな。気をつけなくっちゃ。 花は、乾燥させてお使い下さると、便利ですね、保存もききますし。でも、やっぱり生のほうが香りもよくて素敵でしょうね。調理方法としては、どんな使い方しても大丈夫みたいです。煮物、炒め物なんでもドンと来い! 妙文を記した葉も食べたい、という場合には、若葉がおすすめ。だって固くて苦そうじゃないですか、大きくなったのは。刻んでお粥にするとおいしそうですね。おなかを冷しちゃう効果もあるから気をつけなきゃいけませんけど。さぁ、来年以降に向けてさっそく育てましょう。ついでに菊人形もつくって菊ライフを堪能してくださいませ、ウフフ。
|