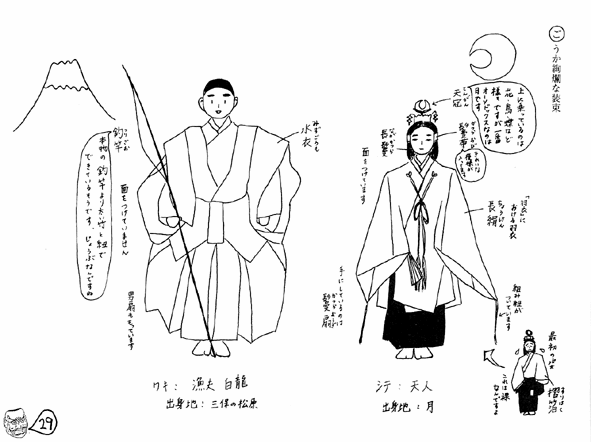
能楽「羽衣」
装束
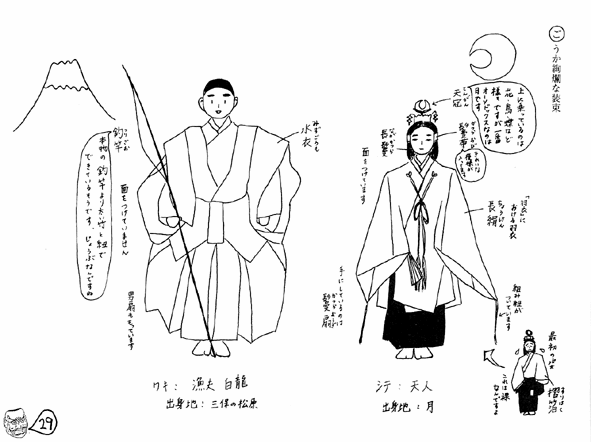
面
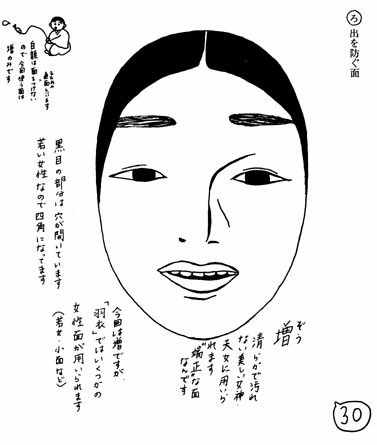
|
もとめたものはどちらだったのか 羽衣伝説は日本中、世界中に存在する。まず、羽衣をまとって地上に降りてくるのは天女である。天女が水浴びをしている間に男が羽衣を隠してしまう。天に帰れなくなった天女は仕方なく男の妻となる。やがて天女は男との間に子供をもうけるのだが、隠してあった羽衣を見つけ出し、天に帰ってしまう。大筋はこのようになっているのだが、妻ではなく老夫婦の養女となるもの、子供が数人であるもの、男もしくは子供が天女を追って天に昇ってくるもの、七夕伝説となるものなど、多種多様である。 その中で、天女と男が共に地上または天で幸せに暮す伝説は、そうできない伝説に比べてずっと少ない。また、天女以外の人外のものを妻にする伝説においても、大抵離れ離れになってしまう(例・鶴の恩返し)。人と人外のものとの婚姻は、やはりうまくいかないものなのだろう。 ところで、他の人外のものが自主的に人間の男の元へ嫁入りするのに比べ、羽衣伝説における天女は羽衣を盗まれ、仕方なく妻となっている。同じ天女であっても羽衣を持たない月の乙女の伝説では、自ら地上に降り男の元を訪れるのである。つまり羽衣が存在する時点で、持ち主である女はそれを盗られて嫁入りすることになるのである。逆に人外のものである天女が人間の男の妻になる伝説に信憑性を与えるために羽衣は存在するのではないだろうか。いずれにしても羽衣伝説の男たちは、他の人外のものを妻とする男たちと違って、先に天女にほれている。しかし子供までもうけても、天女は羽衣を見つけるとそれをまとって天に帰ってしまう。天女にとって男は故郷以上の存在になり得なかったのだ。そう考えると羽衣伝説の男たちは天女を無理やり妻にした自分勝手な人間ではなく、天女に恋焦がれてしまった哀れな人間に思える。なにしろ人外のものとの婚姻はうまくいかないのが相場なのだから。 能楽「羽衣」の白龍が求めたのは天女ではなく羽衣であった。そこでもう他の羽衣伝説の男たちと白龍は全く別物になっているのだ。そうして性の生々しさは消失し、人々が能楽に求める清浄さ、美しさ、可憐さのみが残り、能楽「羽衣」は今日まで最も能らしい能として愛され続けることになったのではないかと思う。 |
|
*1 佛菩薩が出現する前触れ。皆さんもこんな状況に出会ったら心して下さい。 |
*1 お釈迦様がお亡くなりになり、その教えも変わってしまった嘆かわしい世の中。悲観的ですね。 *2 魚を捕まえることを生業とするのは賤しい、という仏教思想が根づいているようです。 |
*1 天上界に対して下界とは人間界のこと。別に人間しか住んでない訳でもないのですけれど。 *2 天人が命を落とす時に現れるという五つの兆候。衣が汚れ、花の髪飾りがしおれ、脇から汗が出、悪臭を放ち、楽しくなくなってしまうらしい。 *3 丹後風土記の天人さんの歌より。この天人さんは、下界の住人となって共に暮らした人間に追い出された時、この歌を歌いました。悲しい歌です。 *4 極楽浄土に住む、頭は人間の少女、体は鳥という生き物。声の美しさは天下一品。 |
*1 天人は嘘をつかないのが定番。 |
*1 東西南北と乾艮坤巽、そして上下を合わせて十方とする。これであらゆる世界、という意味。 *2 月では、毎月一日から白衣の天人が一人ずつ宮殿に入り、それに伴って黒衣の天人が一人ずつ出て行く。十五日には白衣の天人のみとなり、満月になる。その後、黒衣の天人と入れ替わるにつれて月は欠けていくらしい。 |
*1 いつの間にやら夕方に?さっきまで朝だったのに。何時間も舞っていた? 謎。 *2 仏教で、世界の中心、しかも海中にあると考えられた高山。富士山もこの名前で呼ばれることがあったそうです。 |
*1 南無は強い信仰心を表す梵語、帰命は身も心も仏に帰依すること。月天子とは月宮殿に住む天王。本地は本源。大勢至は阿弥陀如来の横で衆生教化を助ける勢至菩薩のこと。つまり、「本当の姿は勢至菩薩である月の天子様を私は心から尊敬し、信じているのです」、ということかな。 *2 天人は、体の色が月の色の様に美しいとされ、色人と呼ばれることもあったそうです。 |