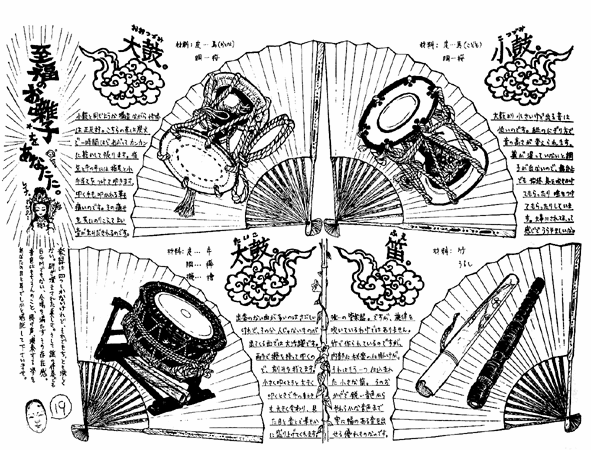
<一期生 R.M>
■第五回 淡海能■
|
平成十二年十月十日(火)正午始
連吟 鶴亀 素謡 竹生島 仕舞 鞍馬天狗 舞囃子 敦盛 班女 杜若 OG会出演仕舞 三輪 屋島 花筐 富士太鼓 山姥 舞囃子 巻絹 小袖曽我 融 招待校出演 佛教大学能楽部 京都橘女子大学能楽部 番外仕舞 通小町 鉄輪 能楽 羽衣 附祝言 終了予定 十六時二十五分頃
|
|
学長挨拶 羽衣 滋賀県立大学学長 日高敏隆 かつて、ある国際学会で能の夕べをやってもらったことがある。日本の京都で開かれる国際会議だからぜひ能を見たい、という外国人からの手紙をいくつも受け取っていたからである。 お願いした能楽師の方は、外国人が多いでしょうから「羽衣」にしましょう、あれは舞が派手で、謡が少ないですからね、親切におっしゃってくれた。 けれど、申し訳ないがぼくは不満だった。当時ぼくは、この「淡海能第一号にも書いたとおり、能が謡の言語にほとんど完全に依存した舞台芸術であるという研究をしていたからである。 ぼくは予めその能楽師の人に、見にきた人全員にイヤホーンを渡し、謡の英訳を流して聞かせてもいいですかとお伺いをたて、英訳ならいいですよ、というお許しを得ていた。だからできるだけ謡が多く、筋が複雑な曲の方がいいと思っていたのである。 しかし、「羽衣」は美しい。観客は外国人も日本人もみな舞に見とれていた。イヤホーンから流れる英訳の謡を聞きながら。 「羽衣がないと天へ帰れません。ぜひ返して下さい。」「いや、返せない。」というような謡の内容は、英訳圏でない国の人々にも容易に理解できたのだろう。皆、満足そうな顔つきで、能を楽しんでいた。 能が終わったあと、近くのホテルで、能を舞ってくれた人たちとの交流会を開いた。美しい羽衣をまとった若い天女を舞ったのが、いい年の男であったことに、外国人たちは一様に驚いていた。いろいろな質問も出たが、能と謡のことについては、さすがに何の質問も出なかった。要するに、耳から入ってくる英訳の謡によって、「羽衣」という能がよく理解でき、十分に能を楽しめたのだとぼくは理解した。妙なことを研究しておいて本当に良かったとぼくは思った。 翌日、「英訳聞いて能わかったよ」という見出しで、この催しの記事が新聞にも大きく載った。ぼくは何となく誇らしい気持ちになった、外国人だけでなく、日本人にもよくわかったということが書いてあったからである。 能の謡の英訳を流したりすることは、今ではもうあまり珍しくないらしい。けれどこの国際学会のあった今から10年前、それは全く新しい試みであったようである。 |
|
顧問挨拶 初心忘るべからず 滋賀県立大学能楽部顧問 脇田 晴子 能楽部のT.Y君のヤイノヤイノの催促をものともせず、私はこの夏休み、十年来の懸案である中世被差別民の著書を必死になって書いていた。四百字八五〇枚、今日のお昼、宅急便で送って、ヤレヤレとホッとして、今はゆっくりとした気分でこの小文を書いている。 能楽の大成者、観阿弥・世阿弥の親子、現在の能楽五流のうち、その四流は大和四座といわれる人々、その他のもろもろの当時、猿楽者と言われた人たちは、声聞師(散所非人)といわれる被差別集落の出身であった。将軍足利義満の寵愛を得て、猿楽、ひいては大和四座の隆盛を招いた世阿弥は、はっきり、「大和猿楽児童、これ観世と称する猿楽法師の子なり(中略)かくの如き散楽者は乞食の所行なり」(後愚昧記)といわれている。 しかし、そんな公卿貴族の非難をよそに、日本の伝統芸能といわれるものは、能楽・狂言をはじめ大部分、猿楽師が所属した声聞師集落に育まれて成長したのである。文楽人形浄瑠璃しかり、歌舞伎の源流であるお国も、「あるき巫女」と称する以上、どこかの声聞師集落出身であろう。その他、現行能楽にもある。放下や放下僧もそうである。かれらは「自然居士」を始祖と仰いだのである。 百万もそうである。百万は鎌倉時代末期、曲舞という白拍子舞からでて、たいへん流行った芸能の名人として名高い女芸人である。有名な話であるが、観阿弥は、この百万の流儀を伝えた乙鶴賀歌女から曲舞を習い、その曲舞のふしを少し大和猿楽流になめらかにして、能楽の「クセ」に入れて成功したのだと、世阿弥は書いている。観阿弥はその追憶からか、百万を主人公にした「嵯峨の女物狂の能」を得意としたが、それを世阿弥が改作したのが、現行曲「百万」である。「百万」は病人など重症の乞食が乗った「土車」を引くところを演じ、功徳作善を行うことを勧め、百万遍念仏の音頭をとるところを演じる。まさに宗教性を帯びた声聞師の女芸人の芸能なのである。 「曽我物語」は瞽女が語る芸能だといわれているが、能楽「望月」では、我が子とともに亡夫の敵討をする妻は、瞽女に扮して曽我物語を語る。能楽「鳥追舟」では、江戸時代の門付けの女芸人の風俗であり、阿波踊りの女の装束である鳥追女のもとの原型を示している。 以上のように、能楽は中世の被差別民が育んだものであり、被差別民の生き生きとした動態を今に伝えているのである。そして、村々町々の鎮守の社寺で庶民の喝采を浴びたものなのだ。現在は貴族趣味などといわれる能楽であるが、初期の猿楽能が持った活気を現在に活かして欲しいと思う。それには能楽部の皆さんの活躍が大きく貢献すると思うのである。世阿弥も「初心忘るべからず」といっているではありませんか。 |
|
連吟・鶴亀 これは昔の中国のお話。 年の初め、皇帝の宮殿の一つである「月宮殿」に臣下たちが集まってきます。その数は一億人にもなろうかというもの。不老門の前で一同に新年の挨拶をすると、その声は天に響くようでもあります。 さて、月宮殿の様子は華美を極めたものです。庭には金銀の珠を散りばめてあるので、光り輝いています。部屋の方に目を移せば、織りを重ねた錦の布団が敷いてあり、瑠璃でできた扉もあります。七宝の一つである美しい二枚貝・しゃこうを埋ずめた渡り廊下に続くのは、メノウでできた橋。池の汀には鶴が舞い、亀が遊んでいます。まるで、仙人たちが住むという桃源郷・蓬莱山のようではありませんか。皇帝の治世の良さが伺えようというものです。 七宝とは読んで字の如く、七つの宝玉のことです。金・銀・瑠璃・玻璃・しゃこう・瑪瑙・珊瑚の七つです。また、真珠を加えるときもあります。 金・銀・真珠についての説明は入らないでしょう。今でも貴金属の代表ですね。瑠璃は西洋ではラピス・ラズリ。魔力を持つとされる青い宝石です。青ガラスも瑠璃と呼ばれることがあります。玻璃は透明な水晶。透明ガラスを玻璃と呼ぶことがあるのは、瑠璃と同じですね。瑪瑙はメノウ、珊瑚はサンゴ。「しゃこう」というのはオオギガイという二枚貝のことです。アコヤ貝のように内側に光沢があり、真珠を生成することがあるようです。 これだけのものを惜しげもなく庭や館に散りばめるというとは、やはり中国のスケールは大きいのですねぇ。
|
|
素謡・竹生島 私たち滋賀県立大生にとっては、ご当地ソングとなるこの「竹生島」。最初に登場するのは、天皇に仕える朝臣(ワキ)。彼は霊験あらたかな竹生島に参詣するためお暇をもらい琵琶湖までやってまいりました。さて湖畔まで着きましたが、竹生島に渡るには当然船が必要です。と、丁度よいタイミングで船が通りかかったではありませんか。これはラッキーと朝臣は船に乗っていた老翁(前シテ)と海女(前ツレ)に竹生島まで乗せてくれるように頼みます。 船に乗せてもらって竹生島に着くと、実は海女は弁才天(後ツレ)であり、また老翁も龍神(後シテ)だったのです。朝臣はビックリするも二人の神様の豪華な祝福を受け、また国土を護ることを約束してもらいました。めでたし、めでたし。というお話です。 自分は校外学習の折、実際に漁船に乗せてもらって竹生島に行ったことがあります。島についてまず目に入ったのが、島の上へと続く長い階段でした。かなり急な階段が続き、その途中途中にお社が建っているというかんじでした。階段を上がり、時折下の方を見ますと、さすがに神様の住んでいるところだけあって、すばらしい景色でした(急な階段を上から見ると少し怖さをおぼえますが)。竹生島といえば、日本三大弁才天の一つが祀られているのは有名ですが、行った時は丁度、観光客も来ない時期らしく神主さんも不在だったようで、弁才天様を見ることができず、謡の内容にあるような、すばらしい体験はできなかったのが残念でした。漁船をチャーターしたまでは良かったのですけど……。日ごろの行いでも悪かったのでしょうかね? とにかく弁才天様に会うために、もう一度竹生島に渡りたいものです。
|
|
仕舞・鞍馬天狗 ワシは鞍馬山に住む大天狗じゃ。大天狗というのは、天狗の中の天狗。すなわち、日本中の天狗を統べる立場にあるのじゃな。 あれは今から九百年も前のことになろうかの。春の陽気に誘われて、鞍馬の西谷へ花見に行ったときじゃった。あの頃の鞍馬寺には平家の稚児が多くての。ワシが化けた山伏と一緒では花見の興がそがれる、と言って寺へ帰ってしもうた。 と、そこへ一人の少年が残っておった。彼こそ紗那王、のちの源義経じゃった。紗那王殿はワシと花見をしようと残ってくれたのじゃ。聞けば、寺では平家の稚児の威勢が強く、肩身が狭いと言うではないか。ワシは正体を明かし、兵法を教えることにした。いつの日か父上の敵がとれるようにな。 紗那王殿の上達ぶりは目を見張るものがあった。数々の奥義を覚え、木葉天狗ならば軽くあしらえるほどにまでなった。さすがに武芸才略の道に通じる家柄である、と感心したものじゃ。この時、人ならぬ身であるワシには、彼が平家を滅ぼすであろうことがわかった。もう教えることは何もない、これからは影から紗那王殿を守ろう、と申すと、袂にすがってお引き留めになる。名残惜しいことじゃが、もはやこれまで。梢に翔って、鞍馬の山へ立ち帰ったのじゃ。
|
|
舞囃子・敦盛 平家物語。この物語の中には、栄華を極めた者の行く末を如実に物語っている。おごり高ぶっていた平家の滅亡を表しながらも、そこに描かれた物語は我々に、世の無常や戦の悲惨さを教えてくれる。 寿永三年(一一八四)。一の谷において一人の武将が馬に乗り戦場を駆け抜けていた。彼の名は熊谷次郎直実。平治の乱において源家十七騎の一人に数えられ、また頼朝に「日本一の剛の者」と称えられたほどの武将である。一の谷の合戦において源氏軍は平家軍を打ち破り、平家軍は海上に退却を始めていた。直実はもはや勝敗の決した戦場で、さらに武勲をあげるために、駆け巡っていたのである。 波打ち際で彼は一人の若者を見つける。どうやら、船に乗り遅れてしまったらしい。しかし、なおも退路を探そうとするその武者に、直実は大声をあげ一騎打ちを申し込み馬を走らせた。一騎打ちを申し込まれた武者は、急な出来事に初めは戸惑ってみえたが、意を決したように同じく馬を直実の方に走らせてくる。二人は、しばし波打ち際で太刀を交えたが、「日本一の剛の者」と呼ばれる直実に、その武者がかなうはずもなく、馬から落とされ、直実に組み敷かれてしまった。直実にとってはいつものことだった。このまま討ち取り武勲をあげる……。しかし、打ち合っている時には気が付かなかったが、兜の下に見えるその武者の顔はあまりに若かったのだ。直実は戸惑った。年のころ十六・七のこの青年を手にかけることに。彼はこの青年を見逃そうと考えた。しかし、集まりくる仲間の手前、敵方の武者を逃すことはできない。 結局、直実はその若武者を自分の手で討ち取ったのである。青年の名は平敦盛。笛の名手として知られていた。直実は、この事を境に出家し蓮生法師となった。そして今、敦盛の菩提を弔う蓮生の前に、敦盛の霊が姿を現す……。
|
|
舞囃子・班女 ここは、美濃国野上(現:岐阜県不破郡関ヶ原野上)の里です。そこのある宿の長が、怒っていました。 「おい、花子よ。客に逢いなさい。吉田の少将と契ってからは形見に取り交わした扇に眺め入ってばかりでなにもしなくなってしまった。もう出ていっておくれ」 花子はよろよろと扇を持ち、その宿から出ていきました。 それから、東国より都に帰る吉田の少将が従者を連れてその宿場にやってきました。 「花子という女がここにいるはずだ。尋ねてきておくれ」 「畏まりました。……どうやら花子は宿の長に追い出されてどこかに行ってしまったそうです」 「そうか、残念だ」 そうして、都に着いた少将たちは、加茂の社(現:下鴨神社)に参詣すると、狂女が神に祈願を捧げていました。 すると、従者がおもしろがって、その女に声をかけました。 「狂女よ、狂ってみろ」 「無情なことを言わないでください」 「その班女の扇はどうしたのか」 「形見の扇です。私は秋の扇のように漢の成帝に捨てられた班女と同じです」 そして、ついには狂おしく舞います。それを見ていた少将はその扇に気づきます。 「その扇をよく見せて下さい」 「これは人に見せるものではないのです」 「私にも形見の扇があるのです」 そして、二人は互いに扇を眺めて、その狂女が花子であることがわかり、少将は花子と夫婦の契りを結びました。 私が舞うのは、形見の扇を持ち、狂おしく舞っているところです。扇にも愛を込めて舞っているでしょう。
|
|
舞囃子・杜若 ここは三河の国、八橋。沢辺に杜若がたくさん咲いています。都から東国へ旅に出た僧は、このさわやかな紫色の杜若にひかれて、ひと休みしていました。すると、一人の女性が声をかけてきました。 「この八橋は古歌にも詠まれたほどの杜若の名所。その古歌とは在原業平の からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ という、『か・き・つ・ば・た』の五文字を一句一句の頭に置いたみごとな歌でした。業平は都に愛する人を残して東国へと旅に出ました。その人をなつかしんで、この歌を詠んだのです」 さらに彼女は続けます。 「業平は実は歌舞の菩薩の生まれ変わりだったのです。そして、たくさんの女性と契りを交わしたのは、女性たちを成仏させるためだったのです。また、彼の詠んだ和歌のおかげで、私のような非情の草木も成仏できるのです」 実は彼女は杜若の精なのでした。彼女は正体を明かし、さわやかに美しく舞って、夜の明けるころ、消えていったのでした。 さて『杜若』の舞台である八橋に五月に行って来ました。ちょうど杜若が咲き始めた頃で、紫色の花と青々とした葉がとてもさわやかでした、その風景を思い浮かべて、今日は舞いたいと思います。
|
|
OG出演仕舞・三輪 三輪山の玄賓僧都の庵へ、毎日 一方、里の男が、三輪明神に参詣すると御神木の杉の枝に、僧都の衣が掛かっているので、知らせに行きます。僧都が見ると、その木の裾に一首の歌が書いてあります。 それを読んでいると、女姿の三輪明神が現れ、私は迷い深い人間の心を持つので、その罪を助けて欲しいと言い、三輪の妻問いの神話を、天照大神の岩戸隠れの物語を語り、神楽を奏し、夜明けと共に消えていきます。
|
|
OG出演仕舞・屋島 ある僧が、讃岐国へやって来ました。讃岐と言えばうどん! ですね。僧はとりあえず今日はどこかに泊まりたいと思い、屋島の塩屋に泊めてもらうことにしました。塩屋の漁翁に、屋島と言えば源平合戦ということで、その話を聞いてみると、やけに詳しく説明してくれます。まるで見てきたかのごとく。僧が不審に思って、名を尋ねると、明け方に名乗ろうと言って消え失せました。なんてあやしい人でしょう。そこで僧は地元の人に尋ねてみると、それは源義経の霊ではないか、と言われます。 その夜、僧が寝ていると、夢の中に立派な義経の霊が現れ、言いました。 「私はまだこの地に執心が残っている」 そう言って、自分が合戦で活躍したときの様子を再現し、修羅道でも闘争しているのだ、と言って消えていったのでした。
|
|
OG出演仕舞・花筐 越前国にいた 季節は秋。天皇となった皇子は紅葉を見に出掛けた。そこに彼を慕うばかりに狂女となった照日ノ前もやって来た。しかし、大事な花筐を官人に打ち落とされてしまう。悲しむ照日ノ前に官人が、それは誰の花筐かと尋ねると、今は天皇となられた大跡部ノ皇子のものだと答えた。そこで天皇ご自身が花筐をご覧になると、確かに自分が照日ノ前に残してきたものなので、本人だということがわかり、再び一緒に暮らすようになったのだった。
|
|
OG出演仕舞・富士太鼓 「富士のゆかりの者が来たら、知らせよ」 萩原院の臣下が、従者に命じています。 そのわけは、管弦の催が行われた時、浅間という太鼓の名人が召されましたが、富士という男がその役を望んで上洛します。そのことを聞かれた院は、浅間の腕が上だと判定なされます。浅間は富士の差し出た態度を憎み、討ってしまいました。 一方、富士の妻は、夢見が気になり、子供を連れて都へ向かいます。そして臣下に会い、富士が討たれたと聞かされ、形見の舞衣裳を渡されます。そして心慰めにとその衣裳を着、太鼓こそが夫の敵だと叫び、子供にも父の敵だと言い、打たせます。 すると、亡き夫の霊が妻に憑き、狂女となり、恨みの太鼓を打ち、舞楽を舞います。そのうちに、乱れ心も収まった妻は、衣裳を脱ぎ捨てて帰っていきます。
|
|
OG出演仕舞・山姥 昔、都で「山姥の曲舞」が流行っていました。その中でも特に名手とうたわれたのが遊女「百萬山姥」でした。彼女はある日、お供をつれて善光寺詣の旅に出たのですが、途中で道に迷ってしまいました。困っているところ、その土地に住むという女が宿を貸してくれることになりました。ほっと一息つき、遊女が自分は都で有名な「百萬山姥」だと言いますと、女は「本当の山姥を知らないのに、山姥の曲舞を舞うとはなんたることか。そのことを注意しに来たのですよ」と言い、夜になったら正体を見せてあげましょうと言って、消えてしまう。さて、夜になると女は正体を現し、山姥となって遊女の前に現れ、山姥の山巡りを見せると、再び姿を消してしまうのでした。
|
|
舞囃子・巻絹
そこへ巫女が現れた。そして勅使に縄を解けと言う。「私に和歌を手向けた者ゆえ縄を解いてやれ」と。天神様が乗り移っておられたのだ。私のような下賎の者が歌を詠んだということを疑い、勅使は縄を解くことを渋ったが、私に上の句を言わせ、御自ら下の句を続けてそのことを証明して下さった。 音無にかつ咲き初むる梅の花匂はざりせば誰か知るべき そして私の縄を解き、和歌の功徳について語りはじめた。和歌は日本の神々にとって、仏の真言にあたるもの、つまり神に最も届きやすい言葉の形ということなのだ。和歌を聞くと神はあらゆる苦悩・苦痛から一時解放されるという。僅か三十一文字に真理を込められる和歌にはそういう、力がある。 神様にお帰りいただけるよう、巫女が祝詞をあげはじめると、神様が更に強く憑いたと見えて、巫女の動き、語りはさらに神懸かってきた。有り難いような、それでいて正直、少し恐ろしいような。ゆっくりと始められた舞は次第に早くなる。三熊野におわします神々佛仏のことを語りながら、御幣を激しく打ち振るい、空を駆けまた地上に踊り、数珠を揉んだり袖を振ったり。そして様々に舞い尽くして神様は、つ、と巫女の体を離れ、おあがりになられたのである。 さあ、今日は神様の憑いた巫女が舞い、語る様を特別、みなさまにも再現してお見せする趣向である。では、どうぞ!
|
|
舞囃子・小袖曽我 仇討ち・敵討ちは数あれど、江戸庶民に広く知られた仇討ちが三つありました。日本三大仇討ち――寛永十一年(一六三四)の荒木又右衛門の助太刀で有名な「伊賀上野鍵屋の辻の仇討ち」。元禄十六年(一七〇三)には『忠臣蔵』として知られる赤穂四十七士の「吉良邸討ち入り」。そして、建久四年(一一九三)五月、「曽我兄弟の仇討ち」が起こりました。ちなみにその前年、建久三年(一一九二)といえば、源頼朝が征夷大将軍となり、鎌倉に幕府を開いた年。兄弟の仇・工藤祐経は幕府の重臣だったのです。 この日、十郎祐成は母の元を訪ねていました。理由は、弟である五郎時致の勘当を解いてもらうこと、共に父の仇討ちをするのを赦してもらうこと……。 兄弟が幼い頃、父は所領争いに巻き込まれ、工藤祐経によって殺されてしまいます。五郎は箱根権現に預けられて僧侶となるはずでしたが、兄の十郎祐成と共に父の仇を討つため、母に黙って元服し時致と名乗ります。しかし時致はそのために母に勘当されてしまったのです。 「例え時致が出家していたとしても、世間は求道のための出家とは思いますまい。むしろ、敵を恐れてのことだと思うに違いありませぬ。ならば勘当を解き仇討ちを認めてこそ、母というものではございませぬか」 母はこれを聞くと不孝も勘当も赦す、と泣きながらに言います。兄弟も感涙に堪えず二人で舞を始め、別れの言葉を残して仇の待つ富士野の狩場に向かうのでした。 このとき祐成が二十歳、時致は十九歳。一方、本日この時点での自分は十九歳。時致と同じ年齢なのです。兄弟はこのように舞っていたのか、と思っていただけるでしょうか?
|
|
舞囃子・融 私は、東国より来た僧で京の都、六条河原院と呼ばれる辺りに着きました。月が出る頃、海浜が近くにあるわけでもないのに塩汲みの尉が現れました。不思議に思い色々尋ねてみると河原院のいわれ、当時の 不思議なことに尉は消え去りました。……まだ何かが起こるのを期待して少し眠ることにしましょう。 月の光が河原院にさし込む頃、そこに旅の僧がいた。僧が色々と尋ねるので語り聞かせた。「ここ六条河原院は融の大臣が 話題を変えるその好意に甘えて語ろう。「この辺りの景色は名所ばかりで、あれは音羽山・逢坂の関・稲荷山……」 語り終えた尉は、袖を濡らし、塩を汲むと、水煙に紛れて消え去りました。 月に照らされ、若く気品のある青年が現れます。自分が融だと語り月を愛で華麗な遊舞を見せます。月が傾き、鳥の声、鐘の音が聞こえてくると名残惜しみながら消え去りました。
|
|
番外仕舞・通小町 夏の間、山で修業をしている僧のもとへ、毎日木の実などを持ってきてくれる女の人がいました。今日こそはと思い、僧は名を尋ねました。すると彼女は「名前は言えないが、私は市原野に住んでいる。どうか私を弔って下さい」と言って姿を消しました。僧はピンときました。市原野は昔、小野小町が住んでいた所。今のは小町の霊に違いない。僧は早速市原野へ向かいました。 弔いを始めると、小町の霊が現れました。彼女は弔いを感謝します。しかしそこへもう一人の霊がやってきて、小町の成仏を妨げようとしたのです。私を置いて行くつもりなのか、と。その霊は深草少将なのでした。二人で成仏すればよいのに、少将は小町の成仏を引き止めようとするだけです。そこで僧は少将に百夜通いの様を見せるように説きます。 少将は語り、再現していきます。小町に「私に逢いたいのなら、百夜通ってきなさい」と言われ、通っていった日々のことを。車や馬で行っては人目につくから、と歩いて通っていったのです。雨の日も、雪の日も。そしてついに百日目の夜となりました。さあ小町との祝儀の酒をどうしようか、やはり仏の戒めは守るべきであろう。と、その一瞬、仏の教えを思ったことにより、少将と小町は成仏できたのでした。
|
|
番外仕舞・鉄輪 ある女が、自分を捨て、新しく妻を迎えた夫を恨み、今日も貴船の社に行き願をかけています。すると社人が「頭に鉄輪をいただき、その三本の足に火を灯し、顔に丹を塗り赤い着物を着て、怒る心を持てばたちまち鬼となって願いが叶う」と言われます。女はそんなのは人違いだと言う間にも、顔色が変じ、つれない人に思い知らそうと走り去ります。 一方、夫は悪い夢見が続くので陰陽師の安倍清明のもとを訪れ、事情を述べて占ってもらいます。すると女の恨みで今夜にも命が尽きると言われたので、祈祷を願います。清明は祭壇を調え、男と新しい妻の すると鬼となった女の霊が現れ、夫の心変わりを責め、後妻の髪をつかんで激しく打ちすえますが、夫を守護する神々に責められ、神通力を失い、心を残しながらも退散していきます。 このお話に出てくる神社参りは、古くから日本にある民俗信仰の丑刻参のことです。丑の刻(午前二時)に呪いのわら人形を境内の杉に打ち付けて、憎い憎いと念じながら五寸釘に木槌をふるうのです。ここまで人をかりたてるほどの恨みとは大変恐ろしいものですねぇ。
|
|
能楽・羽衣 はじめに簡単なあらすじ 昔々、駿河の国に白龍という漁師が住んでいました。ある日、白龍はいつもと同じように三保の松原へ釣りに出かけました。浦に着いた白龍が景色を眺めていると、とても不思議な雰囲気の中、松の木に美しい衣がかかっているのを見つけました。近づいて手にとってみると素晴らしい衣だったので、白龍は持って帰って家宝にすることにしました。 するとそこへ見たこともない女性が現れて、その衣を返して欲しいと言うではありませんか。白龍が返そうとしないので女性は自分が天女であることを明かし、その衣を人間が持っていてはいけないと言うのです。しかし、それを聞いた白龍はますます衣を返そうとはしませんでした。 天女は衣がないと天に帰れないので、たいそう悲しみました。それを見た白龍は、心根の優しい男だったので、衣を返すことにします。ですがその代わりに、有名な天女の舞を見たいと言いました。天女は喜んで舞うことを約束します。すぐ天に帰られては困るので、衣は舞の後に返す、と言う白龍に天女は、天に偽りは存在しない、と言い返しました。白龍は自分の言葉を恥じ、すぐに衣を返しました。 天女は受け取った衣をまとい、舞い始めました。月での生活、三保の松原の美しさを謡い、この国がいつまでも栄えるようにと宝を降らせます。それはまるで夢の中にいるような美しい舞でした。すっかり夢見心地になった白龍を残して、天女は天へ天へと昇っていき、いつしか姿を消したのでした。 ポイント いつ…三月 どこで…駿河国三保松原 だれが…天人 どうした…漁師白龍に羽衣を取られた けど返してもらえた 詳しくはこちらへ ・装束 ・面 ・考察 ・全文掲載(現代語訳付き)
|
|
附祝言・高砂 「高砂」というのは結婚式でも謡われるおめでたいものです。とはいえ最近の結婚式ではどうなのでしょうか。謡ってもらっても若い人にはわからんのでしょう。いや、自分も若いのですが……。 とにもかくにもこのお話の中に出てくるのは二本の松でございます。当然のごとくただの二本の松じゃございません。一方は高砂(兵庫)の地にあり、もう一方は住吉(大阪)の地にある松なのでございます。そして重要なのが、この二本の松はお互い別々の地にあるにも関わらず、夫婦の松であるというところです。離れていても愛し合う。おお、これはまさしく単身赴任のお父さんがいる家族のようでございますな! または遠距離恋愛している恋人の心境! いくら二人の間に距離があろうが、ボクたちの愛の距離はゼロなのサ!こういう謡を結婚式で謡わないでいつ謡うのですか! また、この謡曲は、夫婦の事だけに言及しているのではございません。高砂の松は万葉集。住吉の松は古今和歌集に例えられ、その松の葉が生茂ることは、二つの歌集の言の葉の栄を意味するのです。つまりは天下泰平を意味することになるのです。愛と平和の物語。ラブ・アンド・ピースな謡曲。それが『高砂』なのです。
|
|
あなたのウフフが帰ってまいりました お能でウフフ 神懸りの正体を求めて。……三千里…もいってない 梅の和歌を手向けた者を助けんと、神が巫女に憑き神楽を舞う『巻絹』。憑いたのは一体誰? 「まづまづ音無の天神へ参らばやと思ひ候。」と謡われる、その「音無の天神」。種々の謡曲解説にあたるも祭神としての明記はなく、音無天神は熊野本宮の近くにあり明治二二年の洪水で流された、とあれば詳しい方。天神と言えば通り相場は菅原道真、書くまでもない通念と思ってのことか。されど天神が道真固有の神号でない以上、明記されねば気に懸かるは、これ人情。〈音無の神〉なる神が存在するのか。地名を冠した社名なのか。懸念を抱えていては美容に悪いことこの上ない。調べに調べ、書庫での遍歴の果てに漸う〈音無天神〉、その実存の証となる資料を発見。あわせて祭神も判明。……その名はなんと、少彦名尊。しばし呆然。神楽は女神、男神なら神舞との思い込み、崩れる。巫女ゆえ女体扱いなのか。それはさておき、兄を助け国造りをした大国主の弟が何故? 『巻絹』の山場は神懸りの巫女の舞。それは、和歌の徳あってこその幸甚。真に似つかわしいのは和歌の神。それとも。少彦名は私の知らぬ他の顔を持つのか? ……持っていた。少彦名の別なる顔、それは酒の神。昔々、酒は薬であった。医者の〝医〟の字、もとは〝醫〟と書いたが、下半分には酒を表す〝酉〟が付いている。そしてそのさらに昔。病気の治療が巫女・御巫に任されていた頃の〝醫〟の字は〝酉〟ではなく〝巫〟であったとか。酒と巫女とが意外にもこうして近づきを見せる。また少彦名には芸能の神の顔もあった。名は体を表すという。少彦名は体がとても小さい。昔、芸能をしていた人々も小さかった。ゆえに祖先神として崇められていた。世阿弥によれば能楽の始祖である秦河勝も小さな壷から生まれたとか。こうして「舞う」ことにも、近づく。されど、釈然とはせず芬々とする附会臭。和歌には少彦名、一向に関わる気配を見せぬ。 和歌の神として有名な神の名を挙げよう。素戔鳴尊。住吉明神。衣通姫。菅原道真。……あ。そうか。〈音無天神〉の実在に、ものの見事に騙された。迂回。だが、一旦そうと判れば明快至極。 梅好きとして知られる道真。彼と梅の花を結ぶ逸話は枚挙に暇がない。その筆頭がこれ。 東風吹かばにほひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ そして飛び梅、梅ヶ枝餅。梅の和歌を手向けられるに相応しく、また手向けられてうれしがりそうな御仁。彼の社には梅は欠かせない。多才な道真が和歌の面で特に神と崇められる訳はおそらくこれ。 うつくしや紅の色なる梅の花あこが顔にもつけたくぞある 愛らしい。私がつけたい。……まだ、あこ(阿呼)という幼名の頃、数えで五歳の彼が初めて詠んだ和歌である。今でいえば三歳の作。ついでに、初の漢詩は十一歳の時の作。題は「月夜見梅花」。 月耀如晴雪 / 梅花似照星 / 可憐金鏡転 / 庭上玉房馨 本宮近く、音無の里に彼を祀る天神社が存在していたことも確認。これで確信。巫女に憑いたのは、音無の里に建つ天神社、すなわち音無の天神の祭神・菅丞相であった。「の」の有無で大いに異なるを特筆しておくのは、騙された身としての義務。 斯くの如く結論を出した後、謡曲の本文を読み返してみた私の目に入ったのは「南無天満天神。心中の願ひを叶えて賜はり候へ」との祈りの言の葉。天神に天満が付けば道真固有の神号。あゝ、不覚。祈らぬ私の言の葉は叶えられようはずもない。だが、お陰で少彦名とも近づきになれた。ただ一つ付け加えておく。社が隣接していたり、合祀されていたり、という可能性もある。そのあたりは次の課題。ともかく、結果のみならず過程をも重視すべきだ、人生は。だが閃けども闇雲に走らず、暫し冷静になり再考するだけの心の余裕も必要。それを説いて締めさせて頂く前に蛇足だが。菅公自ら舞う能がひとつある(『来殿』)。そこでは舞うのは公家としての性格を重視して早舞である。『巻絹』では舞う主体は巫女、神ではない。憑いた神の立場は付けたりとしての神楽なのか。ウフフ。
|