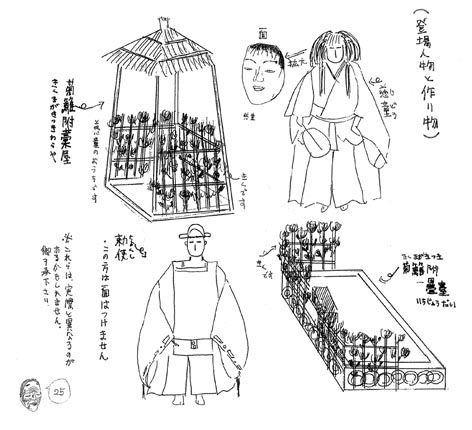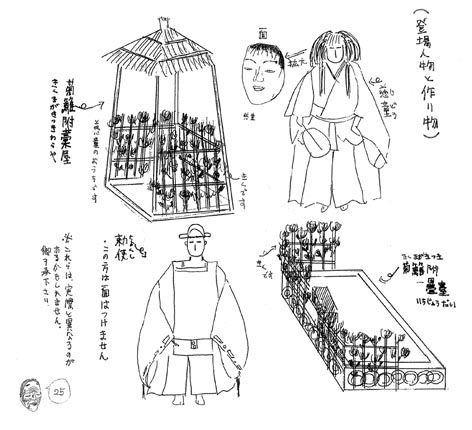| ワキ |
これハ不思議の言ひ事かな。眞しからず周の代ハ。既に數代のそのかみにて。王位もその數移り来ぬ
|
勅使 |
なんと不思議なことを言っている。周の代はすでに大昔のことだ*1。帝王の位も多数移っているのだぞ。 |
| シテ |
不思議や我ハそのまゝにて。昨日や今日と思ひしに。次第に變るそのかみとハ。さて穆王の位ハ如何に |
慈童 |
不思議です。私はそのまま何も変わっていないので、昨日や今日のことだと思っていました。どんどんと王位も変わっているのですね。それならば穆王の位はどうなったのですか。 |
| ワキ |
今魏の文帝前後の間。七百年に及びたり注1。非想非々想注2ハ知らず人間に於いて。今まで生ける者あらじ。いかさま化生の者やらんと。身の怪しめをぞなしにける |
勅使 |
今は魏の文帝の御世で、周の穆王からは、七百年間もたっている。非想非々想天にいるものならわからないが、人間世界では今まで生きているものなどいない。いかにも怪しき化け物ではないか。その身は、とても不審であるぞ。 |
| シテ |
いやなほも其方をこそ。化生の者とハ申すべけれ。忝くも帝の御枕に。二句の偈を書き添へ賜はりたり。立ち寄り枕を御覧ぜよ |
慈童 |
やはりあなたこそ、怪しき化け物ではないのですか。私は穆王より二句の偈*2を書かれた枕を有難くも頂きました。そのようにお疑いになるのならば、立ち寄ってその枕をご覧下さい。 |