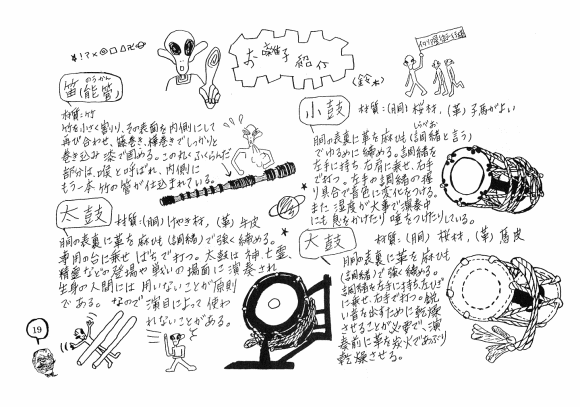
<八期生 A.S>
■第八回 淡海能■
|
学長挨拶 彦根城博物館 能舞台 滋賀県立大学学長 西川幸治 淡海能を演じる能舞台は表御殿を復元した彦根城博物館のなかでも、とりわけ注目される建物である。表御殿で公的な行政機関の役割をはたした表向の部分は現在、博物館の展示空間として活用され、大名の私的な生活の場であった奥向の部分は往時の姿そのままに復元されている。そのなかで、能舞台は往時の遺構をそのまま移築したものである。移築の際に主要な部材は殆んどが当初の材であり、棟札から享保一四年(一七二九)の建築であることが明らかになった。 ところで、能舞台は近世の初頭、すでに今みる舞台、橋掛り、鏡の間の構成を形づくっていたようだ。能は江戸幕府の武家式楽に定められ、慶長一三年(一六〇八)の幕府棟梁の平内家の技術書『匠明』をみると、「当代広間の図」のなかに、能舞台と主殿の関係が記され、舞台は上段の間の正面に相対する形で、白洲をへだてて向きあっている。上段の間はもっとも格式の高い公的な対面の場であり、同時にもっとも格の高い観能の場となっていたことがわかる。こうした構成をもつ能舞台の遺構は京都の本願寺北能舞台(国宝、天正九年(一五八一)の墨書がある)にみることができる。 もっとも、能舞台の構成がはじめから、こうした形に定まっていたわけではない。一五世紀のなかごろ、京都の洛北、賀茂川と高野川が合流する辺りで行われた「糺河原勧進猿楽」の図をみると、舞台の真後の中心軸線上に橋掛りがとりつけられている。しかし、この時期の能舞台の遺構は残っていない。というのも、当時能舞台は常設ではなく仮設で、臨時に建てられたので遺構はみられないのだといわれている。 じっさい、彦根城表御殿でも、宝暦六年(一七五六)の絵図には、雁行状につながる奥の三室のうち、二室を三間四方の敷舞台に改め、脇座、後座、橋掛りなどに改装している。後座の奥には「はめ」と記され、老松・若竹を描いた羽目板が用意されたのだろう。脇座、橋掛りには「高らん」がめぐらされていたが、観能の場は小さく練習や内輪の舞台として臨時に設けられたものらしい。 やがて、文化一〇年(一八一三)、表向の御殿に本格的な能舞台が構築された。これが、今みる能舞台で、十一代藩主直中の隠居の際に建てられたという。この能舞台は近代になっていく度もの転変をうける。明治維新によって表御殿は政事館と名を変え、廃藩置県で彦根県庁、明治八年(一八七五)には陸軍省の兵舎となり、翌九年は城郭一帯で彦根博覧会がひらかれ、一一年には城内の建物の一部が大津兵舎に移され、他は公売に付されたという。この時、表御殿は姿を消したのだろう。さいわい、能舞台はとり壊されることなく、明治二〇年、大洞山麓の井伊神社に移築された。いっぽう、明治二年戊辰の役での戦死者をまつる招魂社が第三郭の内町、埋木舎の近くに設けられ、その後あいつぐ大戦での戦死者をまつる神社となり、昭和一三年(一九三八)、護国神社と改称し、戦後の二三年には沙々那美神社に、二八年には再び滋賀護国神社と改められた。井伊神社に移築された能舞台は二五年、沙々那美神社に移築され二八年には同じ護国神社境内で引き家で移されている。その能舞台が表御殿の復元による彦根城博物館の建設によって、本来の地に復活することになったのである。 |
|
顧問挨拶 滋賀県立大学能楽部顧問 野間 直彦 本日は、淡海能においでいただき誠に有り難うございます。 能楽部は今年も三人の新入部員を迎えることができました。面倒なことの多いクラブ活動ははやらない学生気質のようで、滋賀県立大学でもクラブ・サークルなどの活動をしている学生の数は多くない中、嬉しいことです。 創部以来指導を頂いている深野新次郎先生に加えて、最近は、昨年独立された深野貴彦先生にも月一回の稽古に来ていただくようになり、一段とパワーアップした感があります。実際、二年生部員のこの一年間の上達ぶりには目を見張るものがあると、顧問の欲目ながら思っております。 今回は、淡海能としては初めて、二番の演能があります。 ひとつは業平の幼なじみで夫婦になった女性が昔を回想する、世阿弥の名作「井筒」です。シテの脇田晴子先生は顧問としてずっと能楽部を支えて来られた方です。ご幼少の頃からの能の実践とご専門の中世史・女性史の研究が融合した井筒が期待されます。ご夫君の脇田修先生は狂言を習っておられ、今回もアイとして共演されます。 もう一つは、熊野の巫女が神がかりになって神楽を舞う「巻絹」です。シテを勤めるR.Mさんは県大一期生の能楽部創設メンバーで、大学院に進んでからも熱心に活動し、後輩達の相談相手にもなっています。学生時代を通じての修練の成果をご覧下さい。なおこの能では私がツレを勤めます。巻絹を届ける期限に遅れたため縛られてしまう役で、仕事の締切に遅れることの多い私には向いているかと気に入っております。 どうぞ楽しんでご覧下さい。ご意見をいただけましたら幸いです。 |
|
連吟・竹生島 延喜聖代の春、醍醐天皇に仕える朝臣は噂に名高い竹生島に参詣に行こうと考えます。 琵琶湖湖岸にやって来た朝臣。そこで釣り舟に乗った漁師と海女に出会い、竹生島まで舟に乗せていってもらうことになります。 一同を乗せた舟はゆっくりと進みます。舟から望む景色はとても美しい。周囲の山々に雪がつもったようにもみえる満開の桜。冬の寒さが戻る日も、沖に漕ぎ出す舟の数はたえません。湖面に映った竹生島の様子は殊に素晴らしい。樹木の影をぬうようにして泳ぐ魚たちは、まるで木に登っているよう。月が姿を映すときには月面に住むうさぎたちも湖面を駆けるのでしょう。 島につくと、漁師は朝臣を弁天堂へと案内してくれました。そして自分たちは実は人間ではないということを打ち明けます。その後海女は御殿の中に消え、漁師は「自分こそはこの湖の主である。」と名乗って湖面に姿を消すのでした。 しばらくすると、御殿が鳴動して先ほどの海女が美しい天女の姿をして現れます。「この竹生島に住み、人々を守っている弁才天とは私のことなんですよ。」そういって弁才天は舞います。空からはたえなる音楽が響き、花が降りかかります。春の夜の月に白く揺れる天女のたもと。見事な舞を見ているうちに時は過ぎていきました。月を映した静かな琵琶湖の湖面に突然波風がたち、漁師が本来の姿、龍神となって現れます。湖上に姿を現した龍神は、光輝く金銀珠玉を朝臣に差出して激しく舞います。 仏の衆生済度の請願はとても深いものです。あるときは弁才天の姿で人々の願いを叶え、またあるときは下界の龍神の姿となって国土を鎮めます。 そうして龍神は弁才天が御殿に帰っていくのを見送り、自らは湖に飛んで入り、大きな大蛇の姿となって龍宮へと帰っていったのでした。
|
|
仕舞・敦盛クセ 平家は世を取って二十数年になる。でも栄えていたのは昔のこと、今では都を追われる身となってしまった。どんな栄光も過ぎてしまっては夢の中のことと何も変わらない。寿永二年、四方から吹く風に秋の木の葉がただはらはらと散っていく。その姿に自分を重ねた。木の葉は船のように波に浮いて、流されていく。もはや夢に逃げることさえできない。 籠の中の鳥が雲を恋しがっている。故郷に向かう雁の群れが列を乱して飛んでいく。そんなあてもない旅の日々。いつしか日も年も過ぎていく、何度目かの春、たどり着いたこの一ノ谷、しばらくはここ、須磨の浦に篭ろうと決めた。 後ろから山風が吹き落ちる。目の前の光景が冴え渡っていく。海際で夜も昼も船が揺れる。千鳥の声の力がなくなって行くのも僕の袖が濡れているのもきっと波のせいだ。きっと。 漁師の小屋に共寝する生活。磯馴松の如く水辺を這い、まるで須磨に住む人のように柴というものを敷いて寝る日々。 どうしてこんなことになってしまったんだろう。思いをめぐらしながらも、ここ、須磨の浦に住み続けるより他にない。こんな生活を続けていく中で、平家一門みんな須磨の人間に成り果てていく。かつての栄光はいったいどこへ行ってしまったんだろうか。 わずか十六歳で戦死し、亡霊となった敦盛は、自分が体験した平家の盛衰を、彼の成長と反比例するかのように落ちぶれていった一族への悲しみを生前得意としていた笛と共に、舞で表したのです。
|
|
仕舞・班女クセ 春に吉田少将と契りを結んだ遊女花子は、それ以来客も取らずに少将と交換した扇を眺めてばかり。ついに宿の主人に追い出されてしまいます。秋になり、吉田少将が花子を迎えに来ますが、花子はすでに宿から追い出された後でした。少将は宿の女主人に花子への伝言を残し、男女の縁を守る賀茂明神へと参拝にでかけます。 一方花子は吉田少将を思って狂女となっていました。秋風を恨みながらも、恋しい人との再会を神に祈ります。 秋までには必ず迎えにくると約束してくださった貴方なのに、その頼みにならない言葉を信じていつまで待てばよいのでしょう。お逢いできない夜は重なり、秋風、嵐、山颪や野分が松の木のもとを訪れても、私が待つ貴方の便りはございません。取り替えた扇に触れて貴方のことを想いますが、ただいたずらに季節が過ぎるばかり。逢うは別れの始まりだとはいえ、我が身が不憫でなりません・・・。 そう語って舞う花子を見て吉田少将は不審に思い、かつて交換した扇を差し出します。互いに扇を見せ合い、相手が想い人であると確認した二人は夫婦となるのでした。 この班女という題名は中国前漢のハンショウヨという女性の名前から来ています。ハンショウヨは成帝に愛された詩人でしたが、やがて寵愛を失い嘆きの詩を詠みました。班女の運命を辿らず少将と結ばれた花子。本当によかったですね。 (ハンショウヨは班■(女偏に捷の旁)妤、と書きます。)
|
|
仕舞・花月クセ 京都・清水寺。筑紫(現在の九州・福岡辺り)から一人の僧侶がやって来ました。数年前、息子が彦山で行方知れずになってしまったのを機に、出家して諸国を修行中の身の上です。 寺院内で、僧は花月と名乗る喝食(寺で雑用などをする有髪の修験者)の少年に会います。花月は流行の恋の小歌や、鶯を射る真似事をしながら舞い、謡います。季節はちょうど春。花月は得意の清水寺にまつわる縁起の曲舞を披露します。寺にある清らかな瀧。その水上の千手観音。霊験あらたかな観音様の功徳により、辺りの枯れ木は緑の葉をつけ、桜の花を咲かせました。今の世にも、そう言い伝えられています。 僧が花月をよくよく見ると、幼い頃失った我が子に面差しが似ています。もしかして……。はやる気持ちを抑え、僧は花月に尋ねます。 「あなたはどこのご出身ですか。」 「私は筑紫の者です。七歳のとき、彦山で天狗にさらわれ、このように諸国を巡っているのです。」 間違いありません。僧は父子の名乗りをあげます。天狗にさらわれてからの、つらい遊行の旅が花月の頭をめぐります。 けれど、父と会えたからにはつらい旅ももう終わり。父と共に仏道に入り、修行に出ることにしましょう。 「花月」は芸尽くしの曲と言われ、その名の通り花月が次々と舞い謡っていくのが見どころです。クセは曲舞のことで、清水寺の縁起を謡った部分です。
|
|
第八回淡海能への道のり 二〇〇二年 十二月 忘年会にて旧役員から新役員へ交代。フレッシュな気分で頑張る! この日第八回淡海能の日付が決まる。まだまだ先のような気がする…… 二〇〇三年 一月 素謡「鶴亀」で新しい年の幕開けだ! 舞囃子の演目「小袖曽我」「杜若」「猩々」が決まる。 二月 OG会さんと合同で新年会。能楽の演目をどうしようかで悩む。 三月 涙涙の卒業式。能楽部員3人がクラブから卒業。最後のおもひで作りにみんなで伊勢へ旅行。伊勢うどんを食べ過ぎる。 卒業生追い出しコンパ。本当にこれで最後です。朝まで語り明かす。 気分をかえ新入生勧誘の準備を始める。あやめ会の練習に励む。 四月 ピカピカの1回生が3人入部。うれしはずかしドキドキ、始めての仕舞「鶴亀」の練習。 能楽「巻絹」が決まる。 五月 素謡と仕舞の会、第六回あやめ会 六月 仕舞「笠之段」「敦盛クセ」「班女クセ」「花月クセ」が決まる。舞囃子「融」が決まる。 七月 素謡「橋弁慶」が決まる。 八月 冷夏にも負けず熱く練習をする。 素謡「橋弁慶」の配役が決まる。よしっ! 九月 マキノ町にて合宿。 そして 十月十五日……! |
|
素謡・橋弁慶 昔々、延暦寺の西塔の近くに武蔵坊弁慶という人が住んでいました。さて、ある日のことです。その弁慶さんが日課にしている五條天神へのお参りに出かけようとすると、一緒に連れて行こうとした従者が変なことを言うのです。 「昨日五条天神に行く橋の上で十二、三歳ほどの子供が小太刀を振り回して人を襲ってたんですよ、今日のお参りは危ないからやめておいたほうがいいですよ」 そんなのどうってことないよ、と弁慶さんは言いますが、従者のかなりのびびりっぷりに止めておこうかなと一瞬思います。けど自分もびびっていると思われるのは嫌なので、退治してやりゃいいや、と出かけることに決めました。 一方その頃、噂の子供牛若丸は今日も五條の橋に来ていました。とはいっても今日は、暴れたことが母親にばれてきつく叱られたので、明日は鞍馬寺に帰ろうと決めて都の名残を惜しむためにここに来たのです。しかし秋風が夜嵐のように強くなり、夜もどんどん更けてきて淋しくなってきた牛若君は、誰か橋を通らないかなー、と思わずにいられません。 そこにやって来た弁慶さん、自分の鎧、薙刀、挙句自分の歩き方にまで酔っている彼は牛若君に気付きません。でも橋板をドカドカ踏み鳴らして歩いてくるので牛若君のほうは気付きます。そして人が来たことに喜び、なぜか女装して弁慶さんに近づいていきます。 弁慶さんのほうも牛若君に気付きましたが女性だと思ったので黙ってすれ違おうとします。出家中の弁慶さん、女性と関わってはダメなのです。しかし、いたずら好きな年頃の牛若君はすれ違いざまに弁慶さんの自慢の薙刀を思いっきり蹴り上げます。 「なにすんだ、この馬鹿! なめんなよ!」 大人の弁慶さんもさすがにキレて戦闘態勢に入りますが、牛若君は全く動じません。それどころか動きが素早くて、押されているのは弁慶さんのほうです。何度も切りかかられて、橋げたを後ずさりながら肝を潰してしまいます。 動揺した弁慶さん、たかが子供一人討ち取り損ねるわけには行かないと、薙刀を持ち直して戦いますが、牛若君にひょいひょい避けられ、さらに薙刀を打ち落とされてしまいました。かくなる上は取っ組み合いだ、と半ば意地になって向かっていきますが、素早い牛若君を弁慶さんは掴むことが出来ません。さすがに途方にくれてしまいます。 しかしそこで切り替えの早い弁慶さん、牛若君の腕前に感心します。 「あなたはいったいどなたです? まだ幼い姿だというのにこれほど勇敢で腕が立つなんて。詳しく名乗っていただけませんか?」 「ぼくは源牛若丸です」 それを聞いて弁慶さんは納得しました。彼は有名な源義朝のお子さんだったのです。 「あなたは?」 今度は牛若君が尋ねてきました。名乗った後、弁慶さんは牛若君に主人になってくれないかと頼み込みます。彼の位も家柄も腕も主人とするには申し分ありません。何よりこの出会いに運命を感じたのでしょう。主従関係を結ぶ約束を堅く交わしたあと、弁慶さんは早速、家に帰る牛若君にお供するのでした。
|
|
舞囃子・小袖曽我 曽我十朗祐成と五郎時致の兄弟は母を訪ねて行きました。理由は父を殺した工藤祐経を討ちに行く前に母に別れを告げるため。そして母の意に背いて元服した弟・五郎の勘当を解いてもらうため。 けれども母は十郎には会っても五郎には会おうとしません。五郎が声をかけると母は「時致とは誰です? そういえば箱根の寺に出家させた箱王(五郎の幼名)という愚か者がそうでしたね。その者は母が出家せよと申したのに聞きもせず元服し、勘当したのにここまで来るとは。ますます許せません」と、突き放します。 十郎は母と五郎を何とか会わせたいと思いますが、母に五郎の事を申したならば十郎も勘当する、と言い渡されてしまいます。しかし十郎は五郎を連れ、再び母に会いに行きました。 十郎は母に「父の敵を討ちに行こうと思いましたが、敵討ちをするのに一人では力が足りないので五郎の勘当を解いて頂き連れて行こうと思いました。しかし勘当を解かれず、さらに五郎の事を申せば私も勘当されるとのこと。例え五郎が出家をやめてしまうことになっても、五郎以外に仲間のいない兄を見捨てるのかとむしろ叱ってこそ母の慈悲というものでしょう。」と説得します。五郎はまだ箱根に居た時、毎日父母の為に祈っていたのに。それなのにこの仕打ち。兄弟は恨み顔で泣く泣く立って出てゆきます。しかしそれをついに母は声を上げて止め、ようやく五郎の勘当は解かれます。二人は嬉しく思い涙を流して喜びました。そして舞を舞います。そして本望を遂げようと勇んで敵討ちへと出かけてゆくのでした。 「小袖曽我」と題がついていながら肝心の小袖が出ていないではないか、と思われるかもしれませんね。実はこの「小袖曽我」の原型となっている「曽我物語」にはちゃんと門出の餞に、と母が小袖を渡す場面があるのですが能には出てきません。今残っている謡本には残っていないので削除されたとしたらよほど以前の事のようです。
|
|
舞囃子・杜若 『伊勢物語』の主人公は在原業平であるとされています。この物語の中で、業平は様々な女性と関係を結んでいます。奈良の姉妹、紀有常の娘、伊勢の斎宮などです。清和天皇の后候補の高子とは駆け落ちまでしています。 その在原業平と縁のある八橋へ諸国を巡る僧がやって来ました。僧が沢辺に咲く杜若を眺めていると、どこからか若い女性がやってきて、八橋の謂れを語ります。もともと、川が蜘蛛の足のように分かれて流れていて、そこに橋が八本架かっていたことから「八橋」の名がついたこと。また、業平が東国に下る途中に八橋に立ち寄り、美しく咲く杜若を見て「かきつばた」の五文字を句の初めに置いた「唐衣 着つつなれにし 妻しあれば はるばる来ぬる 旅をしぞ思う」という歌を詠んだこと。語るうちに夕方になり、その女性は自分の家に泊まるよう勧めます。 家に着くと、彼女は色鮮やかな唐衣を着、冠をつけて現われます。僧は粗末な家にそのような衣装があったことを訝ります。すると、彼女は身に着けているのは高子・業平の形見の唐衣・冠だというのです。続けて自分は業平の歌に詠まれた杜若の精であると、正体を明かします。そして業平は実は歌舞の菩薩の化身であったと言うのです。そのため詠んだ和歌の言葉までも功徳を持ち、歌に詠まれたおかげで、心がない植物である自分までも成仏できたのだと言います。杜若の精はそのことを感謝し、業平の舞の姿を現して亡き業平を弔っているのです。 彼女は更に、伊勢物語についても語っていきます。業平が都を出て広く旅をしたのは衆生を助けるためだったこと。彼が様々な女性と付き合ったのは、彼女たちを菩薩の力で救うためであったと言い、業平を称えます。 杜若の精は夜が明けていく中、明るく美しい舞を舞うとどこへともなく消えていったのでした。
|
|
仕舞・笠之段 難波の春の浦。貧しさ故に妻と別れた男がいた。男は自分の境遇を嘆くわけでもなく時に興じ、芦を売り歩く。そこへ、妻と従者が夫を捜しにやってくる。夫とは知らず、従者は男に声をかけた。 「あなたの芦売りは評判が良いそうですね。ところで、ここをなぜ 「それは仁徳天皇がこの地に皇居をお造りになったからですよ。と、あれをご覧下さい。網引きの漁師たちが、えいやえいやと声をあげて、御津の浜に向かってきます。霞む沖合に浮かぶ小舟、鳴き来る鴎や磯千鳥。和歌にも詠まれた美しい春の難波の浦ですね」 そして男は笠づくしの舞を始める。 「難波の春と言えば梅。その梅に鶯が戯れると、花笠が縫われるのでしょう。鳥といえば、カササギは笠の名を持っていますね。カササギが飛ぶ空には月が光る。月の笠とは天の乙女の衣笠なのでしょう。ここ難波の乙女たちは、雨が降ると、袖や肘を笠の替わりにします。雨の芦辺には波が打ち寄せて、芦がなびきます。ざらりざらり……ざらざら、ざっ。まるで風が簾を吹き上げるような、面白い景色なのですよ」 妻は男が自分の夫であることに気付き、声をかけた。夫は今の自分の身を恥じ隠れてしまう。だが二人は和歌を詠み交わし、再び心を通わせ、一緒に暮らすのであった。 「笠之段」は「芦刈」という曲の中の、笠づくしの舞の部分です。謡も舞も、笠づくしなのです。
|
|
いきなり! 段歌クイズ! 「え~段歌てなにやさ」といわれるのも道理。そこでちろりと説明。段歌とは即ち謡事の小段名。一曲の謡いどころ、舞いどころになっている、いわゆる“○之段”と呼ばれる箇所のこと。上段の仕舞「笠之段」はそのひとつの例。 この段歌、一曲の中心部をなすものが多い。一曲の主題ともなる部分なればクセやらキリの形式に当てはまらぬ謡・舞で表現され聴きごたえ・見ごたえ共に充分。例えば「鐘之段」。これはここ、滋賀県を舞台にした名曲の一部。鐘といえば……そう、言うまでもなく三井寺の名鐘。子と生き別れさ迷い歩く母者が観音菩薩のお告げにより仲秋の名月の元で三井寺の鐘をつく、あの場面である。 そこで。数ある段物からいくつか列挙してみた、それぞれ何の話だか考えておみやれ。 ①「網之段」 網でな、花びらを掬うのじゃ ②「鮎之段」 鮎占いによれば吉と出たぞよ ③「鵜之段」 川に鵜を放って魚をとるのじゃ ④「砧之段」 これが解らぬとは言わせぬぞ ⑤「車之段」 重い思いを車に乗せ引くのじゃ ⑥「駒之段」 月夜に馬を走らせ探すのじゃ ⑦「琴之段」 琴の上手は命を救うのじゃ ⑧「酒之段」 謡曲登場人物一の酒豪かの ⑨「笹之段」 笹で叩くは蜂が刺すに似たり ⑩「簓之段」 簓の代わりに扇を数珠で擦ろう ⑪「薪之段」 秘蔵の薪で持て成す心意気じゃ ⑫「玉之段」 龍宮へ玉を取りに行くのじゃ ⑬「鼓之段」 慰みに時の鼓を打つのじゃ ⑭「文之段」 国許の母から便りが来たのじゃ ⑮「枕之段」 枕元に立たれるのは怖いの ⑯「弓之段」 その少年は弓が得物でな ⑰「夢之段」 人の生とは夢のようなものかの ⑱「輪之段」 茅の輪をくぐり厄を祓おうぞ 有名なものもあるがあまり聞かぬものも。曲趣を考えれば判るものもあろう、れっつしんきんぐ! しんぎんぐできればなお楽しかろ。 答え…①桜川 ②国栖 ③鵜飼 ④砧 ⑤百万 ⑥小督 ⑦咸陽宮 ⑧大江山 ⑨百万 ⑩自然居士 ⑪鉢木 ⑫海士 ⑬籠太鼓 ⑭熊野 ⑮葵上 ⑯花月 ⑰邯鄲 ⑱水無月祓 (参考『能狂言辞典』)
|
|
舞囃子・融五段 源融の旧邸を訪れた旅僧。仲秋の名月が夜空に登るころ、不思議な汐汲の老人に出逢う。 「海から離れていても汐は汲めるのです。ここは六条河原院。位人臣を極めた融大臣が、陸奥国塩竃の浦をそのまま再現なされた場所なのですからな。ですが、月日は流れて邸宅も荒れ果て、もはや旧跡となるばかり。紀貫之もかように詠んでおります。『君まさで煙絶えにし塩竃のうらさびしくも見えわたるかな』と」 僧と共に都の景色を楽しむと、老人は姿を消す。 融大臣の栄華を想い、眠りにつく僧。中空に月がさしかかると、貴公子の霊が現れた。 「塩竃浦の塩焼きに心惹かれ、庭園にその有様を再現した。海には島を配し、名月が出れば舟を浮かべる。そのような風景も今は、はや昔。ここはかつての六条河原院。私こそが屋敷の主人にして、河原左大臣。源融である」 河原院の有様を懐かしみ、名月を愛で舞う融大臣。 「西山に陽が沈まなければ、月は霞んでしまうのだ。例えるならば、月夜に星々が輝けないようにな」 権勢を誇るのは陽光のような藤原氏。政争に敗れ、隠居同然となって月の如く陰に潜む我が身。最後の拠り所であった屋敷で享楽の舞を舞いながらも、月光のもとの融大臣に感じられるのは、ただ哀愁。 「眉墨のごとき漆黒の海に三日月の舟を浮かべれば、魚は釣針だと、鳥は弓だと思うのだろうか。しかし、月が地上に降りることも、水が天に昇ることもない。鳥も魚も、我が家で安心して眠るのだ。そう、我が家でな……」 月も傾き、長い秋の夜も白々と明けていく。鳥がさえずりだし、遠く鐘が鳴る。 「実に楽しい夜であったぞ」。名残を惜しみながら、融大臣の姿は月が沈むようにうっすらと消え、月世界へと溶け込んでいくのであった。
|
|
舞囃子・猩々 『猩々』の謡の中に登場する「菊の水」。これは『菊慈童』という能楽に登場する慈童という少年が、飲んで永遠の若さを手に入れたとされるお酒です。「酒は百薬の長」と言うように、お酒は時には薬となり、人に幸せをもたらしてくれるものともなります。『猩々』もお酒の効用を讃え、めでたさを祝った作品です。 中国の金山の麓、揚子の里に高風という大変親孝行な息子がいました。ある夜高風は夢の中、市場でお酒を売るよう告げられました。その教えに従って市場でお酒を売り始めると、次第に裕福になっていきました。そんな高風のもとへいつも必ずやって来てお酒を飲んでいく客がいました。不思議なことにこの客は、いくら飲んでも顔色が変わりません。そこで高風が名を尋ねると、自分は海中に住む猩々だと答え、水辺で待つよう言って消えました。さてこの猩々とは一体……? “猩々”は古代中国の伝説では、赤い顔をしてお酒を好む、人面豚身や人面猿身などとして描かれています。日本においては本来学術的な名称であり、大型類人猿オランウータンのことをさします。そしてその血で染めたなどと言われることもある、赤い布を 今回の舞囃子はここからです。高風はお酒を用意し
|
|
能楽『井筒』 ― 鑑賞の手引きをめざして ― 「お能は何を言ってるかわからなくて分かりにくい。」というあなたにもぜひぜひ楽しんでいただきたくてお届けする企画です。能面・装束などの説明と謡曲全文及びその訳を用意いたしました。これでお能ももう怖くない! といいのですが。まずは『井筒』とはどういうお話なのかあらすじで流れをつかんでくださいね。より分かりやすくなると思いますよ。 ◆あらすじ◆ 諸国を巡る僧が大和国(今の奈良県)で南都七大寺から長谷寺へと向かう途中、在原寺というところを通りがかりました。寺は荒れ果ててしまっているけれど、ここがどうやら平安時代の有名な歌人・在原業平がその妻である紀有常の娘とともに住んでいた場所らしいと気付きます。旅の疲れを癒し、また業平夫婦を弔っているとそこへ、不思議な雰囲気の美女が現れました。その女性は井戸の水と花を草の生い茂る塚の前に供え、手を合わせています。 僧は業平の所縁の者かと思いその女性に声を掛けました。女性は業平縁故の者であることは否定します。しかし、業平のことは詳しくは知らないが、といいつつも僧に業平とその妻のことを詳しく語ります。結婚後に愛人のもとへ通っていた業平を思いとどまらせた「風吹けば沖つ白波竜田山夜半にや君がひとり行くらん」の歌にまつわる物語や、幼馴染であった二人が結婚するに至った「筒井筒井筒にかけしまろがたけ生ひにけらしな妹見ざる間に」の歌にまつわる物語を。あまりの詳しさに僧は不思議に思い女性にもう一度正体を尋ねます。すると、その謎の女性は自分こそが有常の娘であると正体をほのめかして塚の影にて消えてしまいました。 そこへ、折りよく地元の人がやってきたので僧は呼び止め、在原業平についての話を聞かせてほしいと頼みます。地元の人は急にそんなことを訊ねる僧に戸惑いながらも、自分の聞き知っている話を語ります。語り終えて、どうしてこのような話を聞きたいのか知りたがる地元の人に、僧は先ほど有常の娘らしき人とであった話をします。地元の人は、それは有常の娘の霊に違いないので弔ってあげるようにいい、その場を去ります。 もう一度娘に会いたく思う僧は、夢ならば会えるのでは、と在原寺の苔の上でまどろみます。そこへ現れたのは業平の形見の衣装を身につけた有常の娘でした。昔を懐かしんで舞い、井戸の水に映る自分の男装の姿に業平の面影を見た有常の娘は、夜明けの鐘の音とともに消えていきました。 『井筒』は世阿弥作で、“能楽らしい能楽”の代表だといわれています。『伊勢物語』を典拠にした作品です。有常の娘の美しい姿、美しい恋心を堪能してください。 詳しくはこちらへ ・作り物、面、装束、扇 ・全文掲載(現代語訳付き)
|
|
お能でウフフ 月影さやかに光る夜に。 第八回用に改訂しましたけどあまり変わってません 秋ですね。秋になると月が恋しくなります。涼しくなってきて大気も澄み、月は天高くひときわ凛としたその美しい姿を見せてくれます。今でこそ街は照明で溢れ返っていますがそんなものなかった昔、闇を照らしてくれる月の存在はさぞ大きかったことでしょうね。 今回、『井筒』の解説ページを作るにあたり勉強しはじめて思った、いえ解ったことがあるのですが井筒ちゃん(有常の娘さんのことを私はこう呼んでいます。ほら、だって大体は曲名=シテ名じゃないですかー。菊慈童くん、融くん、花月くん……ええそうですよ、その伝で行けば松虫くん〈虫だろ!〉玄象くん〈琵琶だって!〉竹生島くんですってばもういいいよ!分かってるよ!)って、「幸せ」じゃなかったんですね、一般的な見方をしますと。私はこういうたちなもんですからお能の三番目物や四番目物の恋愛物が苦手で、というより気持ちがよくわからないのです。その中でも井筒ちゃんはラブラブ幸せ光線出しまくりな子だと思っていました。それだのに業平の格好してうっとりするもんですからもう訳わかんね、そんなに好きなら業平の側にいたらいいじゃん、なんて思ってたのですね、正直なところ。しかし、中世の人が『伊勢物語』をもとにみんなで作り上げた井筒ちゃん像というものが鮮明になってくるにしたがい、井筒ちゃんに申し訳なく思えてきました。 中世の人が思ってた井筒ちゃんってね、こんな人生送ってるんですよ。
……とまあ、こういう人生なんです。待ち続け、じゃないですかこれじゃあ!「待つ女」とも呼ばれたっていってましたっけね、井筒ちゃん……しかも、こんな最期だなんて。これじゃ死後に一緒にいるのは無理ですよね。業平くんの回りは今も女の人がいっぱいなんでしょうしね。ああ、そんな井筒ちゃんにとって人生の山場はまさしく業平が求婚の歌を送ってきてくれた時だったのでしょう。歌人として名高き業平が誰でもない、自分に自分のことを想って詠んでくれたのですから。だからお能でもあんなに何度もあの歌を口ずさんでいたのか……。井筒ちゃんのこと、ちょっとわかった気がしました。お能って優しいですね。そういう、人の陰をもやさしく見つめてくれているのですね。人は必ずしも幸せばかり感じて生きるわけにいきません。共感を呼ぶ『井筒』が人気曲であるのもうなずけます。 そんな井筒ちゃんを見守ってくれているのは旅のお坊さまですが、詞章を読むともう一つ、見守ってくれている存在がある事に気付きます。井筒ちゃんが登場した時、「忘れ」「偲ぶ」「何時まで」と草の名をちりばめて謡うところがありますね。そのきっかけとなった名も無き草。その、傾いた軒先に生えて風に吹かれながらも月の光に照らしだされている姿、井筒ちゃんの姿と重なり合いませんか? そうです。もう一つの存在はお月さまだと思うのです。名のある草も無い草も…ただ有常の娘とだけ呼ばれる子も分け隔てなく照らしてくれるんですもの、ウフフ。
|
|
素謡・紅葉狩 「わたしは、この辺りに住む女。この山に紅葉を見に来ました。いずれの枝も赤く染まり、谷川の流れも散り浮く紅葉で埋め尽くされています。ここでしばらく眺めましょう。」 「私は平維茂。この山に鹿狩りに来た。九月も二十日(旧暦)ともなると木々の梢は錦のごとく色づき、まことに風情がある。先ほど人影が見えたので部下に名を尋ねさせたが、その女性と侍女たちはさる御方というだけで名前はおっしゃらぬ。どなたであれ高貴な御方が酒宴半ばというなら、邪魔をせぬよう下馬して足音を立てず過ぎ行こうとしたが。」 「どうかお立ち寄りくださいまし。通り雨に一樹の陰で共に雨宿りするごとく、これも何かのご縁です。どうぞわたしをお見捨てにならないで。行ってしまうとおっしゃるなら、恥ずかしながら貴方の袂にすがってでもお止めいたしますわ。」 「遠慮して通り過ぎるつもりだったが、これほど魅力的な女にすがられては堪らない。私とて岩や木ではない。その誘惑に負けた。女はこの世の人とも思えぬほどに麗しく、我が胸はうち騒ぐばかりであった。勧められるままに酒を飲み、女の美貌に心は乱れてしまう。我々のこんなにも酔いに乱れた姿を他人が見たなら、どう思うことだろう。」 「仕方ないですわ。わたしたちは、前世での契り浅からぬ深い情の仲なのですよ。」 「紅葉は燃えるように赤い。酒は美味い。そして女の舞う姿は素晴らしく美しかった。酔いが回ってきて、私の意識はいつしか薄れていった…。」 「あら、寝ていらっしゃるの……そのままぐっすりとお休みなさい、夢から醒めずに……。」 「しまった。不覚にも酒に酔って眠っていた。そのまどろみの中、夢のお告げを聴いた。目を覚ますと不思議なことだ。夢の告げどおりに、女と侍女たちが鬼女の本性を現して炎を放っている。しかし私は恐れなどしない。南無八幡大菩薩と心に念じ、剣を抜いて待ち構えていると鬼女は飛び掛ってきた。大立ち回りの末に、剣を恐れて岩へ登ろうとした鬼女を引きずり下ろし刺し通して、たちまち退治することができたのだった。」
|
|
番外仕舞・老松 平安時代。当時右大臣で、現在は学問の神として祀られている菅原道真は、藤原氏の策略により大宰府に左遷されました。その際に家の梅の花を見て詠んだ歌。『東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ』都から大宰府への東風が吹いたならば、風に託してその香を送っておくれ。主人がいなくなっても春を忘れるのではないよ。その歌に感じ入った梅の枝が裂けて、都から大宰府に飛び来て花を咲かせました。その後、同じく菅公が寵愛していた松も大宰府の庭に枝を交わしました。この梅と松を、それぞれ『飛梅』『老松』といいます。 時は過ぎ。ある夜、天満宮信仰者の梅津(都の西側の地方)の某という男が、夢の中で神託を受けます。『筑紫の大宰府・安楽寺に参詣せよ。』と。その霊夢の通り安楽寺に参詣し、かの有名な飛梅のことを花守の翁に尋ねます。翁は飛梅が紅梅殿と呼ばれて崇められていることを教え、飛梅にのみ心惹かれている男に老松の方へと注意を促します。そしてさらに、梅や松が祀られているいわれや、中国でもこれらの木が好まれていることなどを詳しく語りました。 その夜、梅津の某は老松のそばで旅居し、神のお告げを待つことにしました。そして深夜、老松の精が姿を現したのです。それはなんと、昼間の花守の翁でした。老松の精は、遠方からの来訪をねぎらい、舞楽を奏でます。『君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて……』現在国歌にも使われているこの歌を謡い、今は泰平となった御代の春を祝ったのです。
|
|
番外仕舞・蝉丸 逆髪・蝉丸は醍醐天皇の皇女・皇子であった。蝉丸は生まれつき盲目であったため成長した後、父帝の命で出家させられ、逢坂山に捨てられる。それは、盲目なのは前世の悪業のためであり、山野で暮らすことで罪を償わせ、来世では救われるようにしようという親の愛からであった。そうして捨てられた蝉丸の孤独を慰めるものは琵琶だけであった。 一方、蝉丸の姉の逆髪は折につけて狂乱し、しかも髪が逆立ち、撫でても下がらない。そのため、今は宮中を出て辺境の地をあてどなく放浪していた。 逆髪は京の都を出て彷徨い行く。鴨川・白河を渡り、着いたのは粟田口。都に心を残しつつも音羽山を後にする。松虫・鈴虫の鳴く山科の里人たちよ、狂女だからといって咎めてくれるな。心はここを流れる清瀧川のように清いのだから。近江の国に入り、水の湧き出でる走井に姿を映す。見れば髪は乱れ、自分でも浅ましいと思うほど。これが現実の姿だと逆髪は嘆息する。 逆髪がふと気づくと、近くの藁屋から琵琶の音が聞こえてきた。それも粗末な藁屋には似合わない高貴な音。音に惹かれて近づくと、なんとその琵琶を弾いていたのは弟蝉丸であった。いつの間にか逢坂山に着いていたのだ。二人は再会を喜び、互いの境遇を嘆きあう。名残は尽きないが、二人でいても傷を舐め合うだけだ、と逆髪は旅立って行く。
|
|
番外仕舞・車僧 車僧とは諸国を巡り歩く僧侶の事です。今回ここに出てくる車僧――深山和尚は洛外太秦の海生寺の僧で、常に破車に乗って遊行していたので車僧と呼ばれていました。また、七百年もの昔を語るので、七百歳とも呼ばれていました。 その車僧がある冬の雪の日に、都の郊外・嵯峨野の西山の麓にやってきました。車をとめて辺りの景色を眺めていると声をかけてくる山伏がいます。車僧が何の用かと問うと、その山伏は車僧に禅問答をしかけます。しかしここは車僧。山伏、実は愛宕山の天狗・太郎坊に平然と論じ返します。しばらく問答を繰り返した後、太郎坊は分が悪いと判断して、再び対峙する為に自分の住む愛宕山の庵にお入りあれと言い残し、黒雲に乗って夕方の愛宕山に消えてゆきました。 さて、場所は変わって雪が降り積もる愛宕山。太郎坊は本来の天狗の姿で現れ、車僧を「魔道にも心を寄せよ車僧」と天狗道に誘います。しかし車僧、そのような誘いには惑わされません。すると天狗は車僧に今度は行比べを挑みます。しかし車僧は人も牛も引いていない車を法力で動かしてみせ、天狗は行の力でも打ち負かされてしまいました。 またも打ち負かされてしまった天狗は車僧の力に恐れをなし、魔障を和らげると合掌して消えてゆきました。 仕舞はこの天狗が負けて心を改める場面となっています。あの大天狗が負けてしまうほどなのですから、車僧の力はとても大きなものだったのですね。
|
|
能楽『巻絹』 ― 鑑賞の手引きをめざして その2 ― 「お能は何を言ってるか分からないから解らないよ。」というあなたにもぜひぜひ楽しんでいただきたいのです、私としましては。まあ、全部分からなければ面白がれないものだとも思わないのですが、それは上手な方の舞台に限ってのこと。見てるうちにただただだるくなってくる恐れがありますのでそういう時はこの企画ページを見て気を紛らわせてください。まずは『巻絹』とはどういうお話なのかあらすじからどうぞ。これが分かってるだけでもだいぶ違いますよ。 ◆あらすじ◆ ある夜、天皇が霊験あらたかな夢を見ました。それがどんな夢かは分かりませんが、ともかく巻絹――軸に絹の布地を巻きつけたもので高級品です――を千疋、三熊野に納めるようにとの宣旨が下されました。そこで天皇に仕える臣下が熊野本宮にお出でになり、諸国から納められる巻絹を待ち受けているところです。ただ、ほぼ集まったのですがまだ、都から納められるべき巻絹が到着していません。 そのころ、当の都の巻絹を納める担当のものは旅の途中でした。三熊野への旅は初めてです。見知らぬ土地へ行く事で少し心細くなり、また、遠い道のりに音をあげそうになりながらもひたすら三熊野へと向かっています。そして、ようやく到着しましたがまずは音無の天神へ参詣。そこへ、どこからともなく梅の香りが漂ってきました。どこに咲いているのだろう、と探してその梅の姿に心惹かれた都の男は歌を一首詠み、心のうちに天神に手向けました。それから、臣下の待つ熊野本宮へと急ぎました。 熊野本宮へ巻絹を持って到着した都の男。しかし、約束の日より遅れていたので臣下に咎められ、罰として縛られてしまいます。そこへ巫女が現れました。 「その人をなぜ縛るのですか」 巫女は言います。この人は私に和歌を手向けてくれた人なのだから許すように、と。その、巫女らしくないものいい、雰囲気。どうも、音無の天神が巫女に乗り移っているようです。しかし、臣下は都の男のような身分の低い者が歌を詠むとは思えず、巫女の言う事を信じようとしません。そこで、巫女は言います。それならば、あの物に上の句を言わせるがいい。私が下の句を続けるから、と。 音無にかつ咲きそむる梅の花 匂はざりせば誰か知るべき 巫女は都の男の縄を解きます。そして巫女は和歌の功徳を語り始めます。 事態を了解した臣下は、ついた神におあがりいただくため祝詞を奏上するように巫女に言います。 巫女の祝詞、そしてそれに続く神楽が始まります。巫女は御幣を打ち振るいながら熊野におわします神仏の事を語ります。そして狂乱が最高潮に達した時、神はあがるのでした。 詳しくはこちらへ ・面、装束、作り物 ・全文掲載(現代語訳付き)
|
|
滋賀県立大学能楽部の歩み 一九九五年度 6.13誕生。0歳 ◇開学と同時に創部。顧問は脇田晴子先生。 ◇深野新次郎先生をご紹介いただく。 ◇部員数8→6→5→6 ◆第一回湖風祭公演 たぶん11.2 〈仕舞〉鶴亀・経正クセ・船弁慶クセ・紅葉狩・玄象 ◇着付けに手間取りお客さんを小一時間待たす。言語道断の事。 一九九六年度 1歳 ◇部員数6→7→9→10 ◇満を持して? 自演会(淡海能)開催。 ◆第一回淡海能 10.5 〈連吟〉鶴亀〈仕舞〉鶴亀・吉野天人・羽衣キリ・胡蝶・玄象・嵐山・経正キリ・花月クセ・猩々〈素謡〉橋弁慶・吉野天人・土蜘蛛〈番外仕舞〉竹生島 ◇能もないのに淡海能とはこれ如何に。 ◇この深野先生の番外仕舞から「竹生島・勝手にご当地ソング化運動」開始。 ◆第二回湖風祭公演 11.3 〈仕舞〉鶴亀・船弁慶クセ・経正クセ・花月クセ・胡蝶・小袖曽我・班女・玄象・吉野天人・敦盛クセ・嵐山・紅葉狩・田村クセ・経正キリ・羽衣キリ・猩々 一九九七年度 2歳 ◇部員数10→9 ◇調子に乗ってあやめ会も開催。 ◆第一回あやめ会 5.10 〈連吟〉竹生島〈仕舞〉鶴亀・清経キリ・羽衣クセ・雲雀山・嵐山・花月クセ・班女キリ・羽衣キリ・小鍛冶キリ〈素謡〉土蜘蛛 ◆第二回淡海能 9.28 〈連吟〉竹生島〈仕舞〉嵐山・小袖曽我・花月クセ〈素謡〉鶴亀・大佛供養〈舞囃子〉玄象・吉野天人・羽衣・敦盛・胡蝶・猩々 ◇舞囃子に初挑戦。能に一歩近づいた? ◆第三回湖風祭公演 11.1 〈連吟〉竹生島〈仕舞〉鶴亀・小袖曽我・羽衣キリ・雲雀山・小鍛冶キリ・嵐山・船辨慶・玄象クセ・花月クセ・田村キリ・猩々〈舞囃子〉吉野天人・敦盛 ◇舞囃子とはいえテープ。しかも雨に濡れながら闇の中で。虹が美しい日だった。 一九九八年度 3歳 ◇部員数9→12→11→7 ◆第二回あやめ会 6.13 〈連吟〉鶴亀〈仕舞〉嵐山・敦盛クセ・羽衣キリ・大江山・鞍馬天狗・高砂・菊慈童・鶴亀・田村キリ・杜若・小袖曽我・融〈素謡〉竹生島 ◆第三回淡海能 10.14 〈仕舞〉胡蝶・猩々〈素謡〉橋弁慶〈舞囃子〉高砂・小袖曽我・融・鞍馬天狗〈能楽〉竹生島 ◇能が出せて、名実共に能楽部・淡海能。 ◆第四回湖風祭公演 11.8 〈連吟〉橋弁慶・吉野天人・竹生島〈仕舞〉鶴亀・清経キリ・胡蝶・菊慈童・玄象・嵐山・花月クセ・羽衣キリ・紅葉狩クセ・鞍馬天狗・猩々・高砂・田村キリ・杜若キリ・小袖曽我・大江山・小鍛冶キリ ◇昨年の失敗を考慮しこの年から湖風祭公演は交流センター内で連吟と仕舞、というスタイルが定まる ◇あれから四年。初の卒業生を送り出す。 一九九九年度 4歳 ◇部員数7→12→11→8 ◆第三回あやめ会 5.30 〈連吟〉鶴亀・竹生島〈仕舞〉小鍛冶キリ・経正キリ・松風キリ・天鼓・嵐山・田村キリ・胡蝶・猩々・花月クセ・敦盛クセ・杜若キリ・鞍馬天狗〈素謡〉羽衣 ◇実は合宿のスイカ割はこの年始まった。 ◆第四回淡海能 10.15 〈連吟〉竹生島〈仕舞〉鶴亀・敦盛クセ・班女クセ・小袖曽我・羽衣キリ〈素謡〉土蜘蛛〈舞囃子〉胡蝶・菊慈童・海士・猩々〈能楽〉小鍛冶 ◆第五回湖風祭公演 11.14 〈連吟〉竹生島・大佛供養・土蜘蛛〈仕舞〉鶴亀・田村キリ・小袖曽我・玄象・花月クセ・経正キリ・班女クセ・鞍馬天狗・敦盛クセ・清経キリ・胡蝶・羽衣キリ 二〇〇〇年度 5歳 ◇部員数8 ◇卒業生が集まって彦根に深野新次郎先生のお稽古場ができ、なんとなくOG会を作ろうかという気運が高まる。 ◆第四回あやめ会 6.3 〈連吟〉竹生島〈仕舞〉嵐山・敦盛キリ・花月クセ・経正クセ・杜若キリ・花月キリ・経正キリ・松虫キリ・鞍馬天狗〈素謡〉大佛供養・羽衣 ◆第五回淡海能 10.10 〈連吟〉鶴亀〈素謡〉竹生島〈舞囃子〉敦盛・班女・杜若・巻絹・小袖曽我・融〈能楽〉羽衣 ◆第六回湖風祭公演 11.12 〈連吟〉吉野天人・羽衣〈仕舞〉鶴亀・清経キリ・胡蝶・菊慈童・嵐山・経正クセ・花月クセ・融・松虫キリ・杜若キリ・花月キリ・鞍馬天狗 ◇この年、部員に変動なし。 二〇〇一年度 6歳 ◇深野貴彦先生によるご指導も開始。 ◇部員数8→9→8→7 ◆第五回あやめ会 5.27 〈連吟〉鶴亀〈仕舞〉高砂・菊慈童・籠太鼓・小鍛冶キリ・雲雀山・天鼓・大江山〈素謡〉吉野天人・橋弁慶 ◆第六回淡海能 10.14 〈連吟〉竹生島〈仕舞〉羽衣クセ〈素謡〉菊慈童〈舞囃子〉高砂・半蔀・猩々・葛城・天鼓バンシキ〈能楽〉船弁慶 ◆第七回湖風祭公演 11.11 〈連吟〉鶴亀・放下僧小歌・菊慈童〈仕舞〉小鍛冶キリ・胡蝶・籠太鼓・松虫キリ・大江山・経正クセ・船辨慶クセ・猩々 二〇〇二年度 7歳 ◇部員数7→10→7 ◇旧暦三月十五日、竹生島詣。 ◆第七回淡海能 10.4 〈連吟〉竹生島〈仕舞〉小袖曽我・胡蝶・花月クセ・賀茂・殺生石・野守〈素謡〉土蜘蛛〈舞囃子〉雲林院・玄象・融五段〈能楽〉菊慈童 ◇メディア戦略が効を奏す。 ◆第八回湖風祭公演 11.10 〈連吟〉竹生島・吉野天人〈仕舞〉高砂・清経キリ・松風・班女クセ・嵐山・経正クセ・杜若キリ・大江山・土蜘蛛 二〇〇三年度 8歳 ◇部員数7→10 ◇顧問が野間直彦先生に。部員にして顧問。 ◆第六回あやめ会公演 5.24 〈連吟〉鶴亀〈仕舞〉竹生島・杜若キリ・柏崎道行・鞍馬天狗・嵐山・清経キリ・雲林院クセ・羽衣キリ・敦盛クセ・胡蝶・網之段・富士太鼓・猩々〈素謡〉吉野天人・土蜘蛛 ◆第八回淡海能(10.15今やってます!) 〈連吟〉竹生島〈仕舞〉敦盛クセ・班女クセ・花月クセ・笠之段〈素謡〉橋弁慶〈舞囃子〉小袖曽我・杜若・融・猩々〈能楽〉巻絹 以下次号。(ほんと?) |
|
いかごはん梅子がお贈りする 仏でオホホ 巻物は紐解いてこそ。 お久しゅうございます、梅子です。最後にお会いしたのは第三回淡海能冊子……かれこれ丸五年前ですか。その当時より存知よりの方も、始めましての方もよろしくお願いします。さて、五年もの沈黙を経て私が帰って参りましたのにはそれ相応の理由がありましてよ。そう、「巻絹」です。梅ときて仏ときましてはね、ちょっと浮かれてしまうんですね。 いろいろ出てこられる仏様の中でも、やはり一番のエピソードは行基さんと婆羅門さんの和歌のやり取り。お二人ともさすがだわ。詞章に引用されている和歌は少し文字や言葉が変えられていますが、元の歌はこういうものなのです。 ・霊山の釋迦の御許に契りてし真如朽ちせず相見つるかな (謡曲中では「霊山の釋迦の御もとに契りて眞如朽ちせず逢ひ見つ」) ・伽毘羅衛に共に契りし甲斐ありて文殊の御顔を相見つるかな (謡曲中では「伽毘羅衛に契りしことのかひありて文殊の御顔を拝むなり」) さて、昔々。聖武天皇が東大寺を建てなすった時に、外国からも大勢のお坊さんがその開眼式典に参加するために来日しました。その一向を迎えに難波浦まで行った行基さんは、船から降りてきた一人のお坊さまを見ると、微笑みました。お坊さんもまた、行基さんを見て微笑みました。そして二人は歩み寄って手を取り合い、上記の和歌を詠みあったのです。 その様子を見ていた人々は驚きました。「知り合いなの?」「前世での約束が叶ったのか!」「一緒にお釈迦さんの元で修行してたんだって?」「インドのお坊さま、日本語で和歌詠めるのか!」などなど。ともかく、この和歌で二人の偉人のことが知れたということです。 さて、このお話。日本人の心をくすぐると見えまして実に多くの本に掲載されています。 『太平記』『袋草紙』『拾遺集』『今昔物語』『源平盛衰記』『為兼卿和歌抄』『古事談』『日本往生極楽記』『大日本国法華経験記』『扶桑略記抄』『三宝詞』そして『沙石集』。これだけは何とか追いかけました(他にもご存知だったら教えて下さいな)が、ここで重大問題が発生。上記の本の多くが、謡曲「巻絹」とは歌の作者を逆に伝えています。「伽毘羅衛に~」を行基さん、「霊山の~」を婆羅門さんが詠んだ、とする本がほとんど、というか上記の十二冊中、太平記だけです、謡本と同じなのは。あらら。 和歌なんてどっちが詠んでもよさそうなもんじゃん、と思われるかもしれませんけどね、このやり取りだと「どっちが文殊さんだったのか」が変わってきますものね。ちょっと気になります。ちなみに、もうお一方は普賢さんだった、と言われています。お釈迦さんの元で修行してたのって、そのまま釈迦三尊像ですね! ところで疑問なんですけど、巻絹はなんで巻絹という曲名になったのかしらね? 持っては来てもあっさり片付けられちゃって誰もそのことに触れませんものね。天皇さんの夢と関わりがあるのかかしら。でもまさか「ミクマノニマキギヌヲセンビキオサメヨ」と聞いただけではないですよね、それではあまりあらたかな霊夢とは思えませんもの。そこはそれ、見終わった後天皇さんが盛り上がっちゃって「三熊野に贈り物をしなくちゃね! そうだ、巻絹がいいだろう」と思ったというような展開が望ましいですよね。 あ。やっぱりだめ。だって、持って行かされるのは一般民衆ですもの。きっと余分に税を取られたってのが本当の所でしょう。となると、夢の内容は「三熊野に巻絹(もしくは同価値の何か)を収めることは国民みんなのためになる!」と思えるような内容であって欲しいですね。神様・仏様が千疋もの絹を何に使うのかな? 価値あるものだから、要はお金を納めてるのとおんなじ事なの? 他の物でもよかったのかしら。当時、一般的だったとしたらきっとお米ね。でも重たいわよね。地域の特産物も日持ちしなかったり季節物ですぐには手に入らなかったりでいきなり納めさせるのは無理だったのかも。やっぱり上納品としては絹が最良なのかしら。ああ、中世の庶民の暮し向きが分かってないからこの方面には弱いわね。 さて、ここで終わってはせっかく私が出張った意味がなくてよ。そこで大胆な仮説……というか妄想を披瀝してしめくくるといたしましょう。巻絹って、舞台でははふはふと折った布を棒の先につけた物で表していますが、ホンモノは軸にくるくると生地を巻きつけたものなんですってね。巻き絹、っていうくらいですものね。そこで思い至ったわけです。軸に巻くものは他にも知ってるわ……それは、絵巻物よ! 手紙やお経も巻くけどそれは紙よね。絵って、絹に描く場合多いわよね、“絹本着色”っていうじゃない?。 「巻絹」の巻絹って、熊野を中心とする神々仏々の縁起や曼荼羅が描かれているイメージなのじゃないかしら。集められたたくさんの巻物、そして都の男の縄が解けた時にその巻物も紐解かれ、そして一代絵巻、というか大曼荼羅が繰り広げられた、というわけ。どう? 私はイケテルと思うんだけどなー。でもちょっと無理やりでこじつけっぽいわね、オホホ。
|